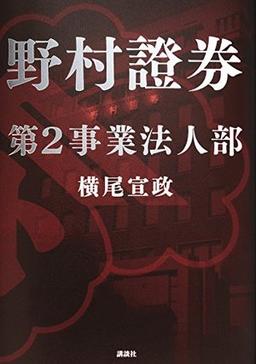ノルマとの闘い
都銀より清らかに思えた

「エラいところに来てしまった」。1977年、京都大学4年生のころだ。就職活動中の著者は、三井銀行から内定をもらっていたものの、いわゆる「囲い込み」に疑問を感じていた。
そこで当時、神姫バスの専務だった父に相談すると、野村證券のある支店長を紹介され、その優秀さにほれこんだ。面接に行くと、出されたのはコーヒー1杯。「なんて清らかな会社だ」と感動し、証券自体にはまったく興味がなかったが入社を決めた。なお後に、このときコーヒー1杯しか出なかったのはたまたまだったということがわかる。
78年に入社した著者は、軍隊のように厳しい「野村イズム」の刷り込み研修を終えて、金沢支店(石川県金沢市)に配属された。直前の不祥事でぼろぼろの支店だった。
配属初日、先輩からはいきなり「今日から毎日、管内の社長の名刺10枚集めてこい」と言われ、入社をひどく後悔した。パワハラという言葉などない時代だ。
とんでもない場面に出くわしたこともある。ある日の応接室での出来事だ。ノルマを果たせない課長代理が、上司に怒鳴りつけられていた。その横には奥さんの姿があった。「こいつのために、みんなが迷惑してるんです。奥さん、どうにかしてください」。見てはいけないものを見た気がした。
ついたあだ名は「社長さん」
著者が入社した78年に、悪夢の投資商品が生み出された。表面利率6.1%の10年物国債、通称「ロクイチ国債」だ。政策金利の引き上げで利回りが急上昇し、額面に対する債券価格が大暴落したため、買った瞬間から値が下がり続ける代物だった。
この国債の販売に全力で取り組んだのが野村證券だ。こんな商品にノルマが課せられていては大変である。実際、同期の離職率は4割にも及んだ。しかし稼げば何でも許されるという能力主義の社風に、著者はマッチしていた。「土下座の横尾」と呼ばれるほどがむしゃらに働くうちに、どん底だった金沢支店も立ち直っていった。
驚くべきことに当時、営業マンは自分で客に勧める銘柄を決められず、各営業本部が決めていた。ほぼ同一の株価の銘柄を売り買いすることで株価を引き上げる、いわゆる「仕切り商い」だ。野村が取引手数料(コミッション)を儲けるためにつきあわされた客は、ほとんどが大損した。
こんなことを続けるうちに、「野村は絶対に潰すべきだ。それにはオレが社長になるしかない」と口走るようになった。周囲からは「社長さん」と呼ばれた。
「コミッション亡者」と呼ばれて
試し打ち人事

「大栄転だ」。81年12月、金沢から異動となり、第2事業法人部に配属されることになった。著者は当時、まだ27歳である。通常なら2支店を経験した30代の社員が行く部署だ。ひどい状態だった金沢支店を立て直したことが、田淵義久常務(後に社長)によって高く評価された。
事業法人部は、第1と第2に分かれていた。人員はそれぞれ25人ずつで、両部で首都圏の上場企業とその子会社を担当する。その数は約1000社だ。まさに証券会社のメインエンジンともいうべき部署である。支店が客に販売する増資分の株式や、新規発行の転換社債(CB)、ワラント債(新株引受権付き社債、WB)を数多く入手するのがおもな仕事だった。
この花形部局で「コミッション亡者」と揶揄されながらも、著者は結果を出していった。
トリプルメリットとウォーターフロント
85年、プラザ合意による急速な円高により、日本の輸出産業は大きな打撃を受けた。この窮地に対して、野村は2つの戦略をしかけることにした。