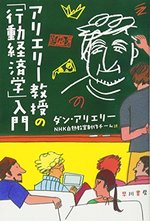オリンピック秘史
120年の覇権と利権
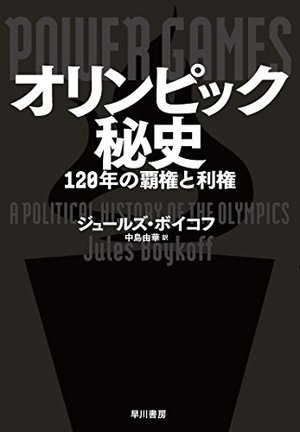
著者
ジュールズ・ボイコフ (Jules Boykoff)
1970年生まれ。パシフィック大学政治学教授。元プロサッカー選手であり、バルセロナ五輪の米国代表メンバーとしてブラジル戦やソ連戦などの国際試合に出場した経験をもつ。2014年、NHKの国際討論番組「グローバルディベート WISDOM」に出演し、「世界が語る“21世紀のオリンピック”」というテーマで為末大氏らと議論を繰り広げた。
1970年生まれ。パシフィック大学政治学教授。元プロサッカー選手であり、バルセロナ五輪の米国代表メンバーとしてブラジル戦やソ連戦などの国際試合に出場した経験をもつ。2014年、NHKの国際討論番組「グローバルディベート WISDOM」に出演し、「世界が語る“21世紀のオリンピック”」というテーマで為末大氏らと議論を繰り広げた。
本書の要点
- 要点1発足当初から、オリンピックは排外主義と協調主義というパラドックスを抱えていた。
- 要点2「オリンピックは政治や商業主義とは一切関わらない」としながらも、実際には政治と不可分であり、商業化しているのも事実である。
- 要点3一般市民から支持を得るため、オリンピックの経費は最初、低く算出される。
- 要点4「オリンピックには高い経済効果がある」という説はかなり疑わしい。オリンピック開催に積極的な都市も減ってきている。
- 要点5真の改革を果たすためには、まず膨らみつづける開発費用を抑えなければならない。
要約
オリンピックの復活
すべてはとある男爵の野望から

Purestock/Thinkstock
オリンピックの創始者であるピエール・ド・クーベルタンは、スポーツを心から愛していた。そして古代ギリシャのオリュンピア大祭を復活させたいという野望を抱いていた。「オリンピズムとは、努力と律動的調和という2つの要素からなる原則に由来する精神のありようである」と語っていた彼にとって、オリンピックとは単なるスポーツの祭典ではなく、むしろ宗教的な儀式だった。またクーベルタンは多様性を重んじ、スポーツによって平和は築けると信じていた。
とはいえ彼の発言には矛盾も多い。平和を強調する一方で、スポーツを「間接的な戦争準備」と表現したり、スポーツに必要な一連のスキルはそのまま戦争に活かせると語ったりしたこともある。
加えて彼の見解も、当時の人間らしい偏見にあふれていた。「オリンピックは万人のためのものである」と言いながら、最初から枠に入れてもらえない選手が数多くいたのだ。人種に関しては比較的穏当な発言が多かったものの、性別、階級、アマチュアリズムに関するクーベルタンの見解は、多くの論争と混乱を招いた。たとえばクーベルタンは女性のオリンピック参加を好ましいものとは見なしていなかったし、「参加者はかならずアマチュアでなければならない」という持論を固持することで、多くのトラブルを招いた。
クーベルタンが一線を退いた後も、オリンピックは排外主義と協調主義という矛盾を抱えたまま、危険な綱渡りをくりかえしていく。
「オリンピック」はいくつもあった
1900年代初頭から、世界各国で婦人参政権を要求する運動がさかんになった。にもかかわらずオリンピックは、女性が参加できる種目を一部に限定しつづけた。
これに不満を覚えた人たちは、1921年10月31日に国際女子スポーツ連盟(FSFI)を創設し、女子オリンピックを開催した。女子オリンピックは1922年~1934年の間に4回開催され、それなりの成功を収めた。結局FSFIは1936年に消滅してしまったが、これがきっかけでいくつかのオリンピック種目が女性に開放された。
またオリンピックに代わるイベントとして、労働者オリンピックという催しもあった。ナショナリズムにまみれたオリンピックとは違い、そこではあらゆる人種、民族、性別の人が歓迎された。おもにヨーロッパの社会主義者が主催し、1925年から1937年にわたって開催された。その後は社会主義と共産主義の分裂に苦しみ、最終的には第二次大戦の勃発によって打ち切られた。
女子オリンピックや労働者オリンピックなどの代替イベントは、IOC(国際オリンピック委員会)に大きな衝撃を与えた。しかしその一方で、オリンピックの威信とステータスは無視できないまでに大きくなっていた。
オリンピックと政治経済
オリンピックは政治と不可分である
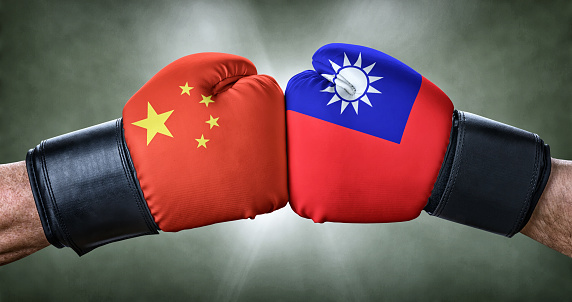
Zerbor/iStock/Thinkstock
オリンピックの質が大幅に高まったのは、ソビエト連邦(ソ連)が参加してからだ。彼らは最初、オリンピックを「ブルジョワ的」と否定していたが、1940年代からオリンピックへの参加をふたたび望むようになった。
IOCは1951年5月、ソ連の受け入れを正式に決めた。これにとくに強く反応したのがアメリカだ。ソ連の加入により、アメリカの競争意識は確実に高まった。1952年のヘルシンキ大会は、さながら代理戦争の様相を呈した。スポーツが「外交の武器」という性質を帯びるようになってきたのはこの頃だ。
こうした事態をうけて、IOCは「オリンピックは政治にいっさい関わってはならない」という立場を強調した。ヘルシンキ大会でIOC会長に選出されたエイブリー・ブランテージも、「われわれはオリンピック・ムーブメントへの政治介入を積極的に排除し、オリンピックがなんらかの組織によって道具もしくは武器として利用されることに断固として反対する」という声明を出している。
ただしオリンピックと政治が切り離せないのも事実だ。自由主義と共産主義の政治的対立の煽りをうけ、いくつもの国が一時期オリンピックをボイコットしている。とくにIOCを悩ませたのが「2つの中国」問題だ。中華人民共和国(中国)も中華民国(台湾)も、もう一方をオリンピックから追放することを望んでいた。そこでIOCは妥協策として、台湾政府に国名の変更を求めたのだが、この国名変更には多くの批判が集まった。
加えてアパルトヘイト政策を掲げる南アフリカも、IOCにとって頭の痛い問題だった。当初IOCは南アフリカの人種差別問題を無視していたが、反アパルトヘイト運動はもはや無視できないほどに広がっていた。最終的に南アフリカはアパルトヘイトが廃止されるまで、オリンピックへの参加ができないことになった。スポーツを利用した政治的な問題提起が有効と証明された瞬間だった。その後も多くの抗議活動が、オリンピックに絡めたかたちで行なわれた。
商業化するオリンピック

Medioimages/Photodisc/Thinkstock
オリンピックが忌避していたものは政治だけではない。もともとオリンピックは商業化に真っ向から反対していた。だが今日のオリンピックを見ればわかるように、企業から大金が流れこむイベントになったことは否定できない。
その大きな原因は1976年に行なわれた2つの大会にある。当初アメリカのデンバーで行なわれる予定だった冬季オリンピックは、オリンピック開催に反対する住民投票の結果をうけて、開催地を途中でオーストリアのインスブルックに変更することを余儀なくされた。加えてカナダのモントリオールで行なわれた夏季オリンピックも、予算見通しの甘さから15億ドルもの赤字を出した。こうした損失を補填するため、オリンピックの商業化が一気に加速したのである。
ブランテージ会長はかつてこう言った。「ビジネスはビジネス、スポーツはスポーツだ。2つを混ぜあわせることはできない」。しかしそれはただの理想論だった。1984年に行なわれたロサンゼルス大会以降、IOCはそれまでの比較的小規模なスポンサーを切り捨て、400万ドル、もしくはその金額に相当する物品を提供してくれる企業だけをスポンサーとした。さらにライセンス制度を設け、提携している企業以外を除き、オリンピック関係の商品を販売できないようにした。
こうして潤沢なスポンサー資金が、IOCのもとへ集まるようになった。かつてはテレビ放映権の販売による収益が98%を占めていたが、現在ではテレビ放映権の収益が全体の半分、スポンサー契約による収益が45%、入場券の販売による収益が5%となっている。
【必読ポイント!】 オリンピックの抱える問題と対策
なぜオリンピックの経費は高騰するのか
オリンピック史上もっとも成功した大会は1992年のバルセロナ大会だろう。バルセロナ市はオリンピック開催を契機に、市の中心部および臨海部の大部分を再開発できた。その経費は115億ドルにのぼったが、大半はインフラ開発とオリンピック施設に投入された。その結果、失業率は下がり、建設業は活気づき、住宅市場は上昇に転じた。バルセロナの人気観光地ランキングもうなぎのぼりになった。
とはいえバルセロナ大会に問題がなかったわけではない。バルセロナは招致活動中、経費を6億6700万ドルと見積もっていた。一般市民から支持を得るために経費をわざと低く計算したのだ。実際オックスフォード大学の研究によると、1960年から2012年までに開催されたオリンピックは、例外なく予算を超過したことがわかっている。経費の予算超過率は平均179%で、これはダム建設やインフラ開発などと比べても格段に高い。
またオリンピック開催に端を発した都市の再開発は、富裕層と貧民層の分離を推し進めた。オリンピック開催地付近の家賃が高騰し、ホームレスやワーキングプアのような社会的弱者は一掃された。いわゆるジェントリフィケーション(都市の住居地域を再開発して高級化すること)が起きたのだ。こうした現象はバルセロナ以降も多く見られるようになった。
経済効果という幻想
オリンピックの支持者たちは、その経済効果の高さを声高に主張する。だがすべてがバルセロナのようにうまくいったわけではない。オリンピックの経済効果についての調査研究のほとんどは、スポンサーを喜ばせるため、問題のある手法を用いているのだ。
オリンピックの経済効果に関して調査してきたアンドリュー・ジンバリストは、オリンピックの経済効果に対して否定的な結論を下している。その代表例となるのが、2004年に行なわれたアテネ大会だ。ギリシャ政府は当初、16億ドルを予算として見積もっていたが、最終的には160億ドルとなった。しかも大会期間中に1日あたり10万5000人の観光客が来るという試算があったが、実際には1万4000人だけだった。経済的には大失敗である。さらに悪いことに、大会後も荒廃したスタジアムの維持費に税金が吸い取られてしまっている。
ギリシャ大不況の一因は、オリンピックの開催だといっていい。オリンピックという催しは、財政的な観点からすると大失敗に終わる可能性が高いのだ。
今後に向けた提言

william87/iStock/Thinkstock
現実問題として、オリンピック開催に意欲的な都市は減るばかりである。かつてのIOCは、オリンピックが観光や雇用、経済成長を促進すると喧伝してきたが、もはやその言葉をそのまま信じる人は少ないだろう。オリンピックが真の改革を果たすためには、膨らむばかりの開発費用を抑えることが前提となる。
オリンピックは多額の経費を必要とするにもかかわらず、開催地の一般市民は十分な利益を得られていない。その要因としては、前述したような過剰に見積もられた経済効果もそうだが、オリンピックの開発計画と開催地の開発計画が結びついていないことが挙げられる。IOCは独立機関をつくり、招致活動で立案されている建設計画がその都市の長期的な開発戦略にかなっているかどうかを、客観的に評価させるべきだ。
また、本当に必要なもののために公金が使われるよう、計らう必要もある。いまのところインフラ構築に使われるはずの税金は、大会後の借金返済に使われてしまっている。公共交通機関の整備や、オリンピック選手村の公営住宅への転用など、開催地に住む人にとって有益になる施策を行なわなければならない。
その他にも、環境問題への配慮(現状の「持続可能性」の標榜はただの欺瞞でしかない)、民主的な組織の実現、前時代的なジェンダー意識の撤廃など、オリンピックが解消すべき問題は山積している。
それでも悪しき流れは変わりつつある。たとえば今日ほど、選手が社会的な行動を起こせる時代はなかった。たしかにIOCは相変わらず権力を手放さないし、一部の人間がオリンピックに便乗して私腹をこやしているのは事実だ。だが文化理論家のスチュアート・ホールが言うように、「覇権(ヘゲモニー)はけっして永遠ではない」。これからも歴史をしっかりと見つめなおし、悪しき部分を改めていくべきである。

この続きを見るには...
残り0/4458文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.02.09
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約