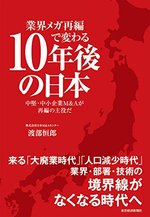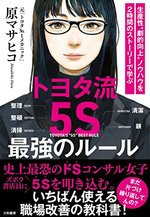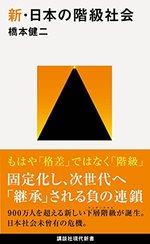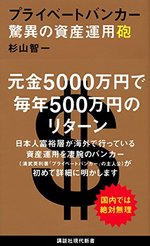生きている会社、死んでいる会社
「創造的新陳代謝」を生み出す10の基本原則


著者
遠藤 功(えんどう いさお )
ローランド・ベルガー日本法人会長。早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。経営コンサルタントとして、戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。ローランド・ベルガーワールドワイドのスーパーバイザリーボード(経営監査委員会)アジア初のメンバーに選出された。株式会社良品計画社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社社外取締役。日新製鋼株式会社社外取締役。株式会社マザーハウス社外取締役。株式会社ドリーム・アーツ社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。
『現場力を鍛える』『見える化』『現場論』(以上、東洋経済新報社)、『新幹線お掃除の天使たち』(あさ出版)など、ベストセラー著書多数。
ローランド・ベルガー日本法人会長。早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。経営コンサルタントとして、戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。ローランド・ベルガーワールドワイドのスーパーバイザリーボード(経営監査委員会)アジア初のメンバーに選出された。株式会社良品計画社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社社外取締役。日新製鋼株式会社社外取締役。株式会社マザーハウス社外取締役。株式会社ドリーム・アーツ社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。
『現場力を鍛える』『見える化』『現場論』(以上、東洋経済新報社)、『新幹線お掃除の天使たち』(あさ出版)など、ベストセラー著書多数。
本書の要点
- 要点1会社の目的は「独自価値を創造しつづけること」だ。ただし、会社が老化するとそれは難しくなる。老化を防ぐために、会社は新陳代謝しなければならない。
- 要点2会社には「経済体」「共同体」「生命体」の3つの側面がある。そのうち「生命体」こそ会社の核心だ。会社は、キラキラ輝き、逞しく、みなぎる力に溢れる生命体であるべきだ。
- 要点3生きている会社の条件は、「熱」(ほとばしる情熱)、「理」(徹底した理詰め)、「情」(社員の心の充足)の3つだ。その結果、「利」(利益)と「魂」(spirit)が生まれる。
要約
【必読ポイント!】 「生きている会社」とは何か
独自価値を創造しつづける
会社のあるべき姿を考えるためには、「そもそも会社は何のために存在するのか、その目的は何か」という問いからスタートしなければならない。経済学では、会社の目的は「利益の最大化」とされている。だがそれは目的ではなく大前提だ。利益の最大化は、会社が社会に必要とされていれば実現する。
社会に必要とされるために会社が為すべきは、「価値の創造」であり、これこそが会社の真の目的である。ただし、創り出す価値を判断し、選択するのは、顧客だ。つまり会社の目的とは、顧客が認める独自価値を創造することである。
ただし、苦労して独自価値を創造しても、競争の末、やがて陳腐化してしまう。挑戦によって独自価値を連続的に創造しつづけ、「絶え間なき創造」を実現しなければならないのだ。
新陳代謝する

Jon Feingersh/Blend Images/Thinkstock
創造しつづけることは難しい。なぜなら企業は老化するからである。「安住」と「傲慢」という老廃物が溜まることで、創造は困難なものになる。たとえばアマゾンのように、創造しつづける会社は、老化の怖さをよく知っている。だから創業当初の、初々しい野心や桁違いのエネルギーに溢れた1日目「デーワン」でありつづけようと努力しているのだ。
デーワンでありつづけ、創造を継続的に行うための鍵を握るのは、新陳代謝だ。創造と代謝はコインの裏表の関係である。新しいものを生み出すことだけが戦略ではないと認識しなければならない。
代謝戦略の対象は、事業、業務、組織、人だ。それぞれについて、「捨てる」「やめる」「入れ替える」こと。ただし、古いから、赤字だからといって必ずしもダメなわけではない。問題は、「凡庸さ」だ。それを放置せず、当たり前だと思っていることに対してメスを入れなければならない。
キラキラ輝く「生命体」である

Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Thinkstock
会社は「生き物」にたとえられるが、生き物としての会社は、「経済体」「共同体」「生命体」という3つの側面で形成されている。
「経済体」とは、価値を創造し、営利を追求するという会社の役割を遂行するために必要な側面だ。「共同体」とは、人々が同じ目的を共有し、「共働する場」であるという側面。「生命体」とは、そこで働く人々が仕事を通じてやりがいを感じ、人として成長し、活性化する場という側面である。
これまで会社は、経済体としての側面においてのみ論じられ、評価されてきた。確かに、そこには目に見える部分や測定可能な部分が多く、善悪の判断が容易という理由もあるだろう。ただし、経済体としての会社は、会社の一部分にすぎない。むしろ「生命体」こそ会社の核心である。会社は、キラキラ輝き、逞しく、みなぎる力に溢れる生命体でなければならないのだ。
生命体の正体は「気」である。会社にはそれぞれの「表情」があるものだが、会社としての活力、つまり気はそこにあらわれる。創造のために挑戦しつづけている会社は喜怒哀楽が豊かである一方、創造できない「死んでいる会社」は無表情なのだ。
生命体である会社の根源は、「人」だ。会社が活性化するかどうかは人にかかっているのだから、人事を人事部にまかせていてはいけない。経営者の最大の仕事は、「人」を元気にすることなのだ。
「生きている会社」の条件
「熱」を帯びている
生きている会社をつくるために必要なものは、じつはとてもシンプルだ。(1)「熱」(ほとばしる情熱)、(2)「理」(徹底した理詰め)、(3)「情」(社員たちの心の充足)の3つである。この3つの条件が整い、重なり合うことで会社は「生きている会社」になり、その結果「利」(利益)が生まれる。

この続きを見るには...
残り1813/3300文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.06.06
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約