論語と算盤
モラルと起業家精神

著者
渋沢 栄一 (しぶさわ えいいち)
1840(天保11)年~1931(昭和6)年。明治~昭和期の実業家、財界の指導者。武蔵国榛沢郡血洗島村(現埼玉県深谷市血洗島)に生まれ、幕末の青年期には討幕運動にも参加したが、のちに一橋家に仕え幕臣となる。1867(慶応3)年に渡欧して欧州の様々な知識を吸収し、明治維新の後に帰国して大蔵省に出仕。1873(明治6)年に大蔵省退官後は、第一国立銀行、王子製紙をはじめ多くの企業のほか、大学、病院、団体など600近くの様々な組織の立ち上げにかかわった。日本実業界に指導的役割を果たした経済近代化最大の功労者。
道添 進(みちぞえ すすむ)
1958年生。文筆家、コピーライター。国内デザイン会社を経て、1983年から1992年まで米国の広告制作会社に勤務。帰国後、各国企業のブランド活動をテーマにした取材執筆をはじめ、大学案内等の制作に携わる。企業広報誌『學思』(日本能率協会マネジメントセンター)では、全国各地の藩校や私塾および世界各国の教育事情を取材し、江戸時代から現代に通じる教育、また世界と日本における人材教育、人づくりのあり方や比較研究など幅広い分野で活動を続けている。著書に『ブランド・デザイン』『企画書は見た目で勝負』(美術出版社)などがある。
1840(天保11)年~1931(昭和6)年。明治~昭和期の実業家、財界の指導者。武蔵国榛沢郡血洗島村(現埼玉県深谷市血洗島)に生まれ、幕末の青年期には討幕運動にも参加したが、のちに一橋家に仕え幕臣となる。1867(慶応3)年に渡欧して欧州の様々な知識を吸収し、明治維新の後に帰国して大蔵省に出仕。1873(明治6)年に大蔵省退官後は、第一国立銀行、王子製紙をはじめ多くの企業のほか、大学、病院、団体など600近くの様々な組織の立ち上げにかかわった。日本実業界に指導的役割を果たした経済近代化最大の功労者。
道添 進(みちぞえ すすむ)
1958年生。文筆家、コピーライター。国内デザイン会社を経て、1983年から1992年まで米国の広告制作会社に勤務。帰国後、各国企業のブランド活動をテーマにした取材執筆をはじめ、大学案内等の制作に携わる。企業広報誌『學思』(日本能率協会マネジメントセンター)では、全国各地の藩校や私塾および世界各国の教育事情を取材し、江戸時代から現代に通じる教育、また世界と日本における人材教育、人づくりのあり方や比較研究など幅広い分野で活動を続けている。著書に『ブランド・デザイン』『企画書は見た目で勝負』(美術出版社)などがある。
本書の要点
- 要点1渋沢栄一は日本の近代資本主義の父とされる人物で、六百社近くの創業に関与している。彼の思想は日本企業の原点といえる。
- 要点2渋沢は明治政府の大蔵官僚だったが、豊かな国を築くため、官職を辞し、実業の世界へ飛び出した。彼が拠りどころとしたのが、論語だった。
- 要点3論語は金銭に批判的な思想だと考えられていた。しかし、渋沢はこうした旧来の論語の解釈を疑い、道徳と経済の両方が均衡することこそ重要だと説いた。
要約
名著『論語と算盤』とは
時代を超えて読み継がれる本
この本を初めて手にする読者は、何となく既視感を抱くかもしれない。というのも、近代資本主義の父といわれる渋沢栄一(以下、渋沢)が設立に関与した会社は、六百社近い。その流れをくむ会社が読者の職場かもしれない。だから、社訓などを通じて渋沢の思想に触れている可能性は高い。また、京セラ創業者の稲盛和夫氏など、影響力のある経済人が『論語と算盤』の影響を受け、その思想の伝道者となっている。
本書の大きな主張は二つある。一つは、道義を伴った利益を追求せよというものだ。そしてもう一つは、自分より他人を優先し、公益を第一にせよ、という主張である。要は、金儲けをすることと、世の中に尽くすことを両立しなさい、というわけである。
こうした考え方は、日本企業に広く浸透したものでもある。企業理念に「社会やお客様と共に」といった文言を盛り込んでいる企業は多い。こうした言葉の源流をたどると、『論語と算盤』に行き着く可能性が高い。
日本企業の強さは『論語と算盤』の延長線上にあったといえる。『論語と算盤』は、日本の経済人にとって、迷った時や先が見えない時に立ち返るべき原点なのだ。ガバナンスもコンプライアンスも突き詰めれば、『論語と算盤』で主張される「道義の伴った利益の追求」ということになる。こうした重要な教えが詰まった本書は、今後も長く読み継がれることだろう。
『論語と算盤』の誕生した時代
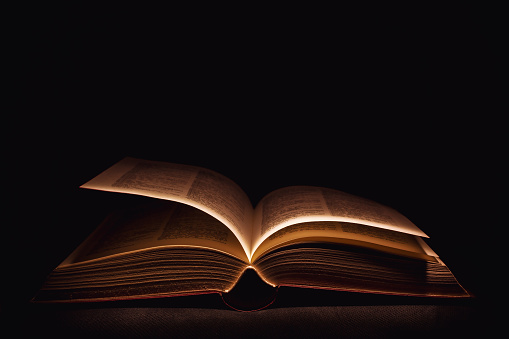
dejankrsmanovic/iStock/Thinkstock
渋沢は、事業の第一線を退いた明治30年代から、堰を切ったように自らの経営思想を語り始めた。『論語と算盤』は、彼の思索の集大成として、大正五(1916)年に出版された。この本の思想は、論語の精神で、人が本来持っているやる気や成長を促し、経済を持続的に活性化させようというものだ。
この本が書かれた大正の初めは、どんな時代だったのか。当時、社会全体がバブル期に突入し、とりわけ若い世代では立身出世、金儲けの風潮が蔓延していた。儒教の倫理観は、時代遅れだとして、隅に追いやられていた。
一方で大正期は、激動の明治が過ぎて、その余韻が収まろうとしていた時代でもあった。先進国の仲間入りを果たしたという安堵感もあっただろう。そして目標を喪失し、現状に甘んじるようになっていた。志ある名士たちは、こうした風潮を諫めようと声をあげた。その一つが『論語と算盤』だった。
渋沢は本だけでなく、あらゆる機会を捉えては、「道徳経済合一説」を唱えた。経済界の人々を前に話すときはもちろん、幼稚園で子供たちに語る時でさえ、最後はこの話になったという。もしも渋沢が今の時代に生きていたら、きっと同じことを語っただろう。本を書いた頃とよく似たこの時代をみて叱咤激励したにちがいない。
渋沢栄一の人生

Hiro_photo_H/iStock/Thinkstock
渋沢は、アヘン戦争の勃発した1840年に生まれ、満州事変の起こった1931年に没した。彼の生きた時代はまさに東アジアの激動の時代だった。
彼の一生は、大きく五つの時代に分けて捉えられる。郷里の村落で過ごした江戸後期の幼少時代、尊王攘夷運動に加わっていた幕末の青年時代、徳川家に随行し、渡仏して大政奉還に直面した時代、大蔵官僚時代、そして実業家時代だ。
幼少期には、理不尽な身分制の下、村人たちのために苦労する父母を見て、公共心や利他心を育んだ。渡仏中には、ヨーロッパの近代を目の当たりにし、産業や経済発展の重要性を痛感した。そして帰国後、渋沢は静岡に商法会所を設立する。これが日本最初の株式会社といわれている。

この続きを見るには...
残り2462/3900文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.06.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











