最強の思考法 「抽象化する力」の講義
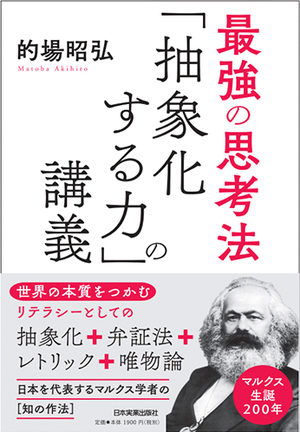
最強の思考法 「抽象化する力」の講義
著者
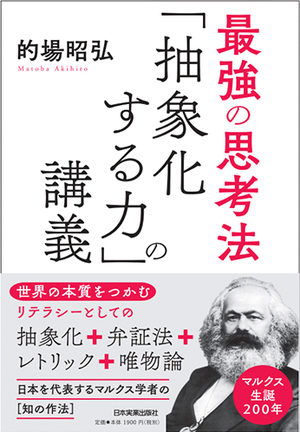
著者
的場 昭弘(まとば あきひろ)
1952年宮崎市生まれ。神奈川大学教授。同大国際センター所長。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士。専門は社会思想史、マルクス経済学。
著書に『超訳「資本論」』(全3巻、祥伝社新書)、『待ち望む力』(晶文社)、『一週間de資本論』(NHK出版)、『マルクスだったらこう考える』『ネオ共産主義論』(以上、光文社新書)、『マルクスに誘われて』(亜紀書房)、『マルクスを再読する』(角川ソフィア文庫)他。訳書にマルクス『新訳 初期マルクス』『新訳 共産党宣言』(以上、作品社)、ジャック・アタリ『世界精神マルクス』(藤原書店)他。
1952年宮崎市生まれ。神奈川大学教授。同大国際センター所長。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了、経済学博士。専門は社会思想史、マルクス経済学。
著書に『超訳「資本論」』(全3巻、祥伝社新書)、『待ち望む力』(晶文社)、『一週間de資本論』(NHK出版)、『マルクスだったらこう考える』『ネオ共産主義論』(以上、光文社新書)、『マルクスに誘われて』(亜紀書房)、『マルクスを再読する』(角川ソフィア文庫)他。訳書にマルクス『新訳 初期マルクス』『新訳 共産党宣言』(以上、作品社)、ジャック・アタリ『世界精神マルクス』(藤原書店)他。
本書の要点
- 要点1われわれには、日々起こる様々な出来事に関して、膨大な情報がもたらされる。しかしだからといって、必ずしも真理をつかんでいるというわけではない。世界の本質に迫るためには、個々の出来事の関係を知る「アナロジー」、バラバラのものを1本に括る「インゲニウム」といった手法が有効である。
- 要点2著者は、雑多な情報や物事をすっきりまとめ、現象の本質をつかむ力を抽象力と呼ぶ。
- 要点3日本人が西洋の学問をさっぱり理解できないことがあるのは、レトリック(修辞学)の中に染み渡っているキリスト教とギリシャ・ローマの古典を知らないからだ。
要約
世界の本質に迫るために
世界を完全につかむことはできない
世界では日々様々なことが起こっており、それらの出来事に関して、膨大な情報がもたらされる。しかし、多くの情報があるからといって、必ずしも真理をつかんでいるというわけではない。
膨大な情報があふれ出してくる現在において、自分で整理をしなければ、どこにどんな情報があるかわからなくなってしまう。だから、知識をどんどん受け入れるよりも、それを分類することのほうが重要だ。これは、図書館と同じだ。図書館には膨大な量の本があるが、十進分類法によって分類されているから、目当ての本を見つけることができる。
「アナロジー」で個々の出来事の関係を知る
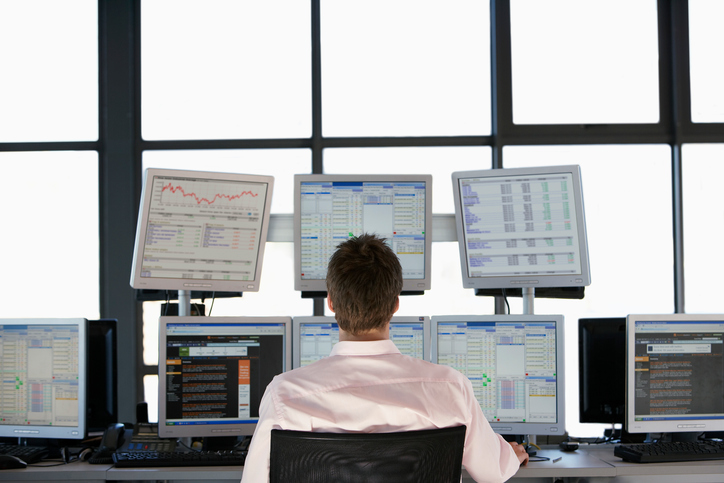
Mike Watson Images/moodboard/Thinkstock
バラバラに起こっている事象を一連の流れとしてつかむ技法が、アナロジーだ。1つひとつの事象を、1つの筋をたどって類推していく。アナロジーにおいて問題になるのは、真実よりも、「何が全体を動かしているのか」ということだ。
2015年の出来事を例に挙げよう。2015年の5月には、ユーロ問題が報道されていた。ギリシャの債務危機がユーロの破綻につながる可能性があるという問題だ。しかし8月には状況が一変し、難民問題へとシフトした。
まったく別物に見えるユーロ問題と難民問題には、実は深い関係がある。アナロジーを使い、ユーロ問題と難民問題の関係を考えてみよう。難民たちは、トルコからギリシャへと入り、マケドニアへと流れた。では、どうしてギリシャへ入れたのか?こうした問題を正確に証明することはできないが、出来事とそのタイミングを見てみると、その関係性を類推することが可能だ。類推の結果、EUからの借金を受け入れたギリシャが、何らかの形でトルコからの難民を受け入れざるをえなかったのではないかと考えられる。
「インゲニウム」で真実に迫る

scyther5/iStock/Thinkstock
この世界をつくったのが神であるならば、人間は世界の真実に至ることはできない。ただ想像するだけである。だからわれわれは、「真実らしいもの」をつかむように努力するべきだ。
「真実らしいもの」をつかむには、想像力をたくましくして、真摯に対象に迫っていく。こういった、バラバラのものを1本に括るための働きを「インゲニウム」という。フランスのバカロレア(国家学位の1つ)の試験では、インゲニウムを試す問題が出題される。たとえば、「人間が生きる目的とは何か? 金儲けという目的は人間の幸せとイコールであるかどうかについて記せ」などという問題だ。こうした問題に答えるためには、様々な知識を総動員して1本にまとめる力が求められる。たくさんある事象の中からいろいろな組み合わせを模索し、真実らしいものを導くのだ。
人間の思考は、「4つのイドラ」によって阻害されている。イドラとは、偶像や虚偽などといった、本当ではないものを頭の中で幻想していることをいう。1つ目は、「東京大学の先生が言っていたから正しい」などといった権威に惑わされる「劇場のイドラ」。2つ目は、「3億円強盗はこんな顔だった」という目撃発言に惑わされるといった人間の感覚の限界から生じる「種族のイドラ」。3つ目は、「あなた以外、みんなこう言っているよ」など、言語が思考にもたらす偏見に囚われる「市場のイドラ」。最後に、それぞれの人間が置かれた環境や習慣の拘束によって、人間は絶対に真理そのものを見ることはできないという「洞窟のイドラ」である。
【必読ポイント!】 「抽象力」で世界史を読み解く
本質をつかむ「抽象力」
この世界を感覚的につかもうとしても、それは不可能だ。なぜなら、われわれの感覚が不十分だからだ。本質をつかむためには、それを一旦、抽象化することだ。この抽象化の方法の1つが、マルクスのいわゆる「唯物史観(史的唯物論)」である。
著者は、雑多な情報や物事をすっきりまとめ、現象の本質をつかむ力のことを「抽象力」と呼ぶ。
世界のすべての出来事が結びついている
マルクスによると、世界史とは、個々の事象が別個に起こっていることを説明するものではない。ある1つの動きが全体を包括し、今まで各国史だったものが1つの世界に包摂されていく過程であるという。つまり、世界が1つの流れで動いているから、世界のすべての出来事が結びついているのだ。
さらに、世界史を引っ張っているものは、「資本」の力だとマルクスは言う。世界のどの国も、利潤追求の中で、遠い他国のことを無視できなくなった。世界史とは、資本主義が生み出した概念だといえる。
多くの大学の入試問題は、「下の中から『共産党宣言』の著者名を答えなさい」などといったものだ。しかし、世界史における「いい問題」とは、「ルネサンスに与えた中東の影響について800字~1000字で記せ」といった問題だ。これは、中東やルネサンスのことを知識として覚えているだけでは解けないだろう。これらとつながっている、十字軍やモンゴル、地中海貿易などについても知らなければならない。本来、世界史の問題とは、こうあるべきだ。
ペリーはなぜやって来たのか?

Mima88/iStock/Thinkstock
「なぜ日本が開国したのか」を考えてみよう。ペリーがやって来たからではない。19世紀のロシア封じ込めがその理由である。クリミア戦争で、イギリスとフランスは、ロシアに対して封じ込めを実施した。アジアでは、カナダとアメリカがその封じ込めを支援した。それがペリーの来航という形をとり、日本の開国がなされたのだ。
世界の様々な出来事は、個々別個に起こっているように見える。しかしどんな出来事にも、その背後に大きな一つの流れがあり、個々の出来事は何らかの形でつながっているのだ。
「レトリック」で古典を読み解く
日本人が西洋の学問を理解できない理由
西洋の学問は、キリスト教の知識がないとさっぱり理解できないことがある。なぜなら、レトリック(修辞学)の中にキリスト教とギリシャ・ローマの古典が染み渡っているからだ。実際、『資本論』第1巻においても、おびただしい量のキリスト教や古典、文学などからの引用がある。これは、けっして知識をひけらかそうとしているわけではない。19世紀の知識人を説得するには、その知識人の思考の形に訴えるしかなかったからだ。
だから日本人にとっては、西洋の学問を表面的に翻訳しただけでは、さっぱり理解できない。たとえば、社会主義やユートピアといった言葉において考えるとしよう。日本の伝統的な共同体にかこつけて考えたり、夢と希望は社会主義にあると考えたりして、なんとか意味を理解しようとするだろう。しかし、キリスト教的な千年王国論やエクソダス(大逃亡)などといったものを知らなければ、これらは表面的にしか理解できない。
価値コード体系はどんどん変化していく
私たちが本を読むときには、ある価値コード体系に従って読んでいる。もし、この価値コード体系が崩壊したら、本はまったく読めなくなってしまう。本が読めるということは、その本と価値コードを共有することだ。もし、価値コードを共有できなければ、その本は不愉快そのものとなる。実際に、1960年代までの文学少年・青年が読んでいた本は、今の多くの若者には読めないはずだ。なぜなら、今の若者の価値コード体系からすると古すぎるからだ。価値コード体系は、時代によってどんどん変化していくものである。
読書は、時代による価値コード体系の変化を明確に反映する。印刷された本は、時代を経ても変わることはない。しかし、その本の読み方は、時代を経て変わっていく。なぜなら、読む側の状況が変わっていくからだ。同じ本であっても、その本の読まれ方は、読む側の状況によってどんどん変わっていくといえる。
レトリックで『資本論』を裏読みする
『資本論』が書かれた時代と現在とでは、価値コード体系がまったく変わってしまっている。だから、『資本論』で用いられているレトリックは、既に理解できないものとなっている。加えて、日本人はキリスト教文化に親しんでいないから、まるで読めないといってよい。
実は『資本論』の冒頭の「商品」の部分は、キリスト教文化がわかれば理解しやすい。「商品」の問題を宗教問題として裏読みするのだ。中世においては、商品を、質的な神々しさで評価していた。しかし資本主義時代において、商品は、労働時間の投下物としての量的なものへと変化した。質から量へと、評価軸が変化している。この本質は、カトリックではなく、プロテスタントの中にある。なぜなら、プロテスタントが商品というモノに対する崇拝を捨て、モノ自体にこだわったからだ。モノは労働時間の量で測られるようになり、神々しさを失ったということだ。このように、普通に読むよりもレトリックで読んだほうが、著者の意図がつかみやすくなるといえる。
『資本論』という書物そのものは何年経っても変化しないが、読者がどう読むかにより、『資本論』はどんどん変化していく。つまり、時代が変わり、価値コード体系が変化する中で、新しい読み方が生まれる。
マルクスはレトリックの天才だった

cherrybeans/iStock/Thinkstock
マルクスの本は、風刺に満ちている。
彼の書物に、『哲学の貧困』がある。タイトルを見た人は、哲学を批判した本だと予想するのではないだろうか。実際は、そうではない。マルクスの宿敵であるプルードンが出版した『貧困の哲学』を批判するためにつけたタイトルなのだ。つまり、「プルードンの本は哲学が貧困だ」と揶揄している。
『聖家族(神聖家族)』という著書もある。一見、キリスト教をテーマにした本だと思うかもしれない。しかし実は、哲学を批判した本なのだ。本の中で批判されている人たちの哲学は、哲学というよりも宗教的だ、と風刺しているタイトルだ。
その他にも、ギリシャ神話を知らなければわからない表現を使ったり、レトリックを駆使して検閲に引っかからないようにメッセージを伝えたりしている書物もある。現在の日本人の読者にとっては、頭をひねらざるをえないものかもしれない。

この続きを見るには...
残り0/4036文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.06.28
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











