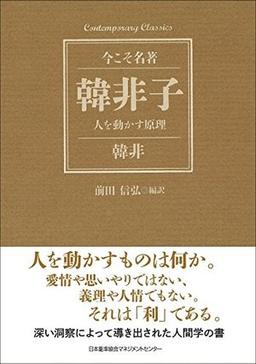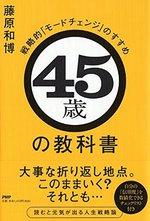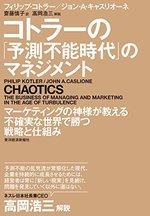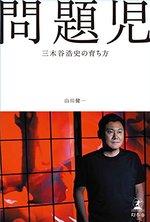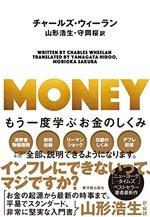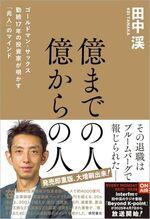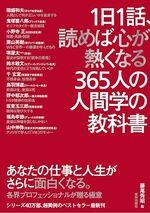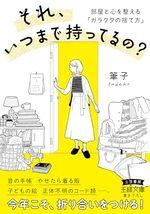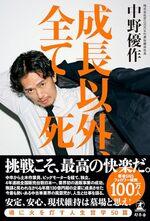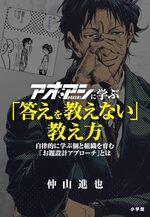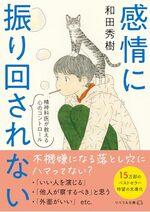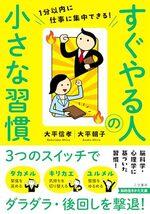韓非と『韓非子』
『韓非子』とは
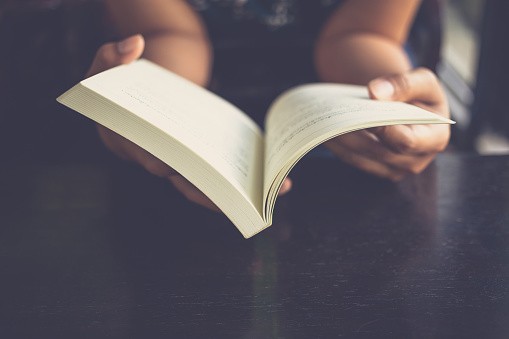
『韓非子』は、中国、戦国時代の思想家である韓非の著作で、中国古代の法家の思想を伝える代表的な書物だ。法家とは、諸子百家の中でも厳格な法治を主張した学派である。『韓非子』は法家思想を知るための必読の書といわれている。
さらに『韓非子』は、広く人間学の書として読むこともできる。人間存在についての深い洞察があり、冷酷ともいえる冷めた目で人間の現実を描き出しているからだ。
人を動かすものは愛情や思いやり、義理や人情ではなく「利」であると韓非は述べる。人間とは自分の利益を追求する存在であり、愛情などによって結びついているわけではない。また、人を信用してはならないと論じてもいる。ただし、だからといって、韓非は人間を否定しているわけではない。人間というものを冷静に見つめ、あるがままの現実を捉えている。こうした思想が『韓非子』全篇に貫かれている。
韓非の人生
韓非の人となりについては詳しい記録が残っておらず、不明な部分も多い。唯一、韓非に関するまとまった伝記として残っているのが『史記』(老子・韓非列伝)である。
『史記』によると、韓非は韓の国の公子として生まれ、紀元前233年頃に亡くなったとされている。韓非は母親の身分が低い「諸公子」であり、かれの地位は決して恵まれていなかった。またかれは吃音であり、自身の考えを直接説くことは不得手であったが、その一方で著作にすぐれていたと伝えられている。
韓非は若いころ、儒家の荀子の弟子になり、やがて離れた。諸学派の説を取り入れ、また批判しつつ独自の学問を形成していった。
韓非が生まれた韓という国は、戦国七雄のなかでももっとも狭小な国であり、強大な秦の前に、その国力は日に日に衰えていった。韓非は祖国の国情が衰えていくことを憂い、たびたび国王に意見を献じたが、それが取り上げられることはないままだった。韓非はその悲しみをこめ、『韓非子』を書き上げた。
『韓非子』は、のちに始皇帝となる秦の王の目にとまる。その名文が買われ、秦に招かれた韓非だったが、敵国の公子という身分を責められ、自殺に追い込まれてしまった。
韓非の生きた時代
韓非が生きた時代の中国はまさに戦乱の世であり、周王朝の衰えからいくつもの国が生まれ、実力者の治める国だけが生き残る時代であった。このような乱世においては、富国強兵に役立つ有能な人材が求められた。儒家の開祖である孔子は、これらの人材の育成にあたった人物である。
その後、孔子の教えとは潮流が異なる墨家が誕生し、儒家と墨家という二大学派の中から、またはそれらに対する批判からさまざまな思想家が学派を形成していった。このときに形成された「儒家」「墨家」「道家」「法家」などの学派を「諸子百家」と呼ぶ。かれらの議論の中心は、古い秩序の崩壊と弱肉強食がはびこる風潮のなかで、どうすれば目前の秩序と安寧をとり戻せるかという問題の解決にあった。
【必読ポイント!】現代語訳『韓非子』
意見を述べることの難しさ

君主に進言したり、意見を述べたりすることは難しい。その難しさとは、述べる知識を持つことにあるのではない。また、意向を伝える弁舌を持つことや、自分の思いどおりにいい切ってしまうことにあるのでもない。人に意見を言うことの難しさとは、話す相手の心のうちを読みとって、自分の意見をそこにあわせることにある。
たとえば韓非は「説難篇」の冒頭で、名誉を求めるものに利益の話をしては相手にされず、利益を求めるものに名誉の話をしても採用されないという例を出している。相手の内心にはどのような思惑があるのか、その機微を探ることが重要だという教えだ。
刑罰と恩賞
明君が臣下を管理するためには、2つの柄(器物の取っ手、物事の要点)を使わなければならない。2つの柄とは、刑(刑罰)と徳(恩賞)である。刑とは罰を加えることであり、徳とは賞をあたえることだ。君主が二つの柄を握り、刑と徳を行えば、臣下たちは罪を犯さず、善に励む。もし、君主が賞罰を臣下に任せてしまえば、