Beyond the Label(ビヨンド・ザ・ラベル)
「こうあるべき」の先にある、自分流リーダーシップと成功の形
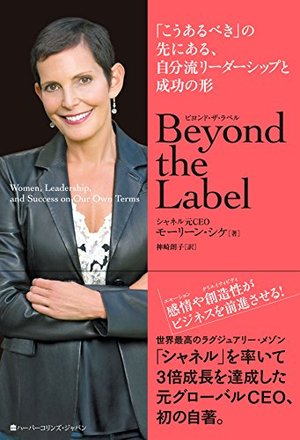
著者
モーリーン・シケ (Maureen Chiquet)
イェール大学にて文学を専攻。卒業後に渡仏し、1985年よりロレアル・パリにてマーケティングの職に就く。アメリカへ帰国後はGAPに入社し、マーチャンダイザー(商品企画)の道に進んだ。系列ブランドのオールドネイビーの立ち上げにナンバー2として携わり伝説的な大成功をもたらしたのち、同じく系列ブランドのバナナ・リパブリックの社長に就任。2003年にシャネルに移り、COO兼アメリカ支社長を経て、同社初のグローバルCEOとなる。2016年に退任し、現在はリーダーシップに関する講演や執筆活動を行う傍ら、イェール大学理事と特別研究員、The New York Academy of Art理事、カナダグースとラグ&ボーン社外取締役を務める。
イェール大学にて文学を専攻。卒業後に渡仏し、1985年よりロレアル・パリにてマーケティングの職に就く。アメリカへ帰国後はGAPに入社し、マーチャンダイザー(商品企画)の道に進んだ。系列ブランドのオールドネイビーの立ち上げにナンバー2として携わり伝説的な大成功をもたらしたのち、同じく系列ブランドのバナナ・リパブリックの社長に就任。2003年にシャネルに移り、COO兼アメリカ支社長を経て、同社初のグローバルCEOとなる。2016年に退任し、現在はリーダーシップに関する講演や執筆活動を行う傍ら、イェール大学理事と特別研究員、The New York Academy of Art理事、カナダグースとラグ&ボーン社外取締役を務める。
本書の要点
- 要点1映画でも演劇でも、観る人によって解釈は異なる。組織においても同様で、リーダーの発言はメンバー1人ひとりによって受け取り方が違うものだ。
- 要点2最初からキャリアパスが明確な人は少ない。自分がしたくないことを認識し、自分の望みに向かって踏み出すことが大切だ。
- 要点3早いうちから自分のコアバリューについて考えておこう。そうすれば、転職のような判断に迷う問題に直面しても決断できる。
- 要点4どんなに小さな仕事にも成果を上げるチャンスはある。チャンスをつかんで高みを目指そう。
要約
原点としてのフランス
五感の目覚め

mactrunk/gettyimages
アメリカで育った著者がフランスに魅せられたのは、16歳の夏、プロヴァンス地方で1カ月間のホームステイを経験したことがきっかけだった。重厚な建物に降り注ぐ陽射しや一面のラベンダー畑、野の花を生けた花瓶などからフランス人の優れた美的感覚を感じ、大いに刺激を受けた。
中でも著者の五感を刺激し、その後のキャリアを左右したとも言えるのは、名産のシェーブルチーズだったという。それは、著者がホームステイ先に到着したその日に、冷たいロゼワインとともにふるまわれた。
まるで儀式のように、彼らはゆっくり、じっくりとシェーブルチーズを味わっていく。その儀式から、フランス人の美に対するアプローチが見て取れるようだった。
フランスでの暮らしは、著者に新鮮な刺激を与えてくれた。ありとあらゆる感覚が目覚め、生きていることを実感できた1カ月だった。
映画・演劇とビジネス
すっかりフランスに魅了され、イェール大学ではフランスのヌーヴェルヴァーグ映画入門の授業に登録した。ヌーヴェルヴァーグ映画には、美しい映像と味わい深いストーリー、フランス語と、大好きなものがすべて詰まっているように思えたのだ。
著者の専攻である文学の視点から映画を見てみると、映画も演劇もテクストの形式であると論じることができると気づいた。映画では、音や映像、音楽、照明などが互いに作用し合い、観客の感情に訴えかけ、解釈を求める。それは、イメージや言葉の相互作用によって読者の感情を呼び起こす文学作品にも共通することだ。そして映画であれ演劇であれ、人によって解釈はさまざまに異なる。そこに面白さを感じたのだった。
ヌーヴェルヴァーグ映画では、カメラの存在がつねに意識される。観客に臨場感を与えるべく、カメラが人間のようにまばたきをしたり、場面に合わせて揺れたりといった工夫が凝らされているのだ。こうしたことから、著者は“カメラの眼”をもって身の周りの物事や人びとを観察することを学んだ。ロレアルで印刷物のデザインやサイネージの色を選ぶときには、徹底的に顧客の目になって考えることができたし、顧客の感じ方にはいくつもの可能性があることを理解できていた。これはビジネススクール出身のほかのマーケターたちが持たない視点だった。
ロラン・バルトが教えてくれたこと
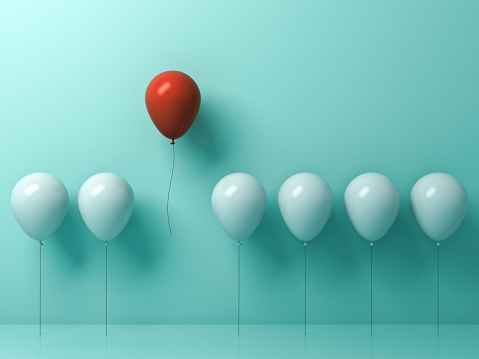
masterzphotois/gettyimages
フランスの哲学者・批評家、ロラン・バルトが書いたエッセイに『作者の死』というものがある。読者が作者の書いたものを独自に解釈することによって、読者は作者を“殺す”というのがその主張だ。
著者はこの主張をリーダーシップに当てはめて考えた。リーダーがメンバーにビジョンやミッション、戦略をこんこんと説いたとき、リーダーが本来意図したものは“死んで”しまう。そしてリーダーとしての影響範囲が拡大すればするほど、この“死”は不可避となる。それでもリーダーは強い目的を持ち、それを堂々と表明しなければならないのだ。
文学や歴史などの人文系の学問は軽視されがちだが、

この続きを見るには...
残り2985/4218文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.11.04
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











