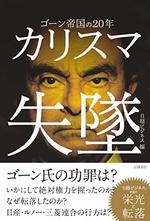社会学の誕生
社会学の固有の問題
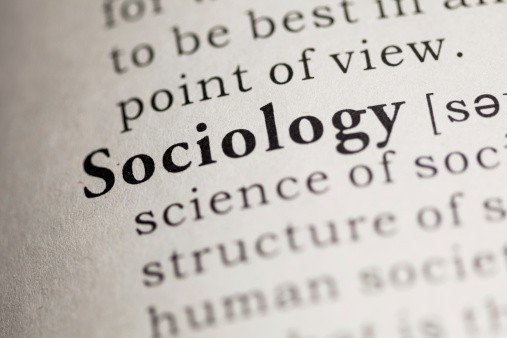
社会学の歴史はそれ自体が社会学となる。なぜなら社会学自身が社会現象だからだ。自然科学系の学問は、過去の説を捨て、新しい説へ向けて「直進するタイプ」の学問である。一方、何度も同じ問題を考える「反復するタイプ」の学問がある。その一例である哲学では、プラトンが考えた問題を現在の私たちも考えることがあるように、過去の哲学者と同じ問題に向き合っている。つまり、哲学史をやることがそのまま哲学となる。
社会学の場合は両方の側面がある。社会学は近代に生まれた比較的新しい学問だが、広い意味での近代社会を生きる私たちも、社会学が生まれた時と基本的には同じロジックで動く社会を生きている。よって、社会学史を学ぶことは、今日においても非常に有意義なのである。
社会学を理解するためには、「現に起きている社会現象に対して、ある種の不確実性の感覚をもつ」ことが重要となる。なぜ、ある社会秩序が生成したり、壊れたりするのだろうか。つまり「社会秩序はいかにして可能か」。これが社会学固有の主題となる。
「社会学」の創始者
「社会秩序はいかにして可能か」。この問いに関しては、アリストテレスの著作にもその萌芽が見られる。だが、自らが生きていた都市国家を自明のものと見なしていた点で、当時はまだ社会学は存在していなかったといえる。一方、トマス・ホッブズの社会契約の考え方は、社会秩序の問題への一つの答えとなっている。
一般に社会学の教科書では、社会学の創始者は「社会学」という言葉を発明した、オーギュスト・コントとされている。コントは著書『実証哲学講義』において、数学を頂点として社会学を一番下の土台とする、学問の地図を作った。また、ハーバート・スペンサーは、社会進化論を取り入れた著作『総合哲学体系』の一部として、社会学を論じた。
コントとスペンサーは、ホッブズのようなそれ以前の社会哲学者と比べると、時間や歴史を思想の根幹としているという点で、大きな違いが存在する。
社会学者としてのマルクス
学者、著述家、革命家としてだけでなく、社会学史上、思考・実践の両面で最も影響を与えてきた人物といえば、カール・マルクスである。
「生産様式」を土台、「イデオロギー」を上部構造に置く図式や、「疎外論」と「物象化論」、「価値形態論」など、マルクスには重要な論点が多数ある。だが、著作『資本論』において、資本主義を一種の宗教と捉えたことは、彼の最も重要な洞察といえる。『資本論』にはいたるところに神学的な隠喩が使われているが、マルクスは、貨幣を貯め込む守銭奴に禁欲さを見出し、宗教に通じるものを見た。これをさらにシステマティックに考え抜いたのが、マックス・ヴェーバーだ。
【必読ポイント!】 社会学の絶頂期
「社会」の発見

19世紀から20世紀への転換期に、社会学は絶頂期を迎えた。この時期のビッグスリーとして、エミール・デュルケーム、ゲオルク・ジンメル、マックス・ヴェーバーが挙げられる。
だが、忘れてはならないのが、ジグムント・フロイトだ。彼の提唱した「無意識」や「エディプス・コンプレックス」などの説は、社会学に大きな影響を与えている。これを考えれば、フロイトも社会学史の中に加えなければならない。
無意識とは、私の思考なのに私の外で生起しているように感じられる現象である。その意味で、無意識の発見は「社会の発見」に限りなく近い。
社会の発見という観点に最もふさわしい社会学者は、デュルケームである。デュルケームは『自殺論』や『社会分業論』などの著作をのこした。その中では、社会や集団がもっている性質から現象を説明する「方法論的集合主義」という手法を用いた。また、デュルケームは社会学の方法論を確立させるべく、「社会」という概念を定式化し、学問的な分析に使用できるものにした人物である。