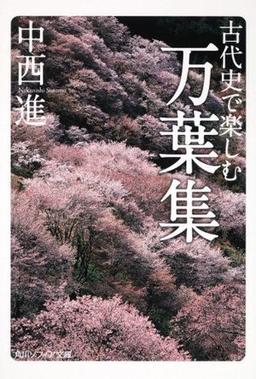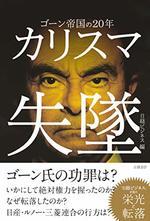【必読ポイント!】 万葉古代の歌うた
万葉集と古代の歌
万葉集20巻には4500あまりもの歌が収められているが、それらは第1巻のはじめから年代順に並べられているわけではない。すべての歌を年代順に考える場合は、いろいろな巻から歌を持ってきて並べかえなければならないのだ。
こうして並べかえていくと、まず出てくるのは5世紀初頭の人物である磐姫皇后(いわのひめのおおきさき)などの歌だ。本書では、7世紀半ば、645年の大化の改新以前の歌を万葉の古代の歌うたと名づける。
磐姫の頃の歌は口頭伝承であったので、彼女のものとして万葉集に収録されている作品が、彼女がよんだ歌の原形そのものかどうかはわからない。それどころか、磐姫が本当にこのような歌を作ったかどうかさえ疑わしいほどだ。
古代の人々を垣間見せてくれる磐姫

古代の歌うたが生み出された時代は、当時の人々にとってどのような時代だったのだろうか。仁徳天皇の皇后磐姫の歌は、それを垣間見せてくれる。
磐姫は、万葉集に収録されている「葛城(かずらき)の 襲津彦(そつひこ)真弓 荒木にも 憑(たの)めや君が わが名告(の)りけむ」という歌の中に登場する。「わたしを頼りになる者だと思ってわたしの名を人に言ったのだろうか」という、自分たちの恋を公にしてしまった男に対する女の歌だ。女への頼りがいを、磐姫の父である「葛城襲津彦の持つ弓のような強力な木の弓」にたとえている。襲津彦が庶民にまで名の知られた強力な武将だったことがうかがわれる。
天皇家が王権を樹立できたのは、葛城の力と結託したからだとされている。磐姫が仁徳に嫁いだのも政略結婚だった。
だから磐姫には多くのライバルがいた。磐姫の嫉妬にたえかねて逃げていった女がいたとされるほどだ。磐姫の留守中に別の女が宮中に召されたことがわかると、磐姫は嫉妬に狂い、神事につかうために取ってあった柏の葉を捨ててしまったという。
万葉集には、磐姫が天皇を思ってよんだ歌が4首のせられている。そのうちの一つは、「秋の田の 穂の上(へ)に霧(き)らふ 朝霞 いづへの方(かた)に わが恋ひやまむ(秋の穂の上にわだかまって行き場のない霞のように、わが恋の苦しさはどちらの方向にも晴れていかない)」という、恋の苦しみを嘆く歌となっている。ほかにも、伝説上の悲恋の主人公と自分を同一視するような歌など、万葉びとが磐姫のいちずな愛を見つめていたことがうかがい知れる。
大化の改新から遷都までの歌
大化の改新が生んだ古代史の文学

蘇我(そが)氏が終焉を迎え、当時の天皇であった皇極が退位すると、その地位をつぐものとして中大兄(なかのおおえ)があげられたが、彼は皇太子の地位を望んだ。皇極の弟である軽皇子(かるのみこ)が即位して孝徳(こうとく)天皇となり、皇后には中大兄の妹である間人(はしひと)皇女が立てられた。こうして陣容を整えた新政府は、古代史に稀にみる改新を断行していく。