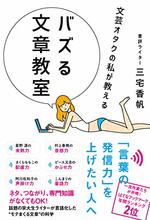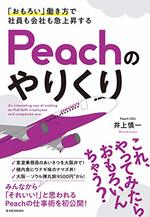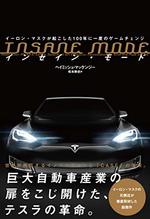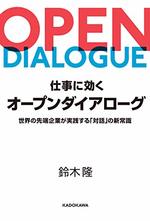NETFLIX コンテンツ帝国の野望
GAFAを超える最強IT企業
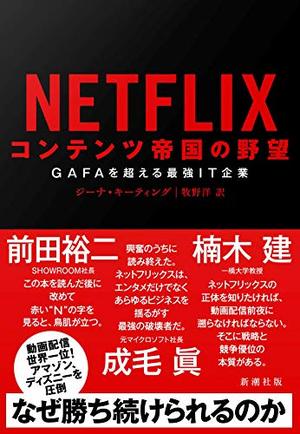
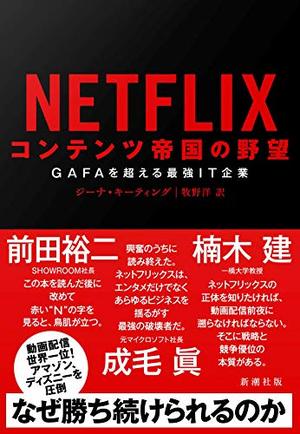
著者
ジーナ・キーティング (Gina Keating)
フリーランスの経済ジャーナリスト。米UPI通信、英ロイター通信に記者として在籍し、10年以上にわたってメディア業界、法曹界、政界を担当。独立後は娯楽誌バラエティ、富裕層向けライフスタイル誌ドゥジュール、米国南部向けライフスタイル誌サザンリビング、ビジネス誌フォーブスなどへ寄稿している。本書は処女作に当たる。
フリーランスの経済ジャーナリスト。米UPI通信、英ロイター通信に記者として在籍し、10年以上にわたってメディア業界、法曹界、政界を担当。独立後は娯楽誌バラエティ、富裕層向けライフスタイル誌ドゥジュール、米国南部向けライフスタイル誌サザンリビング、ビジネス誌フォーブスなどへ寄稿している。本書は処女作に当たる。
本書の要点
- 要点1ネットフリックスはビデオレンタルという業界で、長期的な顧客価値を最大化するための独自のアルゴリズムを常に進化させていった。そして複雑な物流システムを築き上げると同時に、コスト最小化の方法を探りつづけることで、参入障壁の高いビジネスモデルを構築した。
- 要点2ブロックバスターは店舗派とオンライン派で分裂していたものの、オンライン派をスピンアウトさせることで対抗した。そして価格競争やサービス競争でしのぎを削り、ネットフリックスをぎりぎりまで追い詰めたものの、CEOの交代をきっかけにその勢いを失った。
要約
スタートアップ
郵便DVDレンタル

PhotoMelon/gettyimages
1998年4月、ネットフリックスのウェブサイトが立ち上がった。サイト上で映画のタイトルを見つけ注文すると、利用者のもとへ郵送でレンタルDVDが送られてくるという仕組みである。価格は店頭でレンタルする場合と同等だ。
DVDレコーダーは前年97年の3月に登場したばかりであり、レンタルビデオ店のビデオはまだVHS仕様だった。当時市場に出ていたDVDのタイトルは500本ほどで、しかも多くが旧作の映画である。新作映画のDVD化に手をつけていたのはワーナーだけだった。
だからターゲットはきわめて限られていた。DVDプレーヤーを持っていて、ネットショッピングを楽しんでいるような「おたく」である。ネットフリックスはマーケティングの最初の一歩として、オンラインのコミュニティーで影響力を持つインフルエンサーに働きかけることにした。
一方でマス向けのマーケティングとして、DVDプレーヤーのメーカーとの提携も試みた。具体的にはDVDプレーヤーの箱の中に、無料クーポン券を入れたのである。消費者は見るDVD映画がないという理由でDVDプレーヤーを買わない。レコード店は誰もDVDプレーヤーを持っていないという理由でDVD映画を置かない。ならばDVDプレーヤーの箱の中にネットフリックスのクーポンを入れれば、メーカーは消費者に対して「無料で映像ライブラリにアクセスできます」とアピールできるはずである。しかしこの無料クーポンは諸刃の剣であり、ネットフリックスはしばらく赤字を垂れ流すことになる。
延滞料金なし
初期のネットフリックスを特徴づけたのは、顧客に映画を推薦するレコメンドエンジン「シネマッチ」である。アルゴリズムで動くAI(人工知能)が、顧客一人ひとりに合わせて映画を推薦するのだ。またウェブサイトのインターフェイスは、顧客の映画の好みに合わせて、センスのある店員がアドバイスしている、そんな雰囲気を目指した。
配送も、徐々に洗練されたものに改良していった。そのかいあって、翌日配達が可能な地域では、「翌日配達のネットフリックス」という口コミがどんどん広がった。新規顧客獲得に絶大な効果があることがわかると、郵便局の配達エリアに合わせて物流センターを設け、翌日配達のエリアを広げることに注力していく。
2000年には、毎月定額で一度に4本まで好きな映画をレンタルできる「サブスクリプション型プラン」を導入し、多くの顧客を呼び込んだ。返却したら次に映画をリクエストできるが、顧客はいつ返却してもいい。つまり延滞料金を払わなくていいのである。「延滞料金なし」は、店舗型ビデオレンタルに対する大きな差別点になった。
【必読ポイント!】 ブロックバスターとの戦い
カニバリゼーション

BestForLater91/gettyimages
2002年にネットフリックスはIPO(新規株式公開)を果たし、03年3月には契約者が100万人を突破した。波に乗ったのである。その様子をビデオレンタル業界の巨人「ブロックバスター」は複雑な思いで見ていた。ブロックバスター独自の消費者調査では、ネットによる郵送DVDレンタルの関心は引き続き低かったし、ウォール街の見方も同じようなものだったからだ。
ブロックバスターは当初、実店舗の売り上げを侵食する「カニバリゼーション(共食い)」をおそれ、郵便DVDレンタルの参入を見送っていた。だが理由はそれだけではない。じつのところブロックバスターはDVDを飛び越し、その先を見ていた。光ファイバー網の構築によって、アメリカの一般家庭に映画を配信するビデオオンデマンド(VOD)の実現を真剣に検討していたのである。
しかしブロードバンドの構築で提携していたエネルギー大手「エンロン」が粉飾決算で倒産するなどの不運もあり、サービスをスタートさせることはできなかった。そこで渋々ながら巨大なVHS在庫を処分し、DVD化を進めた。これには多大なコストが発生することになった。
巨人は覚醒した
2003年、ブロックバスター社内は、既存店舗網の体質強化が最重要だとする「店舗派」と、ネットによるサービスを立ち上げるべきだとする「オンライン派」に二分されていた。経営陣は最終的に、オンライン派を本社からスピンアウトさせることを決断した。
そしてその年の暮れ、サイトの開発が始まった。だが実店舗から切り離され、店舗よりも目立つマーケティングや、顧客の店舗への不満に言及するようなアピールも禁じられた。しかもエンジニアはすぐに、ネットフリックスがサイトの洗練度やレコメンドエンジンにおいてはるかに先にいっていることに気づいた。表面を似せることはできても、自分たちに与えられた時間と予算ではとても追い付けない。
それでも04年8月、「ブロックバスター・オンライン」はローンチした。行き着いたのはネットフリックスとそっくりの郵便DVDレンタルである。ネットフリックスより2ドル安い月額料金が売りだった。
シンクタンク

Art24hr/gettyimages
こうしたブロックバスターの動きに対し、ネットフリックスは冷静だった。自分たちのこれまでの経験から、バックヤードもふくめたシステム全体を構築するのは、そう簡単なことではないことを知っていたからである。
表から見ただけでは、ネットフリックスは巨大なビデオレンタル店にすぎない。顧客から月額固定の料金を徴収し、DVDを貸し出しているだけだからだ。しかしバックヤードを見ると、まったく違う姿が浮かび上がる。
長期的な顧客価値を最大化するための独自のアルゴリズムを常に進化させ、複雑な物流システムを築き上げ、同時にコスト最小化の方法を探りつづける。この見えにくい部分こそがネットフリックスの競争力の源泉なのであり、これによって高い参入障壁を築いていたのだ。あるアナリストはネットフリックスを評して、「ビデオレンタル店というよりもシンクタンクである」と語っている。
マーケティング費用
ネットフリックスが冷静だったもうひとつの理由は、ブロックバスターが財務的にかなり脆弱だと知っていたからである。格安のレンタル料金を維持するために、長期にわたって資金を使い続けるわけにはいかないと読んでいた。
サブスクリプション型のビジネスは、契約者ベースが十分に大きくなり、固定費を賄えるようになるまでは利益を出すのが難しい。一般的に新規契約から最初の9カ月間は、解約防止に向けたマーケティングで費用が膨らむ。一方で9カ月間以上経過すれば、コスト上昇に歯止めが掛かる。ブロックバスターは最初の9カ月間については我慢して出資し続けなければ、何の恩恵にもあずかれないだろう――これがネットフリックス社内の分析だった。
それにネットによるサービスは、どんなときでも最低限のマーケティングを行わなければならない。一定数の解約が必ず発生するため、それを新規契約で埋め合わせる必要があるためだ。これも経験で学んだことだった。
実際に2005年夏、親会社の資金繰りが悪化し一時マーケティングを休止したことで、ブロックバスター・オンラインの成長が止まった。顧客は100万人で横ばいになった。ネットフリックスの予測が当たったのである。
ハイブリッドモデル
2006年11月、ブロックバスターは「トータルアクセス」という新しいプランをローンチした。これはオンラインと実店舗をつないだハイブリッドモデルであり、実店舗をもたないネットフリックスにはぜったいに実現できないサービスだった。
じつはハイブリッドモデルの構想は当初からあったが、店舗への配慮でなかなか踏み切れなかった。しかしブロックバスターは試行錯誤の末、7千店以上の店舗網を「打倒ネットフリックス」の武器に変える手法を見つけたのである。具体的にはオンラインの利用者に対して、ブロックバスターの実店舗も活用できるというメリットを提供したのだ。返却のために店舗に足を運んだ場合は、そのたびに店舗内で映画を無料レンタルできるというボーナス付きである。
この反響は大きかった。開始からわずか2カ月で、ブロックバスター・オンラインは100万人近い新規契約者を獲得し、年内に会員数200万人という目標を達成した。消費者調査でも、ネットフリックスの会員であることによって得られるどんな特典も、ハイブリッドのサービスにはかなわないという結果が出た。3カ月もすれば、オンラインレンタルの新規契約者の100%が、ブロックバスター・オンラインに流れただろう。それどころかネットフリックスの既存顧客も奪いかねない勢いだった。
オンラインから店舗の逆行
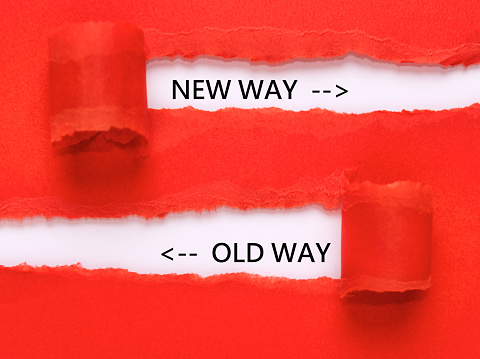
EllysaHo/gettyimages
ブロックバスターへの対抗策が見つからないまま数カ月が過ぎ、投資家がネットフリックスから急速に離れ始めた。このままチキンレースを続ければ共倒れになる。それを防ぐためには、ブロックバスター・オンラインを買収して取り込むしかない。しかしその提案はブロックバスターによって拒否された。まさに八方塞がりだ。
しかし結末はあっけなく訪れた。ブロックバスターのCEOが代わり、オンラインから資金を引き上げ、実店舗への投資を強化したのだ。ブロックバスター・オンラインは値上げせざるを得なくなり、2007年末までには失速してしまう。ネットフリックスは、こうしてふたたび息を吹き返したのである。
ストリーミングサービス
トロイの木馬
2007年、ついにネットフリックスはインターネットを使った動画配信のストリーミングサービスを開始した。こうした動きについて、ケーブルテレビといった既存のメディアや映画製作スタジオといった業界の権威は、自社のコンテンツの二次使用の媒体にすぎないと考え、はじめは軽視していた。実際にネットフリックスが旧作の番組を配信すると、それを見た視聴者が新作に注目し、視聴率も上がった。だからネットフリックスに気前よくコンテンツを提供したのだ。ネットフリックスも自社について、あくまで既存メディアを補完するものに過ぎず、既存のメディアや業界とはWin-Winの関係にあると語っていた。
だが周囲が気を許している間にコンテンツを安く買いあさると、わずか2年でコンテンツ帝国を築いてしまった。いつの間にか契約者数は、ケーブルテレビの最大手に匹敵するまでになっていた。顧客の視聴時間を奪い合うことになった既存メディアは、このときになってネットフリックスという「トロイの木馬」を招き入れたことに、ようやく気づくのである。

この続きを見るには...
残り0/4235文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.08.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約