教養の書

教養の書
著者
著者
戸田山和久 (とだやま かずひさ)
1958年東京都生まれ。1989年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。現在、名古屋大学大学院情報学研究科教授。専攻は科学哲学。著書に『哲学入門』(ちくま新書)、『論理学をつくる』『科学的実在論を擁護する』(名古屋大学出版会)、『知識の哲学』(産業図書)、『科学哲学の冒険』『新版 論文の教室』(NHKブックス)、『「科学的思考」のレッスン』『恐怖の哲学』(以上、NHK出版新書)などがある。
1958年東京都生まれ。1989年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。現在、名古屋大学大学院情報学研究科教授。専攻は科学哲学。著書に『哲学入門』(ちくま新書)、『論理学をつくる』『科学的実在論を擁護する』(名古屋大学出版会)、『知識の哲学』(産業図書)、『科学哲学の冒険』『新版 論文の教室』(NHKブックス)、『「科学的思考」のレッスン』『恐怖の哲学』(以上、NHK出版新書)などがある。
本書の要点
- 要点1教養を身につけるとは、文化遺伝子のリレーの担い手となるということだ。教養とは、知識+人格である。この文脈における人格は、「相対化」と「闊達(かったつ)さ」に集約できる。
- 要点2教養の道の歩みには、認知バイアスや偏見・先入観といった落とし穴がある。これらを回避するひとつのアプローチが、「批判的思考」という自分に対するツッコミである。
- 要点3知らない言葉で思考することはできないので、語彙を豊かにすることが決定的に重要になる。それは自分の言葉の制約から、より自由になることを意味する。
要約
教養とはどのようなものだろうか
文化遺伝子のリレーの担い手に

Italika/gettyimages
ヒトとヒト以外の動物を分けるものに「情報」がある。ヒト以外の生き物の場合、世代から世代へと情報を伝える手段は、ほぼ生物的な遺伝子に限られる。それに対して、ヒトは「文化」や「教育」といったメディアで、世代を超えて情報をリレーさせることができる。こうした媒体を「文化遺伝子」と呼ぶ。
文化遺伝子のなかでも、とりわけ影響が大きいのが「書き言葉」だ。これによって人類の記憶が長期にわたって引き継げるようになった。その結果、「科学や技術」、「概念や理念」といった、人類の生存にとって掛け替えのないものが継承され、発展してきた。
できるだけよいアイデアやよい概念を生み出し、改良し、次の世代に伝えることは、文化遺伝子に依存して生き延びていくヒトという種にとって、決定的に重要なことだ。そうしたリレーの担い手を育てるものこそ、「教養」である。
教養は知識+人格
「教養のある人」というと、どのような人をイメージするだろうか。まず豊かな知識を持つ人というのが思い浮かぶだろう。しかし教養とは知識だけではなく、人格も伴うはずだ。では、それはどのような人格だろうか。著者はそれを「相対化」と「闊達(かったつ)さ」のふたつに集約できると考える。
まず「相対化」である。教養のある人は、自分を特別のものだとは思っていない。自分を超えた人類の知的遺産によって、いまの生存と幸福があることを知っている。そのことを前提にして、自分の考えや価値観を相対化する。たとえば常識というのは、自分を超えた価値尺度のうち、もっとも身近なものだ。しかしこの常識も、さらに高次の価値に照らして、批判的に吟味できる。ここでいう批判的とは、よりよい解に近づくために、あえて異なる視点から見ることをいう。
次に「闊達さ」である。これは「相手の論が正しければ、いつでも自分の方を変える」という余裕のある態度である。教養のある人は、自分を超えた価値に照らし、必要であれば自分を変えていこうとする心のゆとりを持っている。加えて、答えの見つからない状態に耐えるだけの粘り強さもある。
知識のあり方にも違いがある
教養のある人は、人格だけではなく、知識のあり方にも違いがある。
まず知識が「構造化」されている。知識が個々のカテゴリーに分類され、それぞれに重要度が割り振られている。そのうえで、カテゴリーと重要度を飛び越えて知識と知識が結びつき、ネットワークになっている。全体の構造のなかで、何が重要な知識で、何がそれほどでもないかという判断も含めてわかっているのが、教養のある人である。
そして「座標系」である。それぞれの知識が時間的かつ空間的に、大きな座標系のなかに位置づけられている。世界史と世界地図がひとつになったような、分厚い本を思い浮かべてほしい。教養のある人というのは、自分の知識や思考を、どのあたりの時代の、どのあたりの地域に位置づけたらいいのかと考えられる人である。
それは自己形成のプロセス
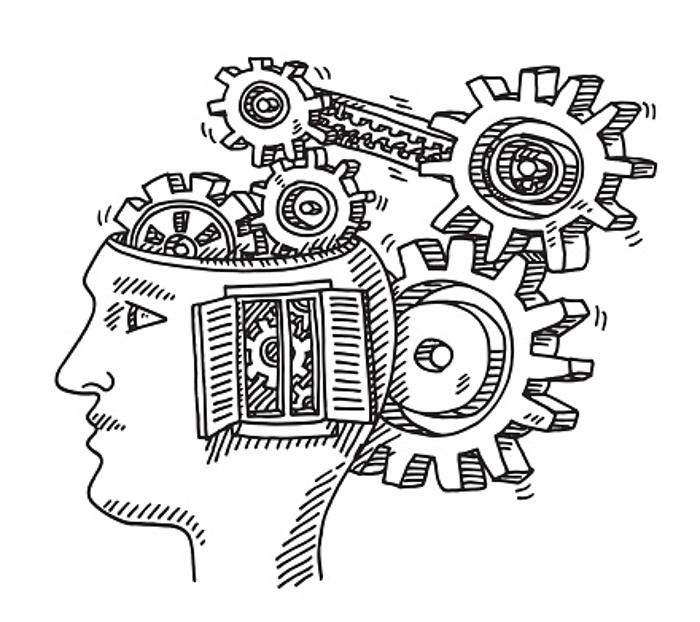
FrankRamspott/gettyimages
明治時代まで、「親は子を教養する」というように、教養は「おしえそだてる」という意味の動詞として使われるのが普通だった。その文脈にならえば、「教養する」最初の行為者は家庭であり、次に学校と書物(現在と過去の教師たち)、最終的には自分自身となる。
それでは教養の目的はなんだろうか? それは文化遺伝子のリレーの参加者を育てることである。これにはふたつの要素がある。

この続きを見るには...
残り2820/4240文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.03.25
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











