日本でいちばん大切にしたい会社7

日本でいちばん大切にしたい会社7
著者

著者
坂本光司(さかもと こうじ)
経営学者。現在「人を大切にする経営学会」会長。千葉商科大学大学院商学研究科中小企業人本経営(EMBA)プログラム長。
1947年、静岡県生まれ。静岡文化芸術大学文化政策学部・同大学院教授などを経て、法政大学大学院政策創造研究科教授、法政大学大学院中小企業研究所所長などを歴任。専門は中小企業経営論、地域経済論、障がい者雇用論。徹底した現場派で、これまで8000社を超える企業の実地調査・アドバイス・研究を続けてきた。
主要著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズ1~6(あさ出版)、『人を大切にする経営学講義』(PHP研究所)、『経営者の手帳』(あさ出版)など、100冊以上がある。
経営学者。現在「人を大切にする経営学会」会長。千葉商科大学大学院商学研究科中小企業人本経営(EMBA)プログラム長。
1947年、静岡県生まれ。静岡文化芸術大学文化政策学部・同大学院教授などを経て、法政大学大学院政策創造研究科教授、法政大学大学院中小企業研究所所長などを歴任。専門は中小企業経営論、地域経済論、障がい者雇用論。徹底した現場派で、これまで8000社を超える企業の実地調査・アドバイス・研究を続けてきた。
主要著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』シリーズ1~6(あさ出版)、『人を大切にする経営学講義』(PHP研究所)、『経営者の手帳』(あさ出版)など、100冊以上がある。
本書の要点
- 要点1著者が人気シリーズ『日本でいちばん大切にしたい会社』を書くことになったきっかけは、日本理化学工業との出会いだった。
- 要点2宮崎県の2世帯に1つが加入している「コープみやざき」は、目の前の組合員を喜ばすことを追求し、組合員から深い信頼を勝ち取っている。
- 要点3振動計測装置の分野でニッチ・トップ・グローバルの実績を誇る「昭和測器」は、創業以来一貫して研究開発の道を歩み、社員ファーストの姿勢で社内外から信頼を集めている。
要約
『日本でいちばん大切にしたい会社』ができるまで
シリーズの原点、日本理化学工業
まずは本シリーズが始まった経緯について紹介しよう。人気シリーズの一冊目にあたる、『日本でいちばん大切にしたい会社』が出版されたのは、2008年のことだ。本が出版される2年ほど前、著者は川崎市にある日本理化学工業と出会う。当時、同社は無名の企業でありながら、約50名のうち35名、つまり率にして70%が障がいのある社員であった。それを知って驚いた著者は、当時社長を務めていた大山泰弘氏のもとを訪れ、話を聞くこととなった。工場の応接室でお茶を出してくれたのが、同社が当時から45年前にはじめて採用した、養護学校卒業の新卒社員だったのである。
当時、彼女の養護学校の先生が大山氏のもとにやってきて、彼女を採用してほしいと嘆願したという。大山氏は最初は断ったが、せめて2週間の就業体験だけでもという先生の熱意にほだされ、体験を受け入れた。すると、体験が終わる前日、全社員15名が大山氏にこう訴えたのである。「自分たちがサポートするから、一生懸命働いている彼女を採用してほしい」。
それ以降も、チョークを生産する工場で、障がい者の人たちが働きやすいような工夫が凝らされてきた。著者はそれまでにも6000社を超える現場を見てきたが、日本理化学工業のような会社は初めてだった。
しばらくして、ある講演会で著者は、日本理化学工業のような会社こそが本当に求められている会社だと語った。これを機に、「正しい経営」を行っている企業をとり上げた『日本でいちばん大切にしたい会社』という本の出版話が持ち上がったのだ。
「5人」の幸せを追求することが会社の使命

oatawa/gettyimages
本シリーズの最初の本が出版されたとき、読者やマスコミから予想を超えた反響があった。著者の研究室や自宅には、メールや手紙、ファックスが殺到することに。そして、本シリーズはいよいよ7作目となる。
著者は一貫して企業の最大の使命と責任は、「5人」のしあわせの追求と実現だと主張してきた。それは、社員とその家族、社外社員(取引先)とその家族、現在顧客と未来顧客、地域住民(とりわけ障がい者や高齢者など社会的弱者)、株主・支援機関である。この要約では、それを体現しているような、お手本となる7社のうち2社について紹介していく。
【必読ポイント!】 社員ファーストを貫く「昭和測器」
振動計測装置でニッチ・トップ・グローバルの座に
1970年に創業した昭和測器は、社員数はわずか30名である。だが、自動車、タービン、その他回転機器などの分野において、多くの画期的な商品を提供してきた。下請けを嫌い、創業以来一貫して研究開発の道を歩んできた同社は、振動計測装置の分野でニッチ・トップ・グローバルの実績を誇っている。
日本にある359万社の企業の99・7%は中小企業だ。過去10年で62万社もの企業が日本から姿を消しているが、その原因の多くは倒産ではなく廃業だ。著者の分析によると、廃業した企業は下請け企業・取引先依存追従型であり、価格をウリにした企業だという。こうした経営では、自分も社員もその家族も幸せになることが難しい。会社の状況を日常的に見ている社長の家族も、事業を継承しようという気にはなかなかならないだろう。
中小企業の生き残りの道は、自ら創造・開発し、大企業では難しいような多品種少量の需要に応えていくことである。規模が小さく、社員数も少なく、需要が大きいわけでもないのに立派な業績を上げている昭和測器は、中小企業の模範といえるだろう。
海底から宇宙まで最先端の技術を支え、堅実に経営
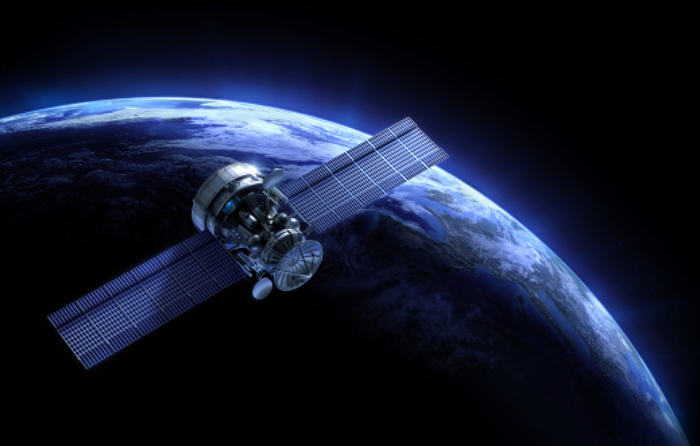
enot-poloskun/gettyimages
昭和測器の主要製品は、微細な振動を計測するさまざまな機器だ。対象に押し当てて数値を読み取るだけで簡単にぶれが計測できる、自社開発の携帯振動計はロングセラー商品となっている。また、同社の高い技術を駆使した精緻な振動計は、理化学研究所が運用している世界一大きな次世代電子顕微鏡の設置や、JAXAの人工衛星の地上における加振試験、そして海底地震の計測などでも使用されている。つまり、海底から宇宙まで、最先端の技術を昭和測器の振動計が支えているというわけだ。年間売上は6億3400万円、創業以来借金ゼロの黒字経営を続けている。
創業者であり現在は会長を務める鵜飼俊吾氏は、バブルの頃、いくら銀行から勧められても不動産、株、債権に一切手を出さなかった。過去の経営経験から、目先の利益に踊らされずに本業に徹することの重要性を、身をもって学んでいたためだ。
一貫した「社員第一主義」の正しい経営
鵜飼氏は、たった1台でも需要がある限りは製品を廃盤にしないと決めている。そのため、同社の製品は多品種少量になっており、年間10台しか売れない製品でも、需要があれば作り続けている。もちろん、社内で「もっと売れる製品に絞ろう」という意見が出ることもある。だが鵜飼氏は、「儲かるからやっているのではない、需要に応えるのが我々の使命だ」という信念を貫いている。
昭和測器の好業績を支えているのは、鵜飼氏の掲げる高邁な経営理念だといっていい。これは、鵜飼氏の人生を大きく変えた、「一燈照隅・万燈照国」という教えに基づいている。「一隅を照らす灯火が集まれば、国中が明るくなる」。つまり、中小企業の力が集まれば、国全体が明るくなるということなのだ。
同社は「社員第一主義」を貫いており、全社員を正社員として採用しているのもその一環だ。また、全社員を入社と同時に、自動的に株主として会社の経営に参画させている。社員に株を無償で提供するかわりに、社員は毎年15%程度で回っている配当金の一部を、株の購入代金として会社に戻しているのだ。これにより、会社は株の譲渡代金を回収でき、社員はお金を出さずに株主として毎年配当金を得られる。
自宅に届いたいただきものであっても、自分のものとは考えずに会社で社員と分け合う、社長もタイムカードを押し、トイレ掃除もみんなで担当するなど、徹底して公平さを追求しているのが特徴的だ。
そんな社風も手伝って、昭和測器では、人を募集すると、有名な大学や大学院を卒業した優秀な人財が殺到する。正しい経営をし、社員の働きがいを大事にしている会社は、中小企業であっても、人手不足とは無縁だということがわかる。
組合員の需要にとことん応える「コープみやざき」
宮崎県の2世帯に1つが加入
全国各地に存在する生活協同組合のなかで、「コープみやざき」は別格の組織だという。出店が始まって以来46年間、15店舗を開店し、1店舗も退店していない。組合員は690人から25万6000人にまで増加し、県内の世帯加入率は53%を上回っているほどだ。しかも、売上高は45年前の1億円弱から、300倍の300億円にも達している。
2019年、コープみやざきは「人を大切にする経営学会」主催の第9回「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」にて、最高賞の「経済産業大臣賞」を受賞した。その際には、組合員からお祝いの生花や手紙、メールが数多く届いたという。これほどまでに地域や顧客から高い評価を得ているお店は珍しい。コープみやざきがここまで高い伸び率を実現してきた背景には、歴代の役職員たちが正しく誠実な経営を継続し、組合員から全幅の信頼を勝ち取ってきたことがある。
組合員自身が主人公であり、経営者である

kuppa_rock/gettyimages
コープみやざきの前身は、1972年に主婦たちがつくった消費者の会にさかのぼる。そこには、「安全なものをより安く子供たちに食べさせたい」という願いがあった。
主婦たちの共同購入からスタートしたコープみやざきは、順調に組合員数と業績を伸ばしていく。だが1988年には新業態に挑戦し、失敗。大きな赤字を出したことが、自分たちの存在意義を問い直すきっかけとなった。「コープみやざきは組合員のものであり、組合員のためにあること。組合員自身が主人公であり、経営者であること」。こうした基本方針を策定するに至った。
パジャマの下だけでも売る究極のサービス
要望があれば、できることをなんでもやる。これがコープみやざき流だ。「夏のパジャマの上はTシャツを着るから、下だけ売ってもらえないか」。組合員からこう尋ねられたら、セットのパジャマをバラして半額で売ってしまう。残った上のパジャマをどうするかはあとで考え、その瞬間は目の前の組合員のことだけを考えて行動すればいいというのだ。「電池1個」「封筒1枚」といった声にも喜んで応じる。

この続きを見るには...
残り597/4056文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.04.13
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











