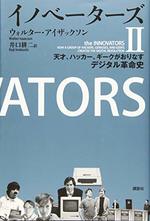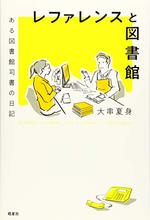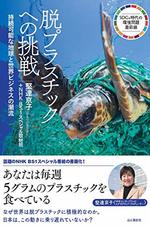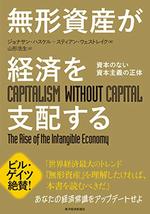サイバーセキュリティ
組織を脅威から守る戦略・人材・インテリジェンス
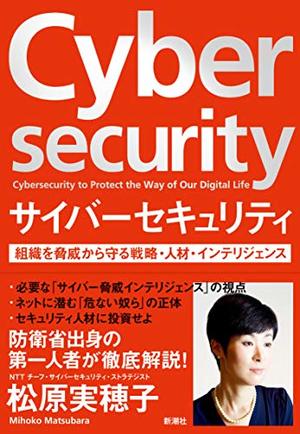
著者
松原実穂子 (まつばら みほこ)
早稲田大学卒業後、防衛省にて9年間勤務。フルブライト奨学金を得て、米ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)に留学し、国際経済及び国際関係の修士号取得。修了後、ハワイのシンクタンク、パシフィック・フォーラムCSISにて研究員として勤務。日本に帰国後、株式会社日立システムズでサイバーセキュリティのアナリスト、インテル株式会社でサイバーセキュリティ政策部長、パロアルトネットワークスのアジア太平洋地域拠点における公共担当の最高セキュリティ責任者兼副社長を歴任。2019年11月現在、NTTのチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストとしてサイバーセキュリティに関する情報発信と提言に努める。
早稲田大学卒業後、防衛省にて9年間勤務。フルブライト奨学金を得て、米ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)に留学し、国際経済及び国際関係の修士号取得。修了後、ハワイのシンクタンク、パシフィック・フォーラムCSISにて研究員として勤務。日本に帰国後、株式会社日立システムズでサイバーセキュリティのアナリスト、インテル株式会社でサイバーセキュリティ政策部長、パロアルトネットワークスのアジア太平洋地域拠点における公共担当の最高セキュリティ責任者兼副社長を歴任。2019年11月現在、NTTのチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストとしてサイバーセキュリティに関する情報発信と提言に努める。
本書の要点
- 要点1企業や国家へのサイバー攻撃被害額は、日本の実質GDPを超える規模にまで拡大しつつあり、世界的な脅威となっている。
- 要点2サイバー攻撃者には多くの場合、国家や犯罪組織が関与している。彼らに対抗する存在が、政府や企業内にいるサイバーセキュリティ人材であり、安心安全なITインフラの維持に貢献してくれている。
- 要点3防御側の技術的強化、具体的な対策立案、組織危機意識向上のために役立つのが、「サイバー脅威インテリジェンス」である。サイバー脅威インテリジェンスを経営判断にもうまく活用すれば、未来の脅威に備えることは可能である。
要約
知らぬ間に企業や国家を巻き込むサイバー攻撃の実例
事業計画が盗まれ経営破綻

spyarm/gettyimages
世界各国で、サイバー攻撃の生々しい事例が報告されている。
たとえばカナダの通信機器メーカー大手であるノーテル・ネットワークス。同社は少なくとも2000年から10年弱に渡り、中国からサイバー攻撃を受けていたと見られる。発覚の端緒は、カナダにいる経営幹部が、普段であればアクセスしないような英国の資料をダウンロードしていた記録にある。調査の結果、経営陣のアカウントが乗っ取られ、技術文書や研究開発報告書、事業計画などが盗まれていた。しかし明確な手がかりが得られないまま調査は打ち切られ、その後数年間被害を受け続けた。
被害と経営の直接的な因果関係はわからない。だが競合他社に情報が漏れたことで、結果として2009年、同社は経営破綻に追い込まれてしまった。
国家機能を麻痺させても罰金18万円の不思議
続いて、エストニアの事例。同国は、行政から金融までさまざまなサービスがインターネットに繋がったIT先進国として有名だ。それは裏を返せばサイバー攻撃の入口が広がっているということであり、事実ロシアからの大規模なサイバー攻撃を許してしまった。
もともと同国には、エストニア系住民とロシア系住民の対立という歴史的背景があった。2007年、ロシア系住民の暴動があり、それに対してエストニア系住民が攻撃。一挙にロシア対エストニアの対立が起きた。このときロシアが大規模なサイバー攻撃を仕掛け、政府の機能や公的サービスが麻痺してしまう大惨事となった。
だがエストニアの刑法では、過去にこのような犯罪がなかった。そのため、このときに逮捕されたロシア系エストニア人の学生は、たった18万円の罰金刑ですまされるという結末になってしまった。
サイバー攻撃による選挙介入
サイバー攻撃による他国への選挙介入も明らかになってきた。選挙介入の目的は、特定の候補者を勝たせたり負けさせたりすることで、政治的利益を得ることだ。また有権者にその国の選挙制度や民主主義体制への信頼を失わせ、政治的均衡を崩し、国力にダメージを与えることも目的に含まれる。
2016年のアメリカ大統領選挙でのロシア介入疑惑は記憶に新しい。日本ではサイバー攻撃での選挙介入問題についてほとんど議論されていないものの、もはや対岸の火事と楽観視することはできない。
国境を跨いで暗躍する「攻撃者」の正体
組織内部・外部の脅威
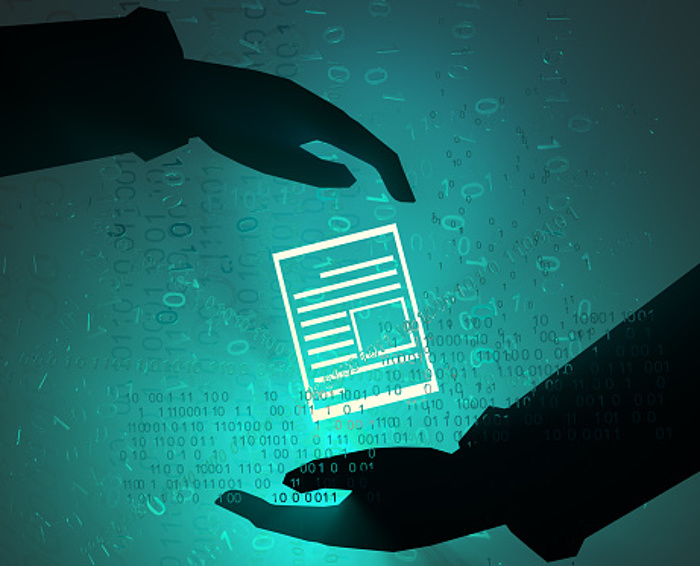
higyou/gettyimages
サイバー攻撃は、誰がどのように起こしているのだろうか。
まず組織内部から発生するケースがあげられる。社員や元社員、下請け業者が立場を悪用して機密情報を盗む意図的なものもあれば、社員がメール誤送信で情報漏洩するなどうっかりミスで起きることもある。これらを防ぐには、社員のアクセス権を最小限にする、データの持ち出しを制限する、本業とは関係ない「怪しい」行動をする社員に対して、AIを使った「ふるまい検知」システムを活用するなどの対策が考えられる。
次に外部の攻撃者については、国家と犯罪集団があげられる。国家は諜報・妨害活動を行い、組織は金銭目的でサイバー犯罪を行う。アメリカ政府の想定では、サイバー攻撃を行なっている国家は中国、ロシア、北朝鮮、イランなど、2016年後半時点で30カ国以上あるという。
外貨不足をサイバー攻撃利益で補う北朝鮮
北朝鮮のインターネット普及率は1%弱と、世界で最もネットへの繋がりが制限されている。つまり攻撃に対する守りは強固なのだ。一方で中国に触発された北朝鮮は、1990年代後半から選抜した学生にIT英才教育を施し、2009年頃からサイバー部隊を編成、他国への攻撃を始めたと言われている。

この続きを見るには...
残り2971/4481文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.04.21
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約