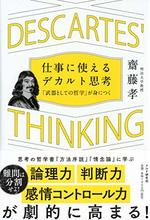世界は贈与でできている
資本主義の「すきま」を埋める倫理学

著者
近内悠太 (ちかうち ゆうた)
1985年神奈川県生まれ。教育者。哲学研究者。
慶應義塾大学理工学部数理学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。
本書『世界は贈与でできている』がデビュー著作となる。
1985年神奈川県生まれ。教育者。哲学研究者。
慶應義塾大学理工学部数理学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。
本書『世界は贈与でできている』がデビュー著作となる。
本書の要点
- 要点1生きる意味や仕事のやりがい、大切な人とのつながりなど、とても大切なのにお金で買えないものは、他者から贈与してもらうことでしか手に入らない。
- 要点2贈与は、贈与だと気づかれてはいけない。気づかれれば商品の売買のような「交換」になってしまう。
- 要点3贈与は交換と違い、瞬時に完了しない。差出人にとっては「届いてくれるといいな」と未来形で、受取人にとっては「すでに受け取っていた」と過去形で完了するものだ。
- 要点4贈与の差出人は、与えるだけの人ではない。他者へ贈与するという行為を通して、逆にさまざまなものを受け取っている。
要約
「お金で買えないもの」の正体
もらったプレゼントには、なぜ価値があるのか
本書では、信頼関係や助け合いのようにお金で買えないもの、およびその移動をひとまず「贈与」と呼ぶことにする。しかし「お金で買えないもの」という定義では、それらが何であるか一向に理解できない。お金で買えないものは、どうやって手に入れたらよいのか。どこから私たちのもとにやってくるのか。
贈与のいちばんわかりやすい例が、プレゼントである。なぜ互いにモノを贈り合うという慣習があるのだろうか。それは誰かからプレゼントされた瞬間、モノがただのモノではなくなり、商品の価値からはみだす「特別な何か」が付与されたと感じるからだ。だから私たちは他者から贈与されることでしか、本当に大切なものを手にすることができないのである。
贈与の中でしか生きていけない人類

Jolygon/gettyimages
なぜ私たち人間は他者と協力し合い、助け合うのか。どうして一人では生きていけなくなったのか。
それは人類が、きわめて未熟な状態で生まれてくることに端を発する。乳幼児を抱えた母親は、数年間にわたって食べ物を自分の力で採取することができず、子育てを周囲の人間に手伝ってもらわなければならなかった。つまり人類は黎明期から、「他者からの贈与」「他者への贈与」を前提として生きていくことを運命づけられてしまったのだ。
ギブ&テイクの限界点
ビジネスの文脈だと、相手に何かをしてほしかったら、対価を差し出すしかない。しかし「助けてあげる。で、あなたは私に何をしてくれるの?」というギブ&テイクの世界には、信頼関係が存在しない。そこでは、他者はあくまでも手段でしかない。裏を返せば、信頼は贈与の中からしか生じないのだ。
ギブ&テイク、つまり交換の論理が徹底された資本主義の世界では、死ぬその瞬間まで一瞬も休むことなく、商品を買い続けなくてはならない。たとえすべてを失った人であっても、「助けて」と叫ぶことができない世界だ。そんな誰にも頼ることができず、誰からも頼りにされない状態を、私たちはこれまで「自由」と呼んできたのである。
名乗らない贈与者、サンタクロース
贈与が「呪い」になるとき
ギブ&テイクの関係ではないつながりは、本質的に贈与的なつながりとなる。私たちは知らず知らずのうちに、贈与を通して他者とつながっている。しかし贈与の力は、自らと他者を縛りつける「呪い」ともなる。それは誰かとのつながりを求めながら、同時にそのつながりに疲れ果てるという相矛盾した状態だ。
なぜこんな状態が生まれるのか。「贈与は、それが贈与だと知られてはいけない」からである。贈与であると知られてしまえば、受取人には返礼する義務が生まれ、単なる交換になってしまう。もし受取人が何も交換するものを持っていなければ、返礼の義務は受取人を押しつぶす呪いとなるだけだ。
一方で、ずっと気づかれない贈与は、贈与として成立しない。贈与したそのときではなく、未来のある時点で「あれは贈与だった」と気づいてもらう必要がある。
16時の徘徊とサンタクロース

allanswart/gettyimages
ある男性が、認知症の母親を介護していた。その母親は16時になると外に徘徊に出かけようとし、止めようとしても必死の形相で抵抗する。
困り果てた男性がベテランの介護職員に相談したところ、16時というのは数十年前、彼が幼稚園のバスで帰ってくる時間だったことに気づいた。

この続きを見るには...
残り2631/4009文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.05.12
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約