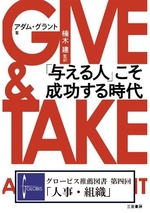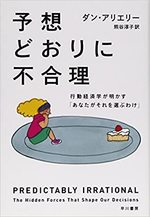仮説思考
BCG流 問題発見・解決の発想法
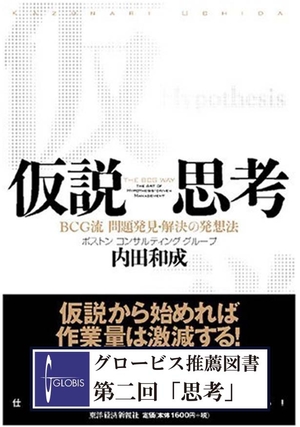
著者
内田 和成
早稲田大学ビジネススクール教授。東京大学工学部卒。慶應義塾大学でMBA(経営学修士)を取得。日本航空を経て、1985年にボストンコンサルティング グループ(BCG)に入社。2000年6月から2004年12月までBCG日本代表、2009年12月までシニア・アドバイザーを務める。ハイテク、情報 通信サービス、自動車業界を中心に、マーケティング戦略、新規事業戦略、中長期戦略、グローバル戦略などの策定・実行支援プロジェクトを数多く経験(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『BCG流 競争戦略 加速経営のための条件』が刊行された当時に掲載されていたものです)
早稲田大学ビジネススクール教授。東京大学工学部卒。慶應義塾大学でMBA(経営学修士)を取得。日本航空を経て、1985年にボストンコンサルティング グループ(BCG)に入社。2000年6月から2004年12月までBCG日本代表、2009年12月までシニア・アドバイザーを務める。ハイテク、情報 通信サービス、自動車業界を中心に、マーケティング戦略、新規事業戦略、中長期戦略、グローバル戦略などの策定・実行支援プロジェクトを数多く経験(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『BCG流 競争戦略 加速経営のための条件』が刊行された当時に掲載されていたものです)
本書の要点
- 要点1仮説思考を使えば、手元にあるわずかな情報だけで、最初にストーリーの全体構成を創ることができる。
- 要点2仮説立案に定石はないが、脳をゆさぶるコツを身に着け訓練することで、ヒラメキを生むことができるようになる。
- 要点3仮説の検証方法は、実験、ディスカッション、分析の3つがある。
- 要点4少ない情報から答えを出すという仮説思考が、初めからうまくいくわけはない。大いに失敗するべきだ。
要約
まず、仮説ありき

imtmphoto/iStock/Thinkstock
網羅思考では情報の洪水に溺れてしまう
一般に企業はできるだけたくさんの情報を集めてから、意思決定しようとする傾向が強い。経営陣から社員まで大半が情報コレクター(網羅思考)になっている。しかし、意思決定に使える時間には限りがあり、完璧な答えが出るまで意思決定を先送りしたくても、相手は待ってはくれない。迅速な意思決定のためには、今ある選択肢をいかに絞り込むかという視点で情報収集すべきである。
たとえばメーカーが業績不振を立て直す事業戦略を構築したとする。一般的なアプローチでは、最初にすべての課題をリストアップしようとする。その中には大小さまざまな問題が混在し、てんこ盛りになる。施策についても、10以上の課題に30くらいの施策が提案され実現も容易ではない。これぞまさに網羅思考の弊害だ。このような方法ではなく、解決策に繋がるいくつかの課題=仮説にフォーカスしたほうがいい。
大きなストーリーが描けるようになる
仮説思考を使えば、手元にあるわずかな情報だけで、最初にストーリーの全体構成を創ることができる。証拠が不十分でも、問題に対する解決策や戦略まで踏み込んで、全体のストーリーを作ってしまう。そうすると、ごく一部の証拠は揃っているけれども、大半は証拠がない状態になり、そこから証拠集めを開始することになる。
その場合には、自分が作ったストーリー、つまり仮説を検証するために必要な証拠だけを集めればいいので、無駄な分析や情報収集の必要がなくなり、非常に効率が良くなる。
「いろいろな可能性が考えられる段階で、大胆に1つのストーリーをつくり上げたりしたら、重大なことを見逃し、間違ったストーリーを作ってしまうのではないか」と心配する人がいる。だが、それは杞憂だ。そのような場合には、ストーリーの証拠集めをした段階で、仮説を肯定する証拠がなかなか集まらない。そして必然的に自分のつくったストーリーが間違いであることにすぐ気付き、初期段階であることから、余裕をもって軌道修正ができる。
3か月程度のプロジェクトであれば、著者はプロジェクトリーダーには2週間で答えを出すように求めているそうだ。仮説思考を実践すれば、情報の洪水に溺れることなく、全体感をもって迅速かつ効果的に問題解決を図ることができるのだ。
【必読ポイント!】仮説を立てる

daizuoxin/iStock/Thinkstock
仮説立案に定石はない
BCGの社内で「コンサルタントはどんなときに仮説を思いついているのか」というアンケートをとったことがある。最も多かった回答は「ディスカッション中に思いつく」だった。次は「インタビュー中、あるいはインタビュー後に思いつく」だ。そのほかにも「突然思いつく」、「じっくり考えているときに思いつく」という回答もあった。つまり仮説の立て方は人それぞれで定石はないのである。

この続きを見るには...
残り3065/4223文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2014.08.05
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約






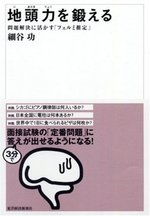
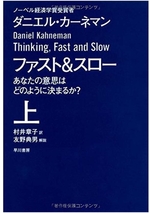
![[実況]ロジカルシンキング教室](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/254_cover_150.jpg)