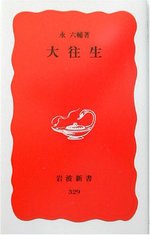クビライの挑戦
モンゴルによる世界史の大転回
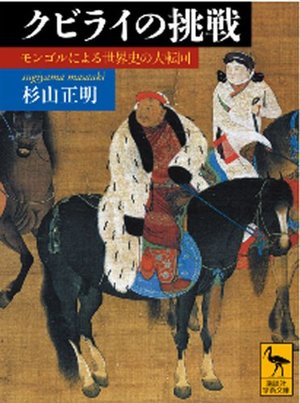
著者
杉山正明(すぎやま まさあき)
1952年、静岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科教授を経て、京都大学名誉教授。2020年没。著書に『モンゴル帝国の興亡』(上下)、『中国の歴史08 疾駆する草原の征服者』『興亡の世界史09 モンゴル帝国と長いその後』ほか。1995年に本作でサントリー学芸賞、2003年に司馬遼太郎賞、2006年に紫綬褒章、2007年に日本学士院賞を受賞。
1952年、静岡県生まれ。京都大学大学院文学研究科教授を経て、京都大学名誉教授。2020年没。著書に『モンゴル帝国の興亡』(上下)、『中国の歴史08 疾駆する草原の征服者』『興亡の世界史09 モンゴル帝国と長いその後』ほか。1995年に本作でサントリー学芸賞、2003年に司馬遼太郎賞、2006年に紫綬褒章、2007年に日本学士院賞を受賞。
本書の要点
- 要点1これまでモンゴル帝国は、中国文明の破壊者という認識が普通であった。しかし、クビライの築いたモンゴルという時代を、もう一度正しく見直すべきだ。
- 要点2軍事力による西方への進攻に限界を見たクビライは、通商によって世界を結びつける構想へと切り替える。東方の強力な諸勢力をまとめ上げることで確固たる地位を確立し、政権をクー・デタ的に奪取した。
- 要点3クビライ帝国の特徴は、その主軸に経済の掌握を据え、ユーラシア大陸の広大な規模で交易圏を築いた。大航海時代の前に起こった、この世界のゆるやかな統合化現象から目をそらして世界史を語ることはできない。
要約
あらたな世界史像をもとめて
モンゴルは中国文明の破壊者か

hadynyah/gettyimages
これまでモンゴル支配による時代は、暴力・破壊・搾取・野蛮・不寛容・非文明などといった悪い評価がふつうであった。モンゴル統治以前にめざましい発展をとげ、世界最高の社会・技術水準に達していた中国は、モンゴルによる致命的な痛手と頓挫を味わった。こうしたイメージは、中国史研究者にも広く浸透している。しかし、本当にモンゴルは「文明の破壊者」だったのだろうか。
たとえばソ連時代のロシアでは、「タタルのくびき」が小学校の教科書にも取り上げられ、世代を超えて受け継がれてきた。タタルとはモンゴル系の有力な遊牧集団のことで、そのタタルによって行われた「ロシア・東欧遠征」の恐ろしさを表した話である。だが、実のところ多くの都市は無傷だった。モンゴルにすすんで臣従する者も現れた。モスクワに至ってはモンゴルと親密になることで権力を強め、ロシア全域の徴税を委ねられることとなった。しかし「タタル」を悪者にすることで、ロシアの権力者の正当化と民族意識の昂揚を図ったのである。
元代の中国に関する歴史記述も、モンゴルへの偏見と思い込みに満ちている。たとえば、南宋時代の杭州の繁栄を語る史料としてマルコ・ポーロなどの旅行記が使われるが、彼が訪れたのはモンゴル統治下であった。実際に杭州は無血開城によってモンゴル統治下に入り、その後も政治ぬきにして繁栄を続けた。また、チンギスの子孫を頂点とした人種・地域による「四階級制」は限りなく誤解に近い。モンゴルは、人種・言語・宗教・文化の違いにほとんどこだわらず、能力主義・実務主義の人材選抜を行った。
世界史とモンゴル時代
近年、歴史学の分野を「世界システム」という考え方が席捲している。これは、大航海時代を端緒として、西欧における生産を頂点に、地球上の各地はしだいにひとつのものとして機能しはじめた、という観念である。
しかし、ペルシア語を中心とした「西方史料」と漢文を主体とした「東方史料」とで、見える歴史像は変わってくる。ある「文明圏」で展開した歴史現象が、実際には他の「文明圏」とかかわりをもっていたとしても、複数の「文明圏」にわたる文献と視点を歴史学者がほとんどもちえないことが壁となり、それぞれは異なる「文明圏」に留まるものと考えられてきた。ところが、極めて稀な例外として、東西の世界が文献の上からもひとつにまとまった時代がある。モンゴル時代だ。
本書は、「世界史」「人類史」の上で際立って特別な意味合いを持つ、ユーラシア大陸をおおう大経済圏を築いたモンゴル時代について、「すくなくともこう考えざるをえない」ことを提示する。それは、クビライが構想した世界国家「大元ウルス(国)」と、それを中心とした世界通商圏に包まれたユーラシア世界についての仮説だ。
世界史の大転回
ユーラシアの多極化時代
西暦1260年は世界史を変える年となった。クビライの弟であるフレグ率いるモンゴル西征軍が、エジプトのマルムーク軍団と会戦したのだ。通称「アイン・ジャールートの戦い」である。意外にもマルムーク軍が勝ち、モンゴル軍は獲得したばかりのシリアをもあとにすることとなった。しかしこの戦いは会戦そのものよりも、それが歴史上に与えた影響において大きな意味を持った。

この続きを見るには...
残り2795/4149文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2022.05.11
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約