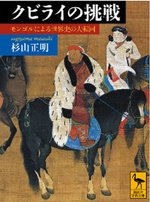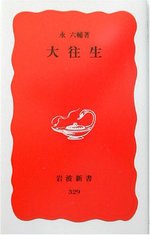音楽する脳
天才たちの創造性と超絶技巧の科学

著者
大黒達也(だいこく たつや)
1986年、青森県生まれ。医学博士。東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構特任助教。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学勤務などを経て現職。専門は音楽の神経科学と計算論。神経生理データから脳の創造性をモデル化し、創造性の起源とその発達的過程を探る。また、それを基に新たな音楽理論を構築し、現代音楽の制作にも取り組む。主な著書に『芸術的創造は脳のどこから産まれるか?』(光文社新書)など。
1986年、青森県生まれ。医学博士。東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構特任助教。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学勤務などを経て現職。専門は音楽の神経科学と計算論。神経生理データから脳の創造性をモデル化し、創造性の起源とその発達的過程を探る。また、それを基に新たな音楽理論を構築し、現代音楽の制作にも取り組む。主な著書に『芸術的創造は脳のどこから産まれるか?』(光文社新書)など。
本書の要点
- 要点1ピタゴラスによる音律・音程・オクターブの発見が12平均律の誕生に繋がり、曲を自由に転調できるようになり、音楽が身近になった。
- 要点2脳の最も普遍的な学習システムである統計学習機能が、音楽の確率を計算する。
- 要点3音楽の芸術性は、作品の確実性と不確実性の絶妙なバランスを追求することにある。
- 要点4音楽は、言葉にできない感動のような感情を呼び起こす魔法のツールだ。
要約
音楽を科学する
脳の進化と音楽の変化
なぜ人は音楽を必要とし、音楽に感動するのか。この疑問への回答に人類はたどりついていないが、これが解明されれば私たちは音楽とさらに深く繋がることができるだろう。
音楽と脳、音楽と人間の関係を知ることは、私たち自身を知ることだ。芸術の起源を辿ってみると、約4万~5万年前の世界最古のフルートがヨーロッパで発見されている。文字を生み出した紀元前3000年頃よりも遥か大昔から、ヒトは音楽活動を行い、新たな価値を創出してきたのだ。
ヒトは何万年とかけて音楽の表現方法を模索し、様々な音の響きを「音楽」と認識できるようになった。現代人の脳にある音楽と非音楽の境界線も、脳の発達によって変わりうるものだ。現時点で「非音楽」と感じる音であっても、感動する未来が来るかもしれない。
ピタゴラスの発見と問題点

AmandaLewis/gettyimages
芸術と科学とは、感性と論理のように対照的に述べられることが多い。しかし、どちらも起源は同じだ。表現の仕方が対照的であっても、自然の不思議な現象を共有したいという根本は共通している。
音楽は、科学の進歩とともに変化してきた。「三平方の定理」を発見した古代ギリシャの天文学者ピタゴラスは、音楽の最も重要な要素である「音律」と「音程」を発見した人物でもある。音律とは、オクターブの中のどのような高さの音を用いるかを規定するもので、音程は2つの音の高さの差を表す。
ピタゴラスは、羊の腸で作った「弦」を用い、一定の長さの弦と、その半分の長さの弦を同時に弾くと、音の高さは違うにもかかわらず同じ音に聴こえることに気づいた。これが「オクターブ」の発見だ。
さらに、一定の長さの弦と、その2/3の長さの弦を同時に鳴らすと、とても協和した響きを出すことに気づいた。これはドとソの音程に相当する。ピタゴラスは、弦の長さを2/3ずつ短くしていくことで、オクターブの中に何個の音があるかを探っていった。
しかし、ピタゴラスの手法で1オクターブ内に音階を作ろうとすると、綺麗に収まらず、ずれが生じてしまう。多くの音楽学者たちはこれを解決しようと、新しい音律を探求した。その結果、「純正律」が生み出された。バッハやモーツァルトの時代の音楽は、この純正律が用いられていたといわれている。
音の響きが綺麗であった純正律であるが、同じ半音程でも音の高さによって違う音程が生まれてしまうという欠点があった。そのままでは、転調すると元の曲とは違う曲ができあがってしまう。その問題を解決したのが、現在私たちが用いている「12平均律」だ。
無調音楽の奥深さ
現代の音楽では12平均律に現れる音しか耳にしていないため、私たちの耳は12平均律に順応しているといえる。
音楽から調性をとったような音楽を「無調音楽」という。ロマン派後期から近代にかけて活躍した作曲家アルノルト・シェーンベルクは、無調音楽「十二音技法」を生み出した人物だ。
十二音技法の曲を初めて聴くと、あまりの難解さに音楽として楽しむことが難しい。しかし何度も聴くと、徐々にその奥深さが堪能でき、最後には普段音楽に感動するのと同じように感動できる。私たち人間の脳は、無調音楽に順応できるのだ。
最上の音楽を作るには
「真に新しい曲」を作る難しさ

yanyong/gettyimages
「新たに曲を作る」ことが作曲家の仕事だ。どの分野でも起こりうることだが、学べば学ぶほど、自分の作品が「特段新しくない」ということを知り、「作れなくなる」という現象が起こる。作曲家は、「音楽理論」のような知識だけでなく、さまざまなタイプの知識を駆使して「真に新しい」曲を作らなければならない。

この続きを見るには...
残り3165/4641文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2022.05.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2022 大黒達也 All Rights Reserved.
本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は大黒達也、株式会社フライヤーに帰属し、事前に大黒達也、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2022 大黒達也 All Rights Reserved.
本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は大黒達也、株式会社フライヤーに帰属し、事前に大黒達也、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約