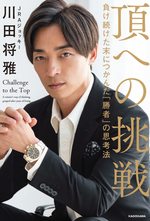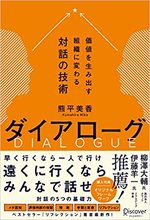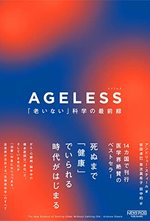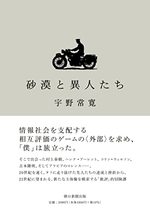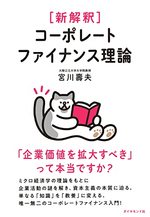物価とは何か
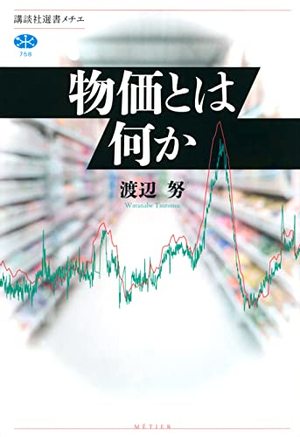
物価とは何か
著者
著者
渡辺努(わたなべ つとむ)
1959年生まれ。東京大学経済学部卒業。日本銀行勤務、一橋経済研究所教授等を経て、現在、東京大学大学院経済学研究科教授。株式会社ナウキャスト創業者・技術顧問。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。ハーバード大学Ph.D.。専攻はマクロ経済学。著書に『世界インフレの謎』(講談社現代新書)、『市場の予想と経済政策の有効性』(東洋経済新報社)、『新しい物価理論 物価水準の財政理論と金融政策の役割』(共著、岩波書店)、『慢性デフレ 真因の解明』)(編著、日本経済新聞出版社)、The Economics of Interfirm Networks(共編著、Springer)、Property Price Index: Theory and Practice(共編著、Springer)などがある。
1959年生まれ。東京大学経済学部卒業。日本銀行勤務、一橋経済研究所教授等を経て、現在、東京大学大学院経済学研究科教授。株式会社ナウキャスト創業者・技術顧問。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。ハーバード大学Ph.D.。専攻はマクロ経済学。著書に『世界インフレの謎』(講談社現代新書)、『市場の予想と経済政策の有効性』(東洋経済新報社)、『新しい物価理論 物価水準の財政理論と金融政策の役割』(共著、岩波書店)、『慢性デフレ 真因の解明』)(編著、日本経済新聞出版社)、The Economics of Interfirm Networks(共編著、Springer)、Property Price Index: Theory and Practice(共編著、Springer)などがある。
本書の要点
- 要点1物価変動の原動力は「貨幣の魅力」にある。それを担保しているのは「決済サービス」としての役割か、政府という徴税権を持った存在なのか、判断することは難しい。大事なのは、どちらかの見方に固執しないことである。
- 要点2中央銀行は、人々の予想するインフレ率のほうが高い場合には、金利を大幅に上げることで、その予想に対抗できる。一方、デフレの場合は物価をコントロールする力が限定される。
- 要点3「人々が主体的に情報を取得し、それを活用して予想している」「人々は自分なりにモデルを使って将来を予測している」という考えが定着した結果、中央銀行は自らの行動原理を正確に伝えることを重視するようになった。
要約
【必読ポイント!】 物価とは何か
物価とは「蚊柱」である
夏の水辺などで、蚊の群れが局所的に飛び交っているのを目撃することがある。それは「蚊柱」と呼ばれ、遠くからだと文字通り、柱のように見える。
物価とは、この蚊柱のようなものだ(この蚊柱の比喩は、岩井克人『ヴェニスの商人の資本論』に拠る)。世の中の商品は、蚊柱における一匹一匹の蚊に相当する。すごい速さで移動する蚊もいれば、ゆっくりと移動する蚊もいるが、蚊柱全体としてはまとまっている。商品も、個々の商品の動きが多少揺らいでも、全体的に1カ所にとどまっていれば、それは物価が安定しているということである。
もし全体が急速度で移動していたら、インフレ(物価上昇)やデフレ(物価下落)に陥っているということだ。また、個々の価格がまったく動かない場合も問題である。1ミリも動かない蚊が、安定しているのではなく死んでいるように、売り手や買い手の事情による価格変動のような経済の健全な動きが止まっていたら、そこには問題が起きている。
物価とは「貨幣の魅力」である

brightstars/gettyimages
ひとつひとつの価格の変動が、そのまま物価の変動につながるわけではない。
ある商品の価格が大幅に上昇したり下落したりしても、それは一過性のもので、揺り戻しがくる。また、商品同士の連動性も低い。ゆえに物価変動の原動力は、個別商品の魅力にあるわけではない。
物価変動の原動力が「個別商品の魅力」にはないならば、他に考えられるのは「貨幣の魅力」である。なぜ貨幣に魅力があるのか。
まず考えられるのが、貨幣は商品を購入する際の「支払い手段」、つまり決済サービスという見方だ。決済サービスを通じ、わたしたちはさまざまなモノやサービスにアクセスできる。

この続きを見るには...
残り3881/4594文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.04.08
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2023 渡辺努 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は渡辺努、株式会社フライヤーに帰属し、事前に渡辺努、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2023 渡辺努 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は渡辺努、株式会社フライヤーに帰属し、事前に渡辺努、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約