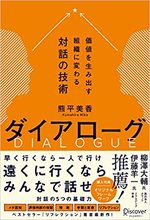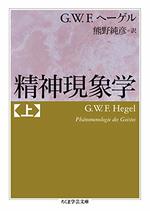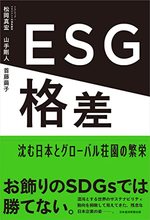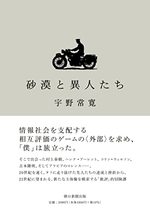新解釈 コーポレートファイナンス理論
「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?
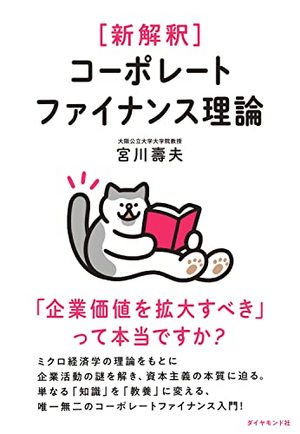
著者
宮川壽夫(みやがわ ひさお)
大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部 教授
博士(経営学)。筑波大学大学院博士後期課程修了。
1985年4月野村證券株式会社入社。営業部門、英国留学、投資銀行部門を経て2000年8月米国トムソンファイナンシャル・コンサルティンググループに移籍(アジア統括シニアディレクター)。2007年10月に再び野村證券株式会社に移籍(IBコンサルティング部上級専任職エグゼクティブディレクター)。2010年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院に専任講師として赴任。同年10月准教授、2014年4月教授。2015年4月よりワシントン大学(University of Washington)客員研究員を兼任。2020年4月一橋大学大学院客員研究員を兼任(〜2021年3月)。上場企業の社外取締役・監査等委員を兼任。
主な著書に『企業価値の神秘 コーポレートファイナンス理論の思考回路』(2016年、中央経済社)、『配当政策とコーポレート・ガバナンス 株主所有権の限界』(2013年、中央経済社)。他論文、メディア向け論稿多数。
大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部 教授
博士(経営学)。筑波大学大学院博士後期課程修了。
1985年4月野村證券株式会社入社。営業部門、英国留学、投資銀行部門を経て2000年8月米国トムソンファイナンシャル・コンサルティンググループに移籍(アジア統括シニアディレクター)。2007年10月に再び野村證券株式会社に移籍(IBコンサルティング部上級専任職エグゼクティブディレクター)。2010年4月大阪市立大学(現大阪公立大学)大学院に専任講師として赴任。同年10月准教授、2014年4月教授。2015年4月よりワシントン大学(University of Washington)客員研究員を兼任。2020年4月一橋大学大学院客員研究員を兼任(〜2021年3月)。上場企業の社外取締役・監査等委員を兼任。
主な著書に『企業価値の神秘 コーポレートファイナンス理論の思考回路』(2016年、中央経済社)、『配当政策とコーポレート・ガバナンス 株主所有権の限界』(2013年、中央経済社)。他論文、メディア向け論稿多数。
本書の要点
- 要点1コーポレートファイナンス理論は企業価値を拡大する方法ではなく、企業行動のミステリーを解明するための学問だ。
- 要点2時価総額に有利子負債を足し、現金と預金を差し引いた金額と非事業用資産を加えたものが「企業価値」である。資本コスト以上のキャッシュを獲得すると企業価値は拡大する。
- 要点3完全市場に近い現実の世界で、不可能に近い企業価値の拡大を実現するには、企業にとって従来の連続性を打ち破ることが必要だ。
- 要点4費用を削減しても企業価値が拡大するとは限らない。手元に置いてある現金に価値はなく、将来どれだけのキャッシュフローを生む力があるかにこそ、価値がある。
要約
【必読ポイント!】 企業価値の拡大とは
企業のミステリーを解明する学問
「企業は企業価値拡大という目的を果たさねばならない。そのためにはコーポレートファイナンス理論を勉強し、企業価値拡大の方法を学ぶ必要がある」
よく見聞するこうした言説に、多くの人はさして疑問を持たないのではないだろうか。しかし、「この初期設定がそもそも間違っている」というのが本書の中心的な問題意識だ。
本来コーポレートファイナンス理論が教えることは「仮に企業の目的がその価値の拡大にあるとしたら、企業はどのような行動を取るだろうか」という論理の道筋だ。企業価値拡大の実践的ハウツウを提供する学問ではない。
将来なにが起きるかをだれも予知できず、だれもがその不確実性に不安を抱きながら決断を下す。その決断と行動をどのように評価すべきか――。そのような果てしなく膨大な思考過程を説明するため、時としてさまざまな二律背反を相克しながら、コーポレートファイナンス理論は体系づけられている。
企業の行動に関するミステリーを、主にミクロ経済学を応用して解明しようとする学問。それがコーポレートファイナンス理論だ。
「価値とはなにか」「そもそも企業とはなんであるのか」といった根本的なところから、本書は丁寧に解きほぐしていく。
資本コストと素直な信仰

Rawpixel/gettyimages
「株式会社」という組織の現場は、緊張感と喜怒哀楽に包まれている。なにかに追われているかのように毎年利益を求め続け、組織の一員は仕事がうまくいけば、時に傲慢になり、うまくいかなければ自信を喪失する。株式会社をそうしたテンションの高い組織に駆り立てるものは「資本」という存在だ。
商売の元手となったおカネである資本が最終的に増えたかどうか、それが株式会社の成果だ。もし会社が期待されていた以上に資本を増やしたら、その分が会社によって生まれた価値として称賛される。そして、多くの資本がその会社に押し寄せ、商売を大きくできる。それが株式会社という説話原型だ。
企業が行う事業の不確実性(リスク)を、年率〇〇%と具体的な数値で表したものが資本コストである。

この続きを見るには...
残り4101/4968文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.04.22
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約