精神現象学 上
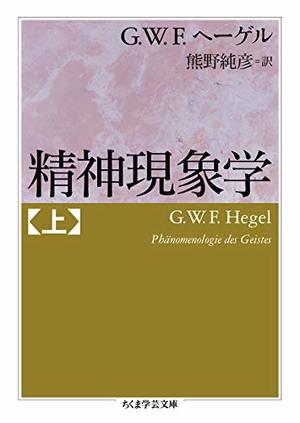
精神現象学 上
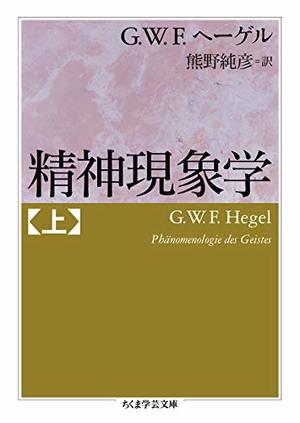
著者
G.W.F.ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
1770-1831年。近代ドイツを代表する哲学者。精神の発展過程を意識経験の学として探究し、その論理を解明したことで、ドイツ観念論の完成者と言われる。イエナ大学、ベルリン大学などで教鞭をとった。著書は他に『論理学』『法哲学』『哲学的エンチクロペディー』、講義録に『歴史哲学』『宗教哲学』『美学』等。
1770-1831年。近代ドイツを代表する哲学者。精神の発展過程を意識経験の学として探究し、その論理を解明したことで、ドイツ観念論の完成者と言われる。イエナ大学、ベルリン大学などで教鞭をとった。著書は他に『論理学』『法哲学』『哲学的エンチクロペディー』、講義録に『歴史哲学』『宗教哲学』『美学』等。
本書の要点
- 要点1一般的な学問は、個別的で具体的な知識を習得したり、偽ではなく真である正しい答えだけを扱ったりするが、哲学は個別的ではなく普遍的なもの、真だけでなく偽も含めた全体を対象とする知の体系である。
- 要点2近代の哲学は認識をテーマとして、自己と対象を切り離したが、それでは実在に関する完全な知を得ることはできない。精神が教養をつみ、理性的になって、自己と対象を全体として一つにとらえられるようになっていく過程のすべてを叙述することが、精神現象学である。
- 要点3人間は、教養を積み、意識から悟性へ、自己意識から理性へと進歩することで、世界が理性であり、理性が実在であることを知る。そうして自己と対象が一致する絶対知へと近づける。
要約
【必読ポイント!】 哲学は真理の学問となり得るか
哲学という教養
「真なるものと偽なるものとの対立は固定されている」という思い込みは、真理の認識を邪魔してしまう。ある哲学的体系に対する賛否を言挙げするだけでは、真理がしだいに発展してゆくすがたとして、哲学的体系どうしの相違をとらえることはできないだろう。花がひらくと消えるつぼみは、その開いた花弁によって否定されるのではない。両者は同時に存在し得ないが、その流動的な本性において有機的な統一がなされているのだ。つぼみと花弁はたがいに抗争することなく、一方は他方にとって必然的なものとなり、それがまさに全体の生命をかたちづくっている。
教養は、実体的な生(対立を知らない素朴な生き方)から離脱しようとすることではじまる。一般的な原則と立場に関する知識を得なければ、離脱は叶わないからだ。真理が存在する形態は学問的体系にほかならず、「知への愛」を意味する哲学は、その名を脱ぎ捨てて、現実に知となることが目指される。そのための努力に参加することが本書の目的である。哲学を学まで高めるべき時代が到来している。
私たちの時代は誕生の時代であり、精神はそれまでの時代と手を切って、自身を改造しようとしている。これまでの自分の世界が解体され、ゆっくりと進む崩壊は、日の出とともに断ち切られ、新たな世界のすがたが一閃の陽光によって一挙に照らし出されるだろう。
真なるものは現実的なもの

Nadezhda Ivanova/gettyimages
真なるものは、実体としてではなく、主体として把握し、表現されなければならない。
実体とは、存在でありながら主体でもある。「その存在が真に現実的であるのは、実体が自己自身を定立する運動であるかぎりにおいてにすぎない」。生き生きとした実体は、単純なものと、否定的なものとに分かれて対立しつつ、みずからを取り戻す。他のものであることを通して自分自身へと反省的に立ちかえることこそが、真なるものなのだ。自分自身のはじまりに終わりが含まれている円環的なものであり、はじまりを目的としてそこに立ち返ることで現実的なものになる。
真なるものは全体であり、全体とは、「みずから展開することによって完成される実在」のことである。したがってこの絶対的なものの本性は、本質的に〈結果〉として存在することにある。つまり絶対的なものとは、現実的なものであり、主体であり、自分自身へと生成してゆくものといえる。
以上から、反省(レフレクシオーン)は、さまざまな対立を廃棄(アウフヘーベン)して、真なるものを結果としてつくりだすものだ。
たとえば胎児は、〈それ自体として〉人間であるが、〈自分自身に対して〉人間であるわけではなく、教養によってみずからを形成することで理性に至ったときに人間となる。そしてその理性とは、〈それ自体として〉それであるように反省することではじめて現実的なものとなる。この生成の〈結果〉は自己意識をともなった自由として、対立するものを置き去りにすることなく、和解(フェアゼーネン)しているのだ。
つまり理性とは「合目的的なはたらき」であり、この目的とは自立的に現に存在するようになった主体にほかならない。この生成の運動こそが、自己という〈結果〉である。
真なるものが現実的となるのは、絶対的なものが「精神」であるからだ。近代では、精神的なものだけが現実的な実在であり、〈それ自体として〉存在する崇高な概念とされてきた。一方で精神的なものは、〈自分自身に対して〉も存在する。みずから他のものとかかわることで規定され、他のものとして、自分自身のうちに反省的に在り続けるのだ。これが「精神的なものは絶対的なしかたで存在する」ゆえんである。

この続きを見るには...
残り2922/4433文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.04.27
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











