「聴く」ことの力
臨床哲学試論
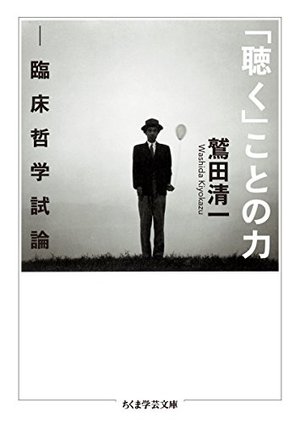
著者
鷲田清一(わしだ きよかず)
1949年、京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。大阪大学名誉教授、京都市立芸術大学名誉教授、せんだいメディアテーク館長。専門は哲学。現象学をベースに、臨床哲学、モード批評などを幅広く展開する。主な著書に『モードの迷宮』(ちくま学芸文庫、サントリー学芸賞)、『「ぐずぐず」の理由』(読売文学賞)、『「待つ」ということ』(以上、角川選書)、『〈ひと〉の現象学』(筑摩書房)、『哲学の使い方』(岩波新書)、『素手のふるまい』(朝日新聞出版)などがある。
1949年、京都市生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。大阪大学名誉教授、京都市立芸術大学名誉教授、せんだいメディアテーク館長。専門は哲学。現象学をベースに、臨床哲学、モード批評などを幅広く展開する。主な著書に『モードの迷宮』(ちくま学芸文庫、サントリー学芸賞)、『「ぐずぐず」の理由』(読売文学賞)、『「待つ」ということ』(以上、角川選書)、『〈ひと〉の現象学』(筑摩書房)、『哲学の使い方』(岩波新書)、『素手のふるまい』(朝日新聞出版)などがある。
本書の要点
- 要点1これまでのアカデミックな哲学は〈話す〉ことについてばかり論じてきた。本書では、哲学を〈臨床〉という社会のベッドサイドに置いて、「語る」ことではなく、「聴く」ことを主題とする哲学のあり方を考える。
- 要点2ひとは他者の苦しみに無関心でいられない。苦しみのなかにいるひとと共にあろうとし、そのひとの苦しみの声を祈るように待つことが、他者の力になる。
- 要点3共感不可能な苦しみのなかにあるひとに、それでもふれようとする。そうした地点でこそ、〈弱さ〉が思想にまで高められる予感がある。
要約
〈聴く〉をこととする哲学の可能性
ただ聴くということ
著者の知りあいの知りあいに、阪神・淡路大震災のあと、近くの小学校の体育館へ炊き出しに通っていた女性がいる。長らくそこに通う間、彼女は避難所で生活しているある女性と語らうようになった。
相手の女性には受験生の息子がいた。深夜の受験勉強に疲れ、一階の居間の炬燵で居眠りしていた息子を、その日は起こすのがかわいそうになってそのまま寝かせることにした。翌日未明の激震で二階は崩れ落ち、その子は階下で押し潰された。
女性はじぶんの不注意で息子が死んだのだとじぶんを責めつづけていた。そして、たまたま出会ったボランティアの女性に、このことを繰り返し語った。ボランティアの女性はただ聴くことが精一杯だったと言うが、ただ聴くということだけが、相手の爛れたこころの皮膚を、かろうじて一枚つづりになった薄膜で覆うことができた。
「わたしはもうだめなのではないでしょうか?」

whitebalance.oatt/gettyimages
この話を聞いて、著者は中川米造の『医療クリニック』に出てきた設問のことを思い出した。「わたしはもうだめなのではないでしょうか?」と言う患者のことばに対して、あなたならどう答えますかという問いである。これに対して、ほとんどの医師や医学生は「そんなこと言わないで、もっと頑張りなさいよ」と励まし、看護師と看護学生の多くは、「どうしてそんな気持になるの」と聞き返すことを選ぶ。だが、精神科の医師の多くが選んだのは、「もうだめなんだ……とそんな気がするんですね」と返すことだ。
なんの答えにもなっていないようにみえるが、精神科医の返答は「患者の言葉を確かに受け止めました」という応答だ。語る側にすれば、言葉を受けとめてもらったという、確かな出来事が起こる。本書では、〈聴く〉という、他者の言葉を受けとめる行為のもつ意味、そして〈聴く〉こととしての哲学の可能性についても考えてみたい。

この続きを見るには...
残り4179/4963文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.06.01
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











