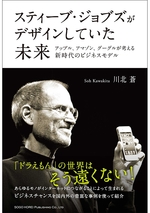スティーブ・ジョブズの王国
アップルはいかにして世界を変えたか?


著者
マイケル・モーリッツ
オックスフォード大学卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校にてMBA取得。
タイム誌の記者として活躍し、サンフランシスコ支局長を務め、数々のテクノロジー企業を取材する。その後、ベンチャー投資家に転身。
シリコンバレー屈指のベンチャーキャピタル、セコイア・キャピタルで、ヤフー、グーグル、シスコシステムズ、オラクル、エレクトロニック・アーツ、ユーチューブなどのテクノロジーベンチャーの創業および経営にたずさわる。
フォーブス誌のベンチャーキャピタリストランキング「ミダスリスト」で2006年、2007年とつづけて1位にランクイン、2008年、2009年は2位にランクインした。
イギリス、ウェールズ出身。サンフランシスコ在住。
オックスフォード大学卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校にてMBA取得。
タイム誌の記者として活躍し、サンフランシスコ支局長を務め、数々のテクノロジー企業を取材する。その後、ベンチャー投資家に転身。
シリコンバレー屈指のベンチャーキャピタル、セコイア・キャピタルで、ヤフー、グーグル、シスコシステムズ、オラクル、エレクトロニック・アーツ、ユーチューブなどのテクノロジーベンチャーの創業および経営にたずさわる。
フォーブス誌のベンチャーキャピタリストランキング「ミダスリスト」で2006年、2007年とつづけて1位にランクイン、2008年、2009年は2位にランクインした。
イギリス、ウェールズ出身。サンフランシスコ在住。
本書の要点
- 要点1アップルを創業したスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック。エレクトロニクスに熱中していた2人は、副業をするような気軽な気持ちでアップルを創業した。
- 要点2アップルは最初から順調だったわけではない。理解あるコンピュータ・ショップのオーナーや、ベンチャー・キャピタリストとの出会いが、事業拡大に大いに貢献した。
- 要点3アップルⅡの成功によってアップル・コンピュータは株式市場に上場し、それによって多くの億万長者を生み出した。一方で人材流出や、世間からの賞賛によりアップル従業員の態度が高圧的になるなどの弊害も生じてしまった。
要約
アップル誕生
2人のスティーブ
スティーブ・ジョブズとともにアップル社を設立した技術者、スティーブ・ウォズニアック。2人が出会ったのはジョブズが高校生、ウォズニアックが大学生のときのことだった。彼とジョブズは2人とも内省的で、自分だけのプライベートな世界に閉じこもりがちだったが、いたずら好きで、エレクトロニクスに熱中しているという共通点を持っていた彼らは、互いの風変わりな性格を次第に認め合うようになる。
ジョブズの青春時代

Justin Sullivan/Getty Images News/Thinkstock
1972年、ジョブズは両親を説得して莫大な授業料を支払い、オレゴン州のリード大学に入学するも、半年もすると勉強以外のものに興味を抱くようになり、学業は不振で、精神的には完全にドロップアウトしているような状態だった。
彼は直観力こそがより高い知的精神状態を形成すると信じるようになり、瞑想にふけることが多くなった。ジョブズとともに瞑想の世界に足を踏み入れていた友人がインドにいったときの土産話を聞いて、自身もインドに行きたくなったジョブズは、エレクトロニクスの会社で働けばインドにいく費用を稼げるかもしれないと考え、アタリというテレビゲームの会社を訪れた。ジョブズは薄汚い格好をしていたが、自分はヒューレット・パッカード(HP)で働いていたとほのめかして採用され、初めての会社員生活を送ることになる。
保守的な社員が多い会社のなかで、ジョブズは他のエンジニアに対して軽蔑の態度を隠そうとせず、いつも「どうしようもないまぬけども」と罵っていたらしい。こうした態度に加えて、風呂にも入らなかったジョブズの臭いに周囲が耐えかね、ジョブズは誰もいない深夜に仕事をするようになる。ジョブズはエレクトロニクスの正式な教育は受けていないにもかかわらず、めきめきと腕をあげていった。
インドから戻ったジョブズが再びアタリで働き始めると、ウォズニアックもテレビゲームに興味を持ち始める(このころ、ウォズニアックはHPで働くようになっていた)。ジョブズの上司は「テレビゲームに使われるチップの数を減らせば、ボーナスを出す」という条件をつけ、ジョブズはウォズニアックの力を借りながら、こうした課題に取り組んだ。
アップル・コンピュータ誕生

Justin SullivanGetty Images News/Thinkstock
1976年になると、ジョブズはウォズニアックに対してしきりに「プリント基板を作って売り出そう」と言ってきた。それを買えば、誰でも自分でコンピュータを組み立てられるという訳である。これは、地元のコンピュータマニアの集まりである「ホームブリュー・コンピュータ・クラブ」に参加していたとき、ウォズニアックの作った回路を用いたコンピュータが賞賛を受けていたことが大きい。
ジョブズはちゃんとした会社というよりも、友人同士で共同経営する合名会社のような形でちょっとした事業をやってみる心づもりだった。ウォズニアックがHPを辞めるとか、自身がアタリとの契約を打ち切るというつもりはなく、あくまで副業のつもりだったらしい。
ジョブズの強烈な説得力と張り合うためにウォズニアックはアタリのセールス・エンジニア、ロン・ウェインを招いた。ウェインが各自の出資額や役割分担を規定したことで、やっとウォズニアックも納得してこの事業への参加を承知した。社名は、ジョブズの食餌療法のメニューやオレゴンの田舎での生活に着想を得て、「アップル・コンピュータ」と名付けられた。
【必読ポイント!】 躍進するアップル
事業規模が10倍に
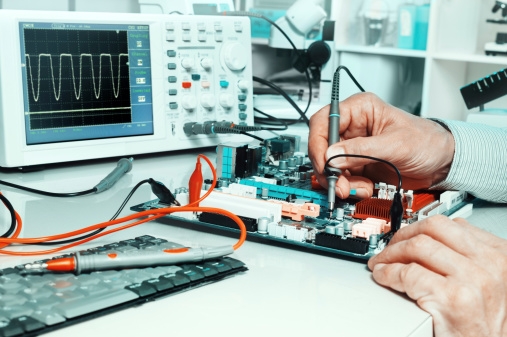
anyaivanova/iStock/Thinkstock
ジョブズはホームブリュー・コンピュータ・クラブに所属していたポール・テレルに、プリント回路基板100個分の注文を取り付けて前渡金をもらおうと、彼が運営する「バイト・ショップ」を訪れた。ジョブズはアップルの試作品を見せ、自分の計画を話した。
それに対してテレルは、むき出しのプリント回路基板ではなく、完全に組み立てられ、テストが完了したコンピュータなら買ってもいい、と答えた。しかも完成品なら50台注文してもよい、さらにその場合は現金で支払う、というのだ。
当初計画していたプリント回路基板100個分のコストは約2500ドルと想定されたが、完全に組み立てられたコンピュータ100台(テレルに納める50台と、友人やホームブリュー・クラブの会員に売るつもりの50台)ではコストが2万5000ドルとなる。テレルの申し出は、事業の規模が10倍に拡大したことを意味していた。
ウォズニアックはそのときのテレルの注文のことを回想して「あれはわが社史上最大のエピソードだった。あれほど大きな、予期しなかった出来事は、あとにも先にも一つもなかった」と語っている。
しかしながら、ジョブズが完成品を持ってきたと言ってテレルの元を訪れたとき、テレルは唖然とした。完全に組み立てられたコンピュータを持ってきてくれと言ったのに、実際にはプリント基板を12個持ってきただけだったからだ。基盤のテストすらできず、当然のことながらキーボードもテレビもついていない。プログラム言語も入っていないし、さらにケースにも入っていなかった。
このように欠点だらけで最初の要求とはまったく異なるにもかかわらず、テレルはその機械を受け取り、約束した通り現金で代金をジョブズに支払ったという。
アップル・コンピュータ設立
アップル・コンピュータはアマチュアの世界から抜け出せずにいた。マイクロコンピュータ業界はアップルを除いてどこも急速に成長していたが、当時のジョブズには事業拡張の野心を満たすだけの資金がなかったのだ。
ジョブズはアタリのトップであるノーラン・ブッシュネルに資金を手に入れるにはどこへ行ったらよいか、助言を求めた。すると彼は、冒険的事業に賭けて出資するベンチャー・キャピタリストの存在について話し、アタリの投資家の一人であるドン・バレンタインに電話をしてみてはどうか、と勧めてくれた。
バレンタインはマーケティング担当がいない会社に投資はできないと告げ、マーケティング担当としてマイク・マークラという男を紹介した。マークラはインテルの株式が上場したことで大金をつかみ、33歳という若さで既に第一線を退いていた。彼はジョブズとウォズニアックの2人に会い、アップル・コンピュータを調べて、その機械に心を奪われた。「これこそ、私がハイスクールを出たときから求めていたものだった」と。彼は1976年11月にアップルに加わるとともに、自身の個人資産からアップルに投資することを決める。こうして1977年1月3日、アップル・コンピュータは正式に法人として設立された。
アップルⅡの成功

AAA-pictures/iStock Editorial/Thinkstock
ウォズニアックはいよいよHPを退社し、アップルに注力するようになった。それまでのアップルIを再設計し、後にアップルⅡと呼ばれる機種の開発に取りかかることになる。
ジョブズの要求はいよいよ厳しくなり、ケースのデザインは様々な人物に依頼したが、どのデザインにも満足せず、より洗練されたものを探し求め続けた。それまで使っていたロゴも改められ、リンゴの片側を一口かじった(バイト)ようにすることで、ビットやバイトの世界を表現した新奇なデザインで、それでいてカラフルな親しみやすいものに変更した。プリント回路基板はアップルⅠ同様にアタリの以前の同僚に依頼したが、この同僚からは「今後二度とあんたの仕事はしない」と言わせしめるまで面倒な要求を繰り返した。
こうして出来上がったアップルⅡはカラーディスプレイ、記憶容量の拡張などさまざまな技術優位性を持っていた。1977年6月に発売されたアップルⅡは巧みな広告宣伝の効果もあり、爆発的人気を呼ぶことになる。ジョブズはさまざまな人々が協力したアップルⅡの背後でみんなの音頭をとり、励まし、後押しした。不屈のエネルギーを発揮し、ことの是非をてきぱきと判断して事業を推進したのもジョブズであった。
アップルⅡは発売されてから3年半がたった1980年9月までに販売台数13万台を記録。売上は1978年9月期の780万ドルから1億1790万ドルになった。アップルは1980年にIPO(株式公開)を果たし、ジョブズは2億ドルを超える資産を手に入れることになったほか、株やストックオプションを保有していた従業員や関係者らを多くの億万長者へと変貌させた。
ようこそ、IBM

Lightcome/iStock/Thinkstock
株式市場はアップル・コンピュータを大喝采で迎えたが、市場以外からの拍手も大きかった。アップルⅡの出現は自動車やラジオの登場に匹敵するほどの衝撃で、多くのニュースで報道された。
ただし、この時期に起こったのは良いことばかりでもない。アップルⅡは偽物が出回り、アップルからは貴重な人材が流出した。また、世間からの賞賛を受けてアップル本社で働く人々が鼻高々となり、部品納入業者や販売店との接し方や、ライバル企業などに対する態度、そして新製品開発への取り組み方など、事業活動のあらゆる面に影響を及ぼした。
結果としてアップルⅡの後継モデルであるアップルⅢはあまりに楽観的な開発スケジュールが組まれ、社内に軋轢を生じさせただけでなく、品質も低く、故障しがちであった。アップルⅢは1年後に再発売されることになったが、結局6万5000台しか売れない大失敗作となる。
さらに悪いことに、マイクロコンピュータ市場がじゅうぶんな規模になった瞬間に参入してくるだろうとだれもが予想していたIBMが、ついに1981年にパーソナル・コンピュータを発売した。
アップルⅡの方がエレガントさでまさっており、機能的でもあったが、IBMの方が良くできたキーボードを備えており、メモリ容量も大きかったようだ。アップルⅡの拡張スロットや図形処理など、一部の機能をまねた点もあった。アップルⅢを社内の力だけに頼って失敗したアップルとは異なり、大いに社外の力を利用した点も、IBMの方が優れていた。
アップルはIBMのパーソナル・コンピュータの登場に対して、心からなる喜びと、見方によれば鼻持ちならない慇懃さでもって歓迎する広告を出した。「ようこそIBM、心から歓迎します」と。ついにアップルと巨人との戦いが始まったのである。

この続きを見るには...
残り0/4100文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2014.12.05
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約