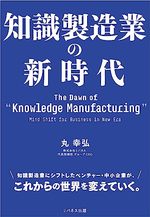日本の人的資本経営が危ない

日本の人的資本経営が危ない
著者
著者
佐々木聡(ささき さとし)
リクルートに新卒で入社後、人事考課制度、マネジメント強化、組織変革に関するコンサルテーション、HCMに関する新規事業に携わった後、ヘイ コンサルティング グループ(現:コーン・フェリー)において次世代リーダー選抜、育成やメソッド開発を中心に人材開発領域ビジネスの事業責任者を経て、2013年7月よりパーソル総合研究所執行役員コンサルティング事業本部本部長を務める。2020年4月よりシンクタンク本部上席主任研究員。立教大学大学院客員教授。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了。
主な著書に『日本的ジョブ型雇用』(共著、日本経済新聞出版)がある。
専門分野は、戦略的人的資源管理、経営リーダー育成、人材アセスメント設計・評価、ピープルアナリティクス、組織開発。
リクルートに新卒で入社後、人事考課制度、マネジメント強化、組織変革に関するコンサルテーション、HCMに関する新規事業に携わった後、ヘイ コンサルティング グループ(現:コーン・フェリー)において次世代リーダー選抜、育成やメソッド開発を中心に人材開発領域ビジネスの事業責任者を経て、2013年7月よりパーソル総合研究所執行役員コンサルティング事業本部本部長を務める。2020年4月よりシンクタンク本部上席主任研究員。立教大学大学院客員教授。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了。
主な著書に『日本的ジョブ型雇用』(共著、日本経済新聞出版)がある。
専門分野は、戦略的人的資源管理、経営リーダー育成、人材アセスメント設計・評価、ピープルアナリティクス、組織開発。
本書の要点
- 要点1社会、企業、個人の「三方良し」の精神によって自社の存在意義を問い直し、独自の企業経営を達成することで、日本の人的資本経営は世界をリードできるようになる。
- 要点2人的資本経営で最も重要なのは「経営戦略と人材戦略の連動」である。
- 要点3人的資本開示情報をまとめた統合報告書には、自社の開示ポリシーに基づき、「開示事項」と「実証性」の双方で独自性のある内容を盛り込むことで、情報開示そのものを経営戦略にしていける。
要約
人的資本とは何か
人的資本の来し方

portishead1/gettyimages
人的資本の概念の源流は、18世紀にアダム・スミスが著した『国富論』にある。アダム・スミスは「富というのは特権階級が重視する金銀を増やすことではなく、庶民にとって必要な生活の必需品を労働によって増やすことだ」とした。そのうえで、「豊かな社会を生み出すためには人材投資が重要であるという人的資本論」を展開した。
天然資源に恵まれない日本は、古くから人的資源に頼らざるを得なかった。日本の集団行動的特性は、近代化における工業製品の製造、モノづくりに活かされ、戦後高度経済成長をも導き出す。1987年に一橋大学の伊丹敬之教授が著した『人本資本企業』では、従業員を主権とする人本主義企業を、株主を主権とする「資本主義企業」の対立概念として位置づけ、世界に誇る競争力の源泉であるとした。
欧米では、1991年に雑誌『フォーチュン』にて「知的資本」という概念が登場し、財務資本ではなく頭脳こそが最も価値のある資産であるとした。こうして1990年代以降、欧米やアジアの成長国が人的資本の改革に取り組んでいった一方で、日本は逆方向に走り、先進国で唯一取り残されることになった。
日本経済の絶頂期、総量規制、公定歩合の引き上げ、地価税の導入を行い、バブル経済は一気にはじけた。1989年のベルリンの壁崩壊以降、ヒト・モノ・カネのグローバル化が進み、インターネットの普及で情報もグローバル化したが、日本ではヒトのグローバル化が大きく遅れていた。デジタル化、技術のオープン化により、海外のクラウドサービスやアプリなど、多様性の高い人材による「組み合わせ」のオープン・イノベーションが主流化し、同質性の高いヒトベースの日本の技術革新は取って代わられた。
伊丹教授は、人本主義のネガティブな側面として、環境は急速に変化しているのにヒトのしがらみにとらわれて動きが鈍くなるという「負のオーバーラン」を指摘していた。日進月歩で進化するテクノロジーを教えることのできる上司や先輩は減りつつあり、日本が得意としていたOJT形式の人材育成にも限界がきている。
こうした背景から「失われた30年」が生まれ、その状況はなお続いているのだ。
ヒトにカネをかけない日本
「ヒト、モノ、カネ、情報、時間のなかで何が最も重要な経営資源なのか」と問われれば、ヒトと答える経営者は多いだろう。しかしながら、日本企業の人材投資額は、内閣府が2010年から14年までに集計した平均で、GDP(国内総生産)比でわずか0.1%である。その額は約5000億円と、米国の約60分の1だ。人口比率を考慮しても無視できないほど大きい。
人への投資は、持続させないとすぐに陳腐化するが、人的資本投資額は主要国の中で最低レベルだ。GDPに占める無形資産投資額の国際比較において、ソフトウェアや研究開発投資などでは、他の先進諸国と同水準なのにもかかわらず、である。
日本の経営者は主に2つの理由で、人材投資に消極的になった。1つは「教育訓練費が財務会計上で費用として計上されること」だ。業績悪化が続く企業がメインバンクや株主に説明を求められたとき、「費用」として計上されることによる短期的な資本効率の低下を避けようとする。

この続きを見るには...
残り3318/4648文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.10.26
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約