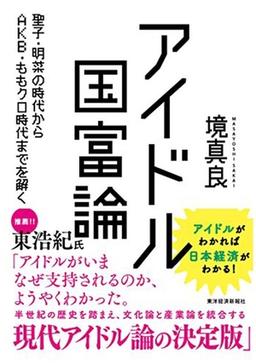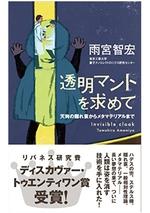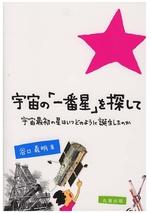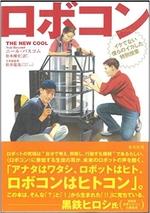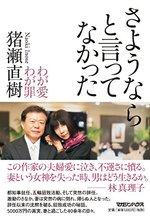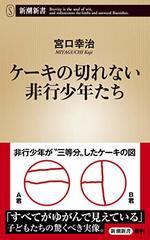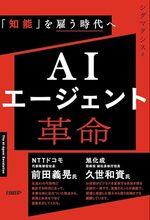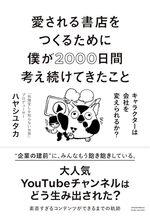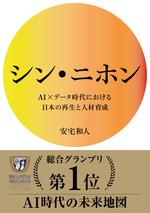80年代アイドルの趨勢
アイドルの発生
映像メディアの主役が、映画からテレビへ交替することで、アイドルが誕生した。「アイドル」の定義は、「若くて、歌手で、メディアミックス的に活動し、目の覚めるような美貌や声や演技力には恵まれてない非実力派」というものである。映画時代の「スター」とテレビ発の「アイドル」を隔てたのは「非実力派である」という一点に集約される。
アイドルの皮切りは南沙織をはじめとする「新三人娘」であった。「花の中三トリオ」、とりわけ山口百恵は国民的アイドルとなり、アイドルのプロトタイプを確立していく。
キャンディーズやピンクレディーといったグループアイドルを生み出しながら、アイドルの爛熟期と呼べる80年代に突入した。アイドルの王道と言える松田聖子や、その筆頭ライバルである中森明菜が登場する。息の長いタレントを多数輩出した「花の82年組」の頃には、小泉今日子が「なんてったってアイドル」でアイドルの生活を戯画的に歌い上げ、アイドルが演じられる時代になっていく。
「アイドル」のビジネスモデル
コンテンツ制作量が急増したテレビや雑誌の世界で、顧客吸引力があるタレントとしてアイドルの存在が必要になった。アイドルの大量生産には、次の2つの仕組みが奏功した。
1)芸能プロダクションが専属的にアイドルを売り出していくという独自のビジネスモデルが誕生したこと
2)テレビや雑誌、映画などのメディアミックス戦略によって「どこかで儲かる」状態をつくったこと
こうしてアイドルが繁栄する一方で、鋭い「アイドル批判」も育っていった。それは「歌が上手くないのに人気があるアイドル歌手を歌手として認めたくない」というアーティスト魂からの告発である。実際、「アイドルはニセモノ」という「やましさ」は音楽業界自体にあったようだ。
そんな中、「アイドルの卵」を消費者に提供して、彼ら自身の創造力でアイドルを作ってもらうという発想が芽生えた。それをいち早く取り入れた秋元康は、20名以上のメンバーが歌う「おニャン子クラブ」という壮大な社会実験を始める。「卒業」システムやソロデビュー、派生ユニットなどの仕組みを導入し、アイドル界のドラマツルギーを可視化したと言える。しかし、その活動はたった2年半弱で幕を閉じた。80年代終わりには、日本の経済成長の申し子である「アイドル」は、バブル経済の頂点に達した時にかき消えてしまい、「アイコン」の座を追われてしまったのだ。
アイドルの消費論
マッチョ主義とヘタレ主義
そもそも、日本人が非実力派のアイドルを好むのはなぜか。まず、アイドルの形態的特徴は「かわいい」だ。これは、完全性を志向する「美しい」と対比して、「アンバランス」・「子どもっぽい」など、不完全なものという意味をもち、「触れたい・庇護してあげたい」という欲求を引き起こす。つまりそれは「支配したい」という欲求と同義であり、対象を自分より劣等な存在と見なすことにも通じている。
この言説に異を唱えたくなるとしたら、それは「劣等な存在を選んではいけない。素晴らしい異性に挑戦すべきだ」という規範を認めている証拠だと言える。