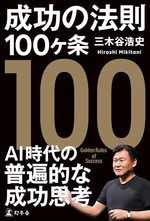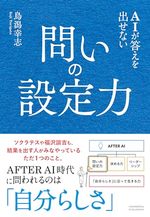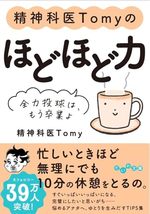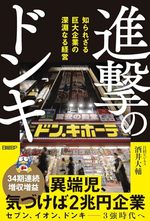報道、トヨタで学んだ伝えるために大切なこと
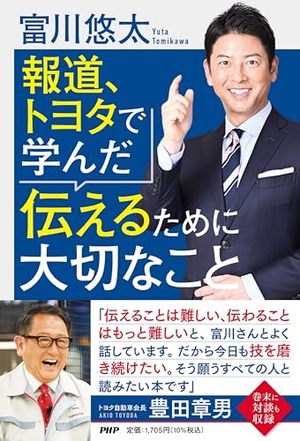
報道、トヨタで学んだ伝えるために大切なこと
著者
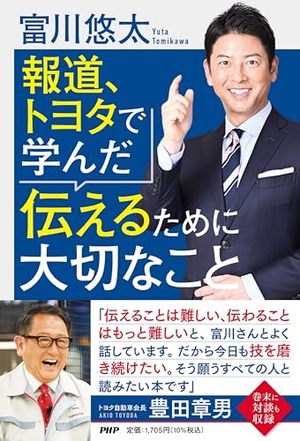
著者
富川悠太(とみかわ ゆうた)
トヨタ自動車のオウンドメディア「トヨタイムズニュース」キャスター。「トヨタイムズ」では、外部への発信のみならず、約38万人の社員(連結子会社含む)に、豊田章男会長の思いを伝えることを目的としている。1976年、愛知県名古屋市生まれ。東京都立国立高等学校、横浜国立大学教育学部小学校教員養成課程体育専攻を卒業。1999年4 月、テレビ朝日に入社。2014年12月には、同年8月に筋萎縮性側索硬化症(ALS)で亡くなったいとこの富川睦美さんを取り上げた『笑顔の約束~難病ALSを生きる~』に出演。同番組は2015年11 月に日本民間放送連盟のテレビ教養番組部門で優秀賞を受賞。2016年4 月11日に古舘伊知郎氏の後任として『報道ステーション』のメインキャスターに就任。2022年3月末、テレビ朝日を退社。同年4月1 日、トヨタ自動車に入社。同年12 月、「トヨタイムズニュース」キャスター就任。プロデューサーも務め、「先人たちの想い」や「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」、「マルチパスウェイで目指す脱炭素社会」など、トヨタの「過去・現在・未来」を伝えている。
トヨタイムズ(toyotatimes.jp)
トヨタ自動車のオウンドメディア「トヨタイムズニュース」キャスター。「トヨタイムズ」では、外部への発信のみならず、約38万人の社員(連結子会社含む)に、豊田章男会長の思いを伝えることを目的としている。1976年、愛知県名古屋市生まれ。東京都立国立高等学校、横浜国立大学教育学部小学校教員養成課程体育専攻を卒業。1999年4 月、テレビ朝日に入社。2014年12月には、同年8月に筋萎縮性側索硬化症(ALS)で亡くなったいとこの富川睦美さんを取り上げた『笑顔の約束~難病ALSを生きる~』に出演。同番組は2015年11 月に日本民間放送連盟のテレビ教養番組部門で優秀賞を受賞。2016年4 月11日に古舘伊知郎氏の後任として『報道ステーション』のメインキャスターに就任。2022年3月末、テレビ朝日を退社。同年4月1 日、トヨタ自動車に入社。同年12 月、「トヨタイムズニュース」キャスター就任。プロデューサーも務め、「先人たちの想い」や「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」、「マルチパスウェイで目指す脱炭素社会」など、トヨタの「過去・現在・未来」を伝えている。
トヨタイムズ(toyotatimes.jp)
本書の要点
- 要点1「相手の視点に立つ」ことと「第三者的視点で自分を見る」ことで、本当に伝わりやすい表現ができているかどうかがわかる。
- 要点2相手の目線で、役に立てることを探しているうちに、相手は心の扉を開いてくれる。
- 要点3言葉の力を磨くには、良い言葉に向き合い、言葉のストックを増やすことが大事だ。
- 要点4相手を巻き込む必要があるときは、相手にも関係する「大きな目的」を伝えるとよい。
要約
相手の視点に立った聞き方・話し方
伝わる話し方と、聞き取りやすい話し方は違う
伝わる話し方とはどのようなものか。著者は、「相手の視点に立つ」ことと「第三者的視点で自分を見る」ことで、本当に伝わりやすい表現ができているかがわかるという。
ハキハキと流ちょうに話せば伝わりやすいと思うかもしれない。だが、「聞き取りやすい」と「伝わりやすい」は違う。聞き取りやすい話し方に意識を向けすぎると、かえって聞き手の印象に残りにくいこともある。それは、聞き手が自分ごととして思えず、臨場感を持てないからだろう。
大事なのは、話し方より「視点」を意識することだ。まず、取材の際など「現場と一体化する」とき、自分の視点は現場の視点になる。現場で起きた事件、災害などの当事者に近い視点で物事を見る。つづいて、視聴者の視点になり、視聴者が「知りたいこと」をもとに伝え方を考える。そのうえで、実際に伝える際には、現場と自分と視聴者とを含めた全体を見る視点に立ってみる。現場中継なら、現場で自分が話す様子を離れた場所から見るようなイメージだ。
話し手が話の内容に入り込むと、現場のニュースが話し手にとっての自分ごとになる。そのため、説得力のある「自分の言葉」で話せるようになり、結果的に相手に伝わりやすくなるのだ。
「上がり込みの達人」といわれるまでに

Mihajlo Maricic/gettyimages
人気報道番組のリポーターになった著者は、事件や事故の現場に行って取材をすることになった。当初は土足で上がり込むような気がして、インタビューをするのは気が重かったという。
それが変化したのは、2004年の新潟県中越地震のときだ。現地へ赴いた著者の前には惨状が広がっていた。建物は倒壊し、土砂崩れも起きて、家に帰れない人がたくさんいる。著者は、取材よりもお手伝いが先だと思い、瓦礫の片づけを手伝った。すると、一緒に作業をしている現地の人が、自然と話してくれた。相手の立場に立って役に立つことを探し、一緒に作業する中で自然に出てくるものを拾う。こうした取材の仕方のほうが、質問して答えてもらおうとするより、はるかにリアルな話を聞けたのだ。

この続きを見るには...
残り3160/4032文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.09.03
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約