頭のいい説明「すぐできる」コツ
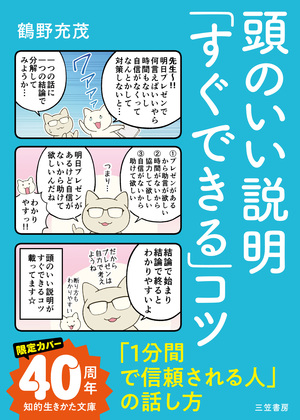
頭のいい説明「すぐできる」コツ
著者
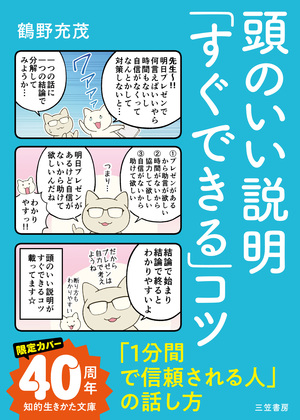
著者
鶴野充茂(つるの みつしげ)
1972年大阪府生まれ。筑波大学(心理学)、米国・コロンビア大学大学院(国際広報)卒業。その後、在英国日本大使館、国連機関、ソニー等を経て独立。一貫して「コミュニケーション」をテーマに幅広い経験を積む。
現在は、コミュニケーション教育事業・ビーンスター(株)の代表、自己演出プロデューサーとして、ビジネスマンに効果的なコミュニケーション技術を提供。主著に、ベストセラーになった『図解 頭のいい説明「すぐできる」コツ』『まんがでわかる! 頭のいい説明「すぐできる」コツ』の他、『あたりまえだけどなかなかできない説明のルール』(明日香出版社)などがある。
会社のサイト https://beanstar.net/
個人公式サイト http://tsuruno.net
お問い合わせ info@beanstar.net
1972年大阪府生まれ。筑波大学(心理学)、米国・コロンビア大学大学院(国際広報)卒業。その後、在英国日本大使館、国連機関、ソニー等を経て独立。一貫して「コミュニケーション」をテーマに幅広い経験を積む。
現在は、コミュニケーション教育事業・ビーンスター(株)の代表、自己演出プロデューサーとして、ビジネスマンに効果的なコミュニケーション技術を提供。主著に、ベストセラーになった『図解 頭のいい説明「すぐできる」コツ』『まんがでわかる! 頭のいい説明「すぐできる」コツ』の他、『あたりまえだけどなかなかできない説明のルール』(明日香出版社)などがある。
会社のサイト https://beanstar.net/
個人公式サイト http://tsuruno.net
お問い合わせ info@beanstar.net
本書の要点
- 要点1ビジネスにおける説明の目的は「仕事で結果を出すこと」だ。この目的意識の有無で、説明の効果は大きく変わる。
- 要点2「話を聞こうという心の準備」ができていないときに情報を提供されても、聞き手はなかなか理解できない。説明の最初に話の種類を伝えつつ、聞き手と歩調を合わせる話し方をして、相手に心の準備をさせよう。
- 要点3メールでの報告は、リマインド言葉→現在地→方向性の三段構成にすると伝わりやすい。
要約
【必読ポイント!】 「頭のいい説明」の基本ルール
説明の目的は「仕事で結果を出すこと」
ビジネスにおける説明の目的は「仕事で結果を出すこと」であって、相手にわかりやすく伝えることでも、正確に伝えることでも、問題が起こらないようにすることでも、情報を自分のところだけで止めておかないことでもない。この「目的意識の差」が、「説明の効果の差」としてはっきりと表われる。
ビジネスにおける説明の目的は「仕事で結果を出すこと」。この定義のもとでは、説明の効果は大きく三段階に分割できる。
第一段階は、「伝える」という段階。話し手が聞き手に情報を一方的に渡した状態であり、相手に話が伝わったかどうかはわからない。
第二段階は、「伝わる」という段階。話し手が伝えた情報を聞き手が理解した状態だ。だが、まだ相手は行動を起こしておらず、「仕事で結果を出すこと」には至っていない。
第三段階は、「結果が出る」段階だ。仕事を進めたい、相手に協力してもらいたいなど、話し手が説明によって意図する行動が実現した状態である。
相手が聞きやすい順で話す

b-bee/gettyimages
ビジネスにおける説明の基本は、自分が思いついた順番ではなく、聞き手が聞きやすいと感じる順番で話すことだ。
わかりやすい例を紹介しよう。著者があるホテルで「この時期は、お客さんは多いのですか? 今日は混んでいますか?」と聞くと、スタッフは「今日の予約は100部屋くらいですね。8割程度でしょうか」と答えた。予備知識のない著者は、この答えでは混んでいるのかどうかわからなかった。
説明においては、「大きな情報」→「小さな情報」の順で話すのがもっとも聞きやすい。先ほどの例であれば、まずは「混んでいるか否か?」「混んでいるとしたら、普段と比べてどれくらい混んでいるか?」という問いに「比較的混んでいます」などと「大きな情報」を提供する。そのうえで「今日の予約は100部屋」「8割」といった「小さな情報」を与える。まとめると、次のようなイメージだ。
「比較的混んでいます。当ホテルの平均稼働率は約7割ですが、今日は8割程度です。ちなみに客室は125部屋で、100組ほどのお客さまが泊まっていらっしゃいます」
相手に「心の準備」をさせる

g-stockstudio/gettyimages
「話を聞こうという心の準備」ができていないときに情報を提供されても、なかなか理解できないものだ。ここでは、相手に「心の準備」をしてもらうコツを2つ紹介しよう。

この続きを見るには...
残り3647/4639文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.02.03
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











