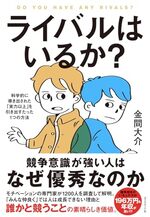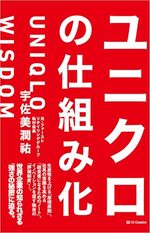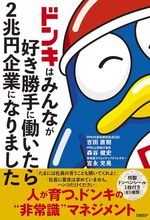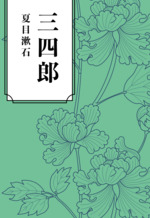社会分業論

社会分業論

著者
エミール・デュルケーム(Émile Durkheim)
1858-1917年。フランスの社会学者。コントに始まる社会学を近代的な学問として確立した。ヴェーバーの歴史主義的方向性に対して、自然主義的アプローチで知られる。ボルドー大学で教鞭をとり、『社会分業論』や『社会学的方法の規準』、『自殺論』を執筆。のちにソルボンヌ大学に転じ、『宗教生活の基本形態』や『道徳教育論』などを著す。その研究成果は宗教学や人類学をはじめ多様な学問分野に広く影響を与えた。
1858-1917年。フランスの社会学者。コントに始まる社会学を近代的な学問として確立した。ヴェーバーの歴史主義的方向性に対して、自然主義的アプローチで知られる。ボルドー大学で教鞭をとり、『社会分業論』や『社会学的方法の規準』、『自殺論』を執筆。のちにソルボンヌ大学に転じ、『宗教生活の基本形態』や『道徳教育論』などを著す。その研究成果は宗教学や人類学をはじめ多様な学問分野に広く影響を与えた。
本書の要点
- 要点1分業は個人がそれぞれの利益を増やそうとして進むのではなく、互いに補いあうために進展し、社会に連帯を生み出す。
- 要点2古い時代の血縁共同体的な連帯は機械的であり、分業がもたらす連帯は高等な生物の器官が連携するような有機的な連帯である。
- 要点3分業は恐慌と倒産の増加、資本家と労働者の対立をもたらすこともあるが、これは分業が正常とは異なる病的な状態にあるためだ。
要約
【必読ポイント!】 分業は社会の連帯をもたらす
分業の問題

AndreyPopov/gettyimages
古代からあったそれを初めて理論化し、分業という言葉に収斂させたのは18世紀の経済学者アダム・スミスだ。いまや、この分業の進展は誰の目にも明らかである。産業は資本と様々な力を集積させると同時に、それぞれの仕事を分割し、専門化させている。それは、ある一つの工場の内部だけで起きていることではない。そもそも、それぞれの工場自体が、他の工場との分業を前提としている。
分業は意図的というよりも、自生的に実現されており、経済の領域だけでなく、政治、行政、司法や、芸術や科学においても進んでいる。また、より高等な動物ほどそれぞれの機能を専門分化させているように、生物学でも生命の有機体における分業が一般的な現象であるとされている。「生命の到来とほとんど同時期に分業がはじまる」というほどにその領域は拡大し、人間の知性と意志による社会的な分業は、その特殊な一形態にすぎないという流れの中にあるのだ。
人間はこの事実に対して、一つの完全無欠な全体を求めるのか、全体の一部の器官にとどまるのか、どちらの方向を望むべきなのだろうか。もし、分業が自然の一法則であると同時に道徳的な準則でもあり得るならば、その理由を知りたい。
この問題を考えるために、本書では次の3点が主に考察される。まず、分業の機能とはどのようなものであり、分業とはどのような社会的要求に応えるものであるのかを考える。それにより、分業を決定づける諸原因と諸条件についても見ることができる。そして、生物における病理学的なものと同様に、分業の異常形態を知ることで正常状態との区別を試みる。
そのためにも、分業を観念的なものではなく客観的事実として扱わなくてはならない。それを観察、比較することで、感覚的なものとは異なる理解を得られるはずだ。
分業の機能
機能とはここでは、生命の運動と有機体の様々な要求との間の対応関係を指す。分業の機能とは何かを考えることで、分業がどのような要求に応えているかを探れるようになる。

この続きを見るには...
残り3410/4260文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.02.08
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約