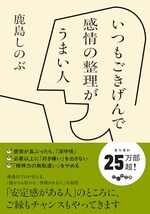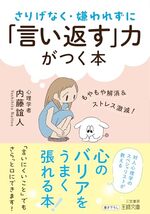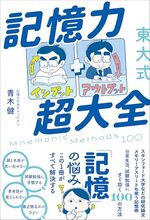なぜか好かれる「人前での話し方」
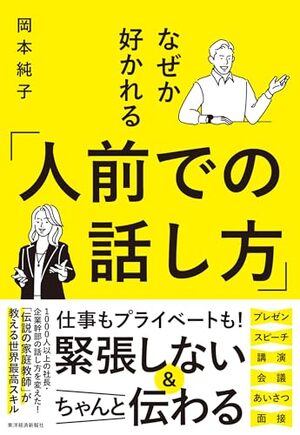
なぜか好かれる「人前での話し方」
著者
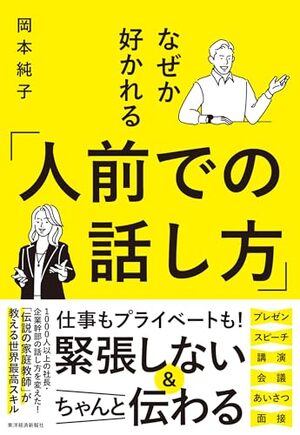
著者
岡本純子(おかもと じゅんこ)
コミュニケーション戦略研究家/エグゼクティブ・スピーチコーチ/株式会社グローコム代表取締役社長
「世界最高の話し方」を教える「伝説の家庭教師」。
もともと自信がなく、人見知りだった自分を変えようと、米ニューヨークでコミュニケーションの科学的知見やトレーニングメソッドを学び、独自のコミュ力改造メソッドを確立。日本を代表する大企業や外資系のリーダー、官僚・政治家など、1000人を超えるトップエリートの家庭教師として、プレゼン・スピーチ等のプライベートコーチングに携わる。
著書に、シリーズ累計20万部を突破した『世界最高の話し方』『世界最高の雑談力』『世界最高の伝え方』(いずれも東洋経済新報社)など。
「今年の顔100人」として「2021 Forbes JAPAN 100』に選出。2022年5月に、次世代リーダー向けの「世界最高の話し方の学校」を設立。早稲田大学政治経済学部卒業。英ケンブリッジ大学院国際関係学修士。米MIT比較メディア学元客員研究員。読売新聞経済部記者などを経て現職。
コミュニケーション戦略研究家/エグゼクティブ・スピーチコーチ/株式会社グローコム代表取締役社長
「世界最高の話し方」を教える「伝説の家庭教師」。
もともと自信がなく、人見知りだった自分を変えようと、米ニューヨークでコミュニケーションの科学的知見やトレーニングメソッドを学び、独自のコミュ力改造メソッドを確立。日本を代表する大企業や外資系のリーダー、官僚・政治家など、1000人を超えるトップエリートの家庭教師として、プレゼン・スピーチ等のプライベートコーチングに携わる。
著書に、シリーズ累計20万部を突破した『世界最高の話し方』『世界最高の雑談力』『世界最高の伝え方』(いずれも東洋経済新報社)など。
「今年の顔100人」として「2021 Forbes JAPAN 100』に選出。2022年5月に、次世代リーダー向けの「世界最高の話し方の学校」を設立。早稲田大学政治経済学部卒業。英ケンブリッジ大学院国際関係学修士。米MIT比較メディア学元客員研究員。読売新聞経済部記者などを経て現職。
本書の要点
- 要点1人の印象は「何を話すか」より「どう話すか」で決まる。話し方のポイントは声、目、手の3要素にある。中でも声はメリハリが9割だ。
- 要点2人前で話す際に緊張をほぐすには、「ドッジボールからキャッチボールへ」を意識するとよい。
- 要点3話す内容を組み立てる際は、キーメッセージを中心に据えて、「OREO話法」などを活用すると説得力を高められる。
要約
人は「どう話すのか」で決まる
「何を話すのか」より「どう話すのか」
人前での話し方は、「どう話すのか」(デリバリー)と「何を話すのか」(コンテンツ)の2つで決まる。コミュニケーションで決定的な役割を果たすのは前者だ。
人の身体からは、「ソーシャルキュー」と呼ばれる無数の信号が発信されている。「何を話すのか」はコミュニケーションの本質である。だが、相手の心証を形成する際には、ジェスチャーや姿勢、アイコンタクトなど言葉以外の情報のほうが、インパクトが強い。
堂々と人前で話すためのボディーランゲージのポイントは、声と目と手の3つである。ここでは声についてのポイントを紹介する。
そもそも、声が大きい=聞き取りやすいというわけではない。話すスピードに関しては、一般的にはテンポのよいスピードを著者はすすめている。現在は、多くの人が倍速でYouTubeやNetflixを視聴する時代だ。同じ時間で多くの内容を聞くことを好む「タイパ志向」の人が増えている。現にあまりにゆっくり話を聞かされると、脳が飽きてしまう。
こうした背景から、最近はスピード感を持って話す人の方が頭の回転が速く説得力があると見られる傾向にある。まくし立てるように話すのではなく、相手を飽きさせないスピード感を意識したい。
声はメリハリが9割

sanjeri/gettyimages
ポイントは、スピード、高さ、大きさ、抑揚、間を工夫して、いかに声にメリハリをつけるかである。例えば、声の高さによって、相手に与える印象を変えることができる。高い声は親しみやすさを、低い声は威厳や力強さを表す。与えたい印象によって、声の高低をコントロールできれば上級者だ。

この続きを見るには...
残り3610/4291文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.03.03
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約