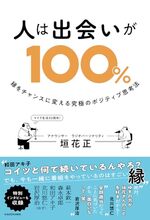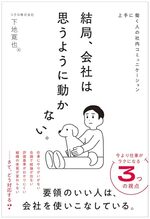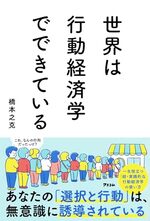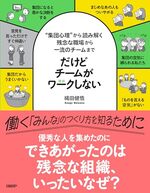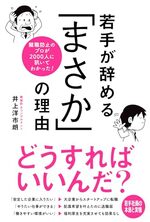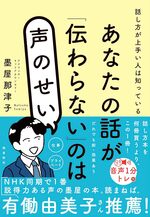仕事も対人関係も 落ち着けば、うまくいく

仕事も対人関係も 落ち着けば、うまくいく
著者
著者
和田秀樹(わだ ひでき)
1960年大阪府生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は精神科医。和田秀樹こころと体のクリニック院長。立命館大学生命科学部特任教授。一橋大学非常勤講師。川崎幸病院精神科顧問。
著書に『感情的にならない本』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』『なぜか人生がうまくいく「優しい人」の科学』など多数。
1960年大阪府生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て、現在は精神科医。和田秀樹こころと体のクリニック院長。立命館大学生命科学部特任教授。一橋大学非常勤講師。川崎幸病院精神科顧問。
著書に『感情的にならない本』『70歳が老化の分かれ道』『80歳の壁』『なぜか人生がうまくいく「明るい人」の科学』『なぜか人生がうまくいく「優しい人」の科学』など多数。
本書の要点
- 要点1みんなに好かれようとしたり、人目を気にしたりすることが緊張や不安につながる。周囲の人は思った以上に自分を見ていないものだ。
- 要点2感情に振り回されない自分を作るために、不安の原因となる固定観念を打ち破ろう。
- 要点3うまくいっている人は、自分にとって重要なものにエネルギーを全集中している。割り切って自分の行動スタイルを決めよう。
要約
現代を取り巻く「悪い緊張」
緊張しやすい人の5つの特徴
日常的に起こる緊張には、「いい緊張」と「悪い緊張」がある。いい緊張とは、新しい挑戦やチャンスに直面したときの感情の変化で、集中力や判断力を高め、意欲を刺激し、パフォーマンスを向上させる。
一方、悪い緊張は、過度の心配や不安などから生じ、思考力や判断力を鈍らせ、パフォーマンスを低下させる。重要なのは緊張それ自体ではなく、緊張の原因を見極め、それに応じた対策を考えることである。
他の人と比べて緊張しやすい人には、次のような5つの特徴がある。
まず、真面目で責任感が強い人だ。一人で責任を抱え込みやすく、失敗できないというプレッシャーを自分にかけてしまう。
次に、完璧主義で自分のミスが許せない人だ。自分の些細なミスも許せず、イメージ通りに物ごとが進まないとイライラしてしまう。
そして、ネガティブ思考の人だ。最悪のケースばかりを想像してしまい、失敗するのではと不安になるところから緊張が始まる。
4つめは、周囲の評価を気にしがちな人だ。自己肯定感が低く、大勢の人を前にすると「自分はどう思われるのか」と考え、自らを追い込んでしまう。
最後に、人と会話をするのが苦手な人だ。会話自体にストレスを感じ、「うまく話せるか」と考えるうちに、何を話しているのか自分でもわからなくなってしまう。
緊張を生む「コミュ力」

Yutthana Gaetgeaw/gettyimages
HSP(Highly Sensitive Person)の人は緊張しやすいと言われている。この概念を提唱した米国の心理学者、エレイン・アーロン博士によると、15~20%の人はHSPの気質を持っているという。小さな音や匂いに敏感で、他人の感情に影響を受けやすく、些細なことでも深く考えてしまう。そうした感受性の豊かさが過緊張につながるのだ。
また、現代の日本では、周囲に合わせられるという意味でのコミュニケーション能力が重視される。自分の意見を伝えるよりも、相手の考えに寄り添うことが求められるため、ストレスが溜まりやすく、不安を感じることも増える。こうした状況が、「緊張や焦りを生む大きな原因」になっている。
いつもどおりの落ち着いた自分、平常心でいるために、まずは不安な気持ちになる「心の仕組み」を見てみよう。
【必読ポイント】 緊張の「仕組み」を知る
不安を生む思考習慣
平常心を保てない原因は、周囲の人ではなく、多くの場合、自分の考え方にある。本書にはそのメカニズムがいくつか紹介されているが、ここでは2つピックアップしよう。まずは思考習慣だ。

この続きを見るには...
残り3052/4094文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.13
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約