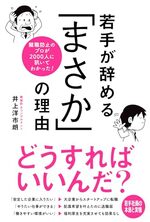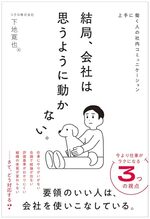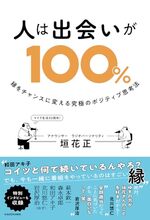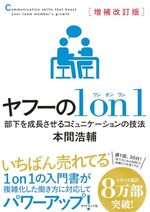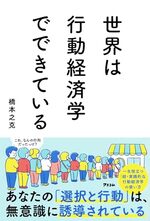“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで
だけどチームがワークしない
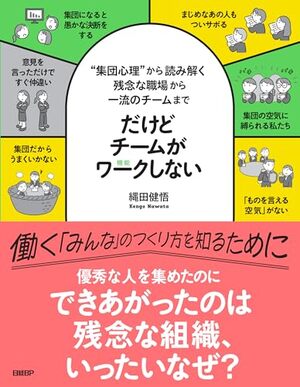
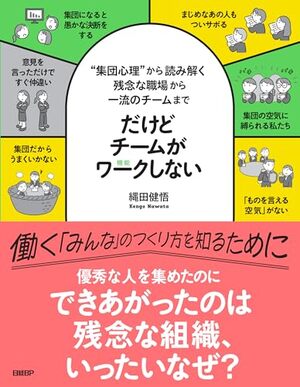
著者
縄田健悟(なわた けんご)
福岡大学人文学部准教授。
専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。
集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。山口県山陽小野田市出身。九州大学大学院人間環境学府博士後期課程修了。博士(心理学)。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)などがある。
福岡大学人文学部准教授。
専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。
集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。山口県山陽小野田市出身。九州大学大学院人間環境学府博士後期課程修了。博士(心理学)。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)などがある。
本書の要点
- 要点1組織とは人の集まり、「集団」だ。集団だから出せる成果もあるが、集団で働くからこそ生まれる問題もある。賢い人たちが集まっているのに、判断を誤ってしまうのもその1つである。
- 要点2チームがワーク(機能)するためには「目標の共有」「相互協力」「役割分担」「成員性」の4つの要素が必要だ。
- 要点3チームワークの土台となるのは「リーダーによるリーダーシップ」だ。これが安定しなければ、チームは機能しない。
- 要点4リーダーシップは「行動」で捉えよう。日常的には「課題」と「対人」を回していき、長期的には「変革型」を取り入れるとよい。
要約
【必読ポイント!】「集団」だからうまくいかない
なぜ「集団」で働くと問題が生まれるのか
組織とは人の集まり、つまり「集団」だ。人は日々、会社や組織、あるいは学校や友達グループなど、集団の中で過ごしている。その恩恵の最も大きなもののひとつは、ひとりではできない仕事ができることだ。集団で力を合わせて協力することで、より大きな成果を生み出すことができ、また困ったときには仲間から助けてもらうこともできる。
一方で、集団ならではの短所を経験したことがある人も多いはずだ。「会議で誰も本音を言えず、正しくない結論に決まってしまう」「他人任せでまじめに働いていない人がいる」「話し合いは盛り上がったのに、大したアイデアが出ない」「チームがうまく連携できず、仕事がいつも止まり気味」――。こうした問題は、ひとりで働いていては出てこない、みんなで一緒に働くからこそ生まれてくる問題だといえる。
こうした問題の背景には、群れをなして暮らすという私たち人間が持つ“集団心理”の特性が深く関わっている。ひとつひとつの組織はさまざまであっても、その根源には集団心理と、そこから生じる集団の課題がある。
こうした問題を解決しようと研究されてきたのが、社会心理学や産業・組織心理学といった分野である。こうした分野の知見を用いることで、集団がどのように機能しているのかをよりよく理解することができる。
「優秀な人たち」が愚かな判断をしてしまう理由

Getty Images/gettyimages
賢い人が集まっているのに、ばかげた結論を出してしまう――。これは集団心理のひとつ、「集団浅慮」という現象だ。
集団浅慮とは、集団のまとまりを追求するあまり、非合理で未熟な意思決定をしてしまう状態を指す。優れた人たちが集まっていても、集団になると浅はかな考えにとらわれてしまうことは少なくない。
その例のひとつに、1986年に起こったスペースシャトル「チャレンジャー号」の爆発事故がある。チャレンジャー号は、打ち上げ後わずか73秒で爆発し、乗組員全員が犠牲になった。

この続きを見るには...
残り3721/4555文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.17
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約