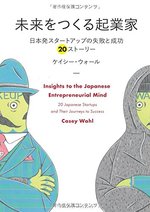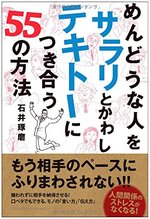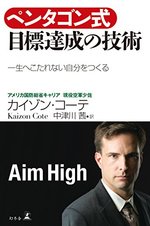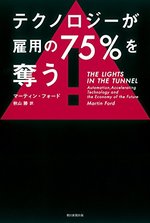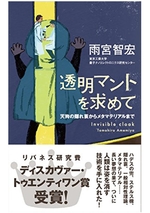マイクロソフトを辞めて、オフィスのない会社で働いてみた
「リモートオフィス」で仕事の未来を考える。
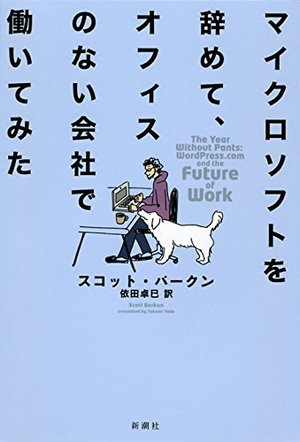
著者
スコット・バークン
マイクロソフトの元マネジャーで、経営コンサルトとして、すでに著作も4冊ある。トラフィックの多さで全世界15位以内に入るブログ・サービス〈ワードプレス・ドットコム〉にコンサルティングをおこない、同社の創始者のマット・マレンウェッグと知り合った縁で、その運営会社である〈オートマティック〉のチームリーダーに就任する。
マイクロソフトの元マネジャーで、経営コンサルトとして、すでに著作も4冊ある。トラフィックの多さで全世界15位以内に入るブログ・サービス〈ワードプレス・ドットコム〉にコンサルティングをおこない、同社の創始者のマット・マレンウェッグと知り合った縁で、その運営会社である〈オートマティック〉のチームリーダーに就任する。
本書の要点
- 要点1オートマティックでは、ブログやチャットを活用したリモートオフィスを採用しており、勤務場所の制約がないため、世界最高レベルの人材を、居住地に関係なく雇うことができている。
- 要点2オートマティックでは、仕事の質と社員のやる気を維持するために、業務の処理件数やかかった時間の統計をとり、社員がお互いの数値を見ることができるような監視体制が敷かれている。
- 要点3リモートオフィスには弊害もあり、オートマティックの社員は手掛ける仕事を自分で選べる自由を享受する一方で、大きな、面倒くさいプロジェクトを避ける傾向がある。
要約
【必読ポイント!】 リモートオフィスで働くこととは?
マイクロソフトを辞めて、オートマティックに参画

inbj/iStock Editorial/Thinkstock
世界全体のウェブサイトのほぼ20%で使われているブログ用ソフトウェアの「ワードプレス」。このワードプレスを運営する「オートマティック」社の文化は従来の企業とはまったく異なり、社員は若く、独立心旺盛で、世界の好きな場所で働いている。電子メールはめったに使わず、毎日のように新しい仕事の成果を世に出し、休暇も自由にとる方針だ。
物理的な拠点にこだわらないという当社の姿勢は会社が創設された2005年から貫かれており、以降オートマティックは完全なフラットな組織で、全従業員が直接、創業者兼CEOのマット・マレンウェッグに報告する体制が敷かれていた。その後、2010年に社内の混乱を収めるため、50人の社員を10チームに分け、各チームにひとりのリーダーを置くという決断を下す。
本書の著者であるスコット・バークンは、オートマティックに対してコンサルティングを行い、その際にフラットな組織からチーム制に移行すべきだ、という提案を行っていた背景から、この実行に自ら携わるべく、社外から呼び込まれた人物だ。本書は、マイクロソフトを辞め、コンサルタントとして働いたあと、オートマティックに参画し、チームリーダーとして働いたスコットが、リモートオフィスの実態を描いた「参加型ジャーナリズム」である。
世界最高レベルの人材を雇うことができる
多くの人にとってリモート環境で働くということ自体がピンと来ないかもしれない。しかし、通常の職場でも、コンピュータだけを使って働く時間はどのくらいあるだろうか。同僚とのやりとりの50%がメールやブラウザーなどを使ってオンラインでおこなわれているのであれば、オートマティックの実態とかけ離れていない。違う点は、オートマティックの仕事が主に(ときには完全に)オンラインであることだけだ。
オートマティックで働くメンバーは、職場の同僚ではあるものの、いっしょに集まる機会は1年に数回程度で、ほとんどの時間はおのおのオンラインで働いていた。著者であるスコットがリーダーを務める「チーム・ソーシャル」の面々は、それぞれシアトル出身、ロサンジェルス出身、サンフランシスコ在住、そしてカナダとアイルランドで交互に暮らしているメンバーだ。
勤務場所の制約がないため、オートマティックは世界最高レベルの人材を、居住地に関係なく雇うことができる。「チーム・ソーシャル」は高いプログラミングの技術を持ったメンバーで構成され、スコット以外の誰がリーダーを務めたとしても、若くて力強い、自信にあふれたクリエイティブなチームになっただろう。
社員同士の競争を促す監視体制

simonkr/iStock/Thinkstock
オートマティックには正式な面接がない。その代わりに「トライアル期間」が設けられ、期間中は本物のツールを使って現実の仕事を行う。トライアル期間をうまくこなせば雇われるし、こなせなければ雇われない、というわけだ。入社にあたっては定型の文書もチェックリストもなく、さまざまなシステム登録や訓練も全てスカイプを通じたメンバーとの会話によって行われる。
こうしたプロセスを経て加わった新入社員は、本来の仕事を始める前にかならず「チーム・ハピネス」と呼ばれるサポート専用のチームで働く。

この続きを見るには...
残り2212/3571文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2015.04.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約