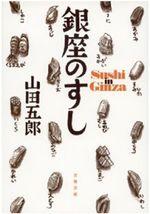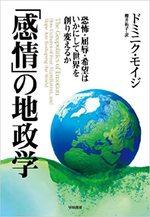宗教で読み解く「日本と世界のこれから」
日本人の宗教観
本書は第1章で、宗教はどんな役割を果たしているのか、日本人として宗教にどう向き合うべきなのか、という池上氏の仮説と主張が述べられている。そしてこれに続く章では、仏教、キリスト教、神道、イスラム教といった伝統宗教の宗教家やその専門家と池上氏との対談を通じて、日本人特有の宗教観や各宗教の特徴について学ぶことが出来る。
日本では、子どもが生まれたら神社にお宮参りをし、七五三も神社で行う。しかし結婚式は教会で挙げて、葬式はお寺でということが、当たり前に行われている。このように宗教への関心は高いにもかかわらず、「あなたの信仰は何ですか?」と問われた時、日本人の多くが「無宗教です」と答えるだろうことも間違いない。世界のほとんどの国で、敬虔な信仰を持った人たちを見ることができるが、そうした国と日本を比較すると、とても不思議な感覚に陥る。
しかし、本書のインタビューのなかで、日本人は単なる無宗教ではなく、実は日本人なりの宗教観や超自然的なものに対する畏れのような宗教意識をしっかりと持っていることがわかる。自分がどのような宗教を信じているかとは無関係に、神社でもお寺でも教会でも、誰かが神聖な場所と思っているならば、そこは大切にしなければと思うものだ。そうした意味で日本人は、宗教がらみの紛争の仲介役に入るなど、国際社会への貢献ができるのではないか。
世界の国々はみな宗教国家

ほとんどの国は、いまも宗教国家だ。たとえばアメリカでは、大統領は就任式において、左手を聖書に置いて宣誓する。つまり、神に誓うのだ。
ヨーロッパ諸国は、西欧も東欧もみな宗教国家であり、神がいることを前提として国家が成り立っている。生まれた子どもの多くは幼児洗礼を受け、その様子はまるで日本のお宮参りのようだ。宗教には、なにかしら共通する意識の構造があるようだ。
さらに言えば、宗教を否定したはずの共産主義もそうした意識構造をもっている。ソ連はトップが変わっただけで精神構造は何も変わっていなかったため、ロシア正教は生き延びたし、タジキスタンやカザフスタンは独立したとたんにイスラム教が一挙に表に出てきた。
中国で1965年から猛威をふるった文化大革命では、誰もが『毛沢東語録』を手に叫びをあげていたが、その様はイスラム教徒が『コーラン』を掲げるのと精神構造は同じと言えよう。
世界の国々の内政にも国際関係にも、宗教は大きな影響を与えている。宗教のことを理解しなくては、世界の動きはまったくわからない。
たとえば仏教では、解脱して涅槃に入ることを理想としている。それは、この世界に二度と生まれてこないことを意味するが、これを若い人に言うととても驚かれるというのが現状だ。キリスト教やユダヤ教やイスラム教には、そもそもこの世界を創ったクリエーターがいるが、仏教にはいない。この本は、そういった基本的なことが学べる入門書としてうってつけである。
【必読ポイント!】 宗教がわかる!
「南無阿弥陀仏」とは
本書でまず紹介されるのが仏教だ。ここでは、『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)という刺激的なタイトルの本を出した宗教学者の島田裕巳氏と、浄土真宗のお寺の住職である釈徹宗氏が池上氏との対談に臨んだ際の様子が紹介されている。
例えば、仏壇に向かうと「ナンマンダブ」と意味もわからず唱えるが、「南無阿弥陀仏」とはどういう意味かご存じだろうか。釈氏によれば、これは「この世界に満ち満ちる、限りない光と限りない生命の仏さまにおまかせして生き抜きます」という、自分の生きる姿勢を表わす言葉だという。自分の生きる姿勢を常に口にして人生を歩む「信仰告白」は世界の多くの宗教で見られる。
ところで、お経を聞いても意味が分からない理由は、漢字をそのまま音読みしているからであるが、聖書がそれぞれの国の言葉に訳されて読まれるように、お経の日本語訳は存在しないのだろうか。