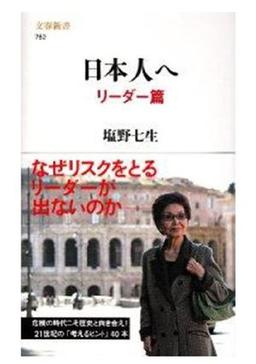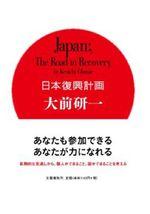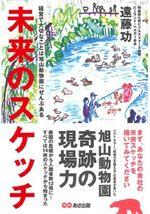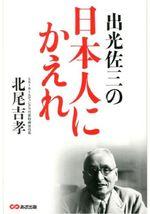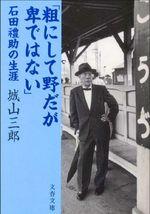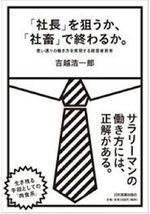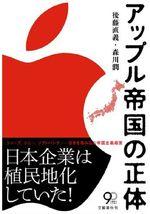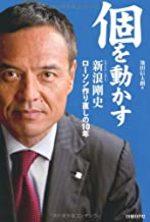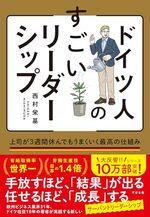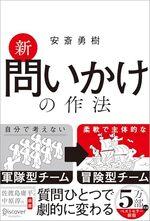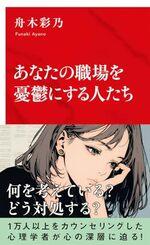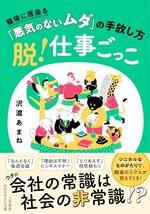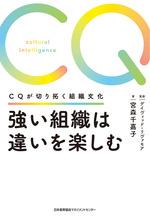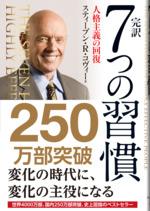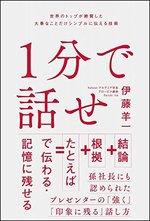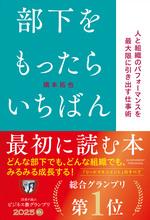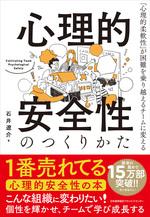二十一世紀の現実
見たいと思わなくても見るしかない現実
本書は日本人が取るべきポジションを、多くはローマ帝国との対比で語られる。冒頭はローマ帝国のユリウス・カエサルの言葉である。
「人間ならば誰にでも、現実のすべてが見えるわけではない。多くの人は、見たいと思う現実しか見ていない」
見たいと思うかどうかわからないが、二十一世紀の現実は次のようなものだ。
一、結局は軍事力で決まるということ
二、アメリカ合衆国への一極集中
三、国連の非力
四、日本の無力
軍事とは究極的には、自らの血を流しても他者を守ることである、と著者は語る。過去に兵役は「血の税」と呼ばれた。ローマ市民は直接税が免除される代わりに、「血の税」の課税対象者であったのだ。一方で、ローマ人に征服された人々は属州民と呼ばれ、兵役の義務がないかわりに、収入の十分の一の属州税が課されたのだ。これは安全保障税だと言われる。まさに日本が湾岸戦争時に多額の経済負担をしたケースが思い出されるかもしれない。
ローマ帝国の統治

ローマ帝国は前三世紀末から後二世紀末までの四百年に圧倒的な強さを誇り、ヨーロッパ、北アフリカ、中近東を網羅し、全域が平和を満喫していたという意味で、「パクス・ロマーナ」と呼ばれた。ローマ帝国がその後の帝国と別格に扱われるのは占領政策にある。
ローマの兵士の特徴は、占領後剣をつるはしに持ち替え工兵と化し、インフラ整備に注力するところにある。また、国家統治の方式も強要せず、属州独自の自治を認めている。
一方で、属州の有力者の子弟、特に十代半ばから二十代半ばの若者は、ローマ等のイタリアの都市に連れられ、現代で言うところのフルブライトの留学生となる。良家が預かり、明日の指導者に必要な帝王学を学ぶ。
このようにローマ帝国の運営哲学は、敗者同化路線である。ローマ帝国を表す言葉として、ファミリーの語源である「ファミリア」と呼ばれていた。そのような強固なローマ帝国も最終的に崩壊を迎える。しかし他の帝国と異なるのは、植民地が次々と独立していったのではなく、属州の離反がなく、帝国として滅亡したところだ。
血の流れない戦争としての外交
若き外務官僚へのメッセージ
著者は外務官僚向けの研修講師の話があったが、大それた依頼だと考え一度断ったものの、実際に話をするなら何を伝えるかということを纏めている。
若き外務官僚がなすべきことは、「外交」ではなく「外政」だという。