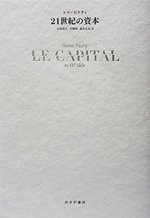夜と霧
新版


著者
ヴィクトール・E・フランクル
1905年、ウィーンに生まれる。ウィーン大学卒業。在学中よりアドラー、フロイトに師事し、精神医学を学ぶ。第二次世界大戦中、ナチスにより強制収容所に送られた体験を、戦後まもなく『夜と霧』に記す。1955年からウィーン大学教授。人間が存在することの意味への意志を重視し、心理療法に活かすという、実存分析やロゴテラピーと称される独自の理論を展開する。1997年9月歿。
著書『夜と霧』『死と愛』『時代精神の病理学』『精神医学的人間像』『識られざる神』『神経症』(以上、邦訳、みすず書房)『それでも人生にイエスと言う』『宿命を超えて、自己を超えて』『フランクル回想録』『を求めて』『制約されざる人間』『意味への意志』(以上、邦訳、春秋社)。
1905年、ウィーンに生まれる。ウィーン大学卒業。在学中よりアドラー、フロイトに師事し、精神医学を学ぶ。第二次世界大戦中、ナチスにより強制収容所に送られた体験を、戦後まもなく『夜と霧』に記す。1955年からウィーン大学教授。人間が存在することの意味への意志を重視し、心理療法に活かすという、実存分析やロゴテラピーと称される独自の理論を展開する。1997年9月歿。
著書『夜と霧』『死と愛』『時代精神の病理学』『精神医学的人間像』『識られざる神』『神経症』(以上、邦訳、みすず書房)『それでも人生にイエスと言う』『宿命を超えて、自己を超えて』『フランクル回想録』『を求めて』『制約されざる人間』『意味への意志』(以上、邦訳、春秋社)。
本書の要点
- 要点1極限状態に陥ると、人は自己防衛のために感情を消滅させてしまう。しかし自然や芸術、ユーモアに触れ、内面を豊かにすることで、正常な精神状態を保つことは可能だ。
- 要点2人は環境によってすべてを決定されてしまうわけではない。どんな状況にあっても、その状況に対してどのように振る舞うかという精神の自由だけは、だれにも奪うことができない。
- 要点3「生きる意味」とは、我々が生きることになにを期待するかではなく、生きることが我々から何を期待しているか、未来で我々を待っているものは何かを知り、その義務を果たすことで生まれる。
要約
第1段階――収容ショック
恩赦妄想
収容所に移送された人々は、まず「恩赦妄想」にとらわれる。死刑を宣告された者が恩赦で助かることを空想するように、「そこまでひどい事態は起きないだろう」、「なにもかもうまくいくはずだ」、と自分に言い聞かせるのである。
実際、移送の貨車に途中で乗り込んできた被収容者たちは、血色もよく、陽気で、その希望を裏付ける姿を見せていた(しかし彼らは実際のところ、新規の被収容者の持ち物から値打ち品を取り上げるために同乗した「エリート」被収容者たちだった)。この恩赦妄想は、夕刻に将校の前で最初の選別を受けるまで、フランクルたちの心を支配していた。
最初の選別

Dodge65/iStock/Thinkstock
夕方、フランクルたちはすべての所持品を置いて貨車から降り、将校の前を歩くように指示された。将校は被収容者が前を通るごとに、指をかすかに右に、あるいは左に動かした。フランクルはできるだけ背筋を伸ばして立った。すると、将校の指は右に動いた。
その夜フランクルは、収容所暮らしの長い男に、一緒に収容された友人の行方がわからないと漏らした。
「その人はあなたとは別の側に行かされた?」
「そうだ」
「だったらほら、あそこだ」
そういって男は、数百メートル先の煙突を指さした。
「あそこからお友だちが天に昇っていってるところだ」
こうしてフランクルは、将校の指の動きが最初の淘汰であったこと、そして収容所がどういう場所であるのかを理解した。
やけくそのユーモアと好奇心
「消毒」と称して身ぐるみをはがされ、体中の毛を剃られ、フランクルたちに残されたのは裸の体ただひとつだけだった。フランクルは書きかけの学術原稿だけは残してほしいと懇願したが、それが叶うことはなかった。
そんな風に希望が潰えていく中で、被収容者たちの心に浮かんだのはやけくそのユーモアだった。「消毒」に使われたシャワー室では、シャワーノズルから「本当に」水が出たことを皆で笑いあった。
ユーモアは、その後の長い収容所生活でも重宝された。ものごとをなんとか笑い話にしようという試みはまやかしにすぎないかもしれないが、生きるためには欠かせないものである。ユーモアとは、状況に打ちひしがれて自分を見失うことのないよう、人間に備わっている魂の武器なのだ。
ユーモアの他にもうひとつ、心を占めたものがある。それは「これからどうなるのだろう」という好奇心だった。世界を外から見るようにして自分たちを観察すると、驚くことがいくつも明らかになった。

この続きを見るには...
残り3402/4420文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.08.05
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約