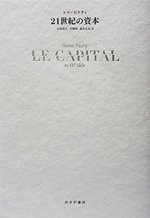利己的な遺伝子
40周年記念版
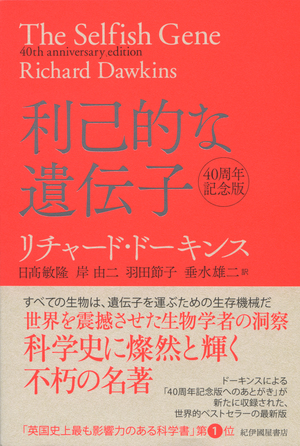
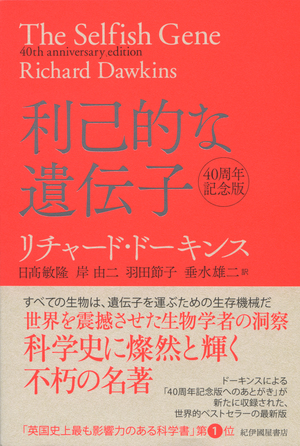
著者
リチャード・ドーキンス(Richard Dawkins)
1941年生まれ。エソロジーの研究でノーベル賞を受賞したニコ・ティンバーゲンの弟子。現在、オックスフォード大学科学啓蒙のためのチャールズ・シソニー講座教授。1976年に刊行された処女作『利己的な遺伝子』が世界的なベストセラーになり、ドーキンスの名声を世界に轟かせた。この本は、それ以前の30年間に進行していた、いわば「集団遺伝学とエソロジーの結婚」による学問成果を、数式を使わずにその意味するところをドーキンス流に提示したもので、それまでの生命観を180度転換した。続く著作に『延長された表現型』、『盲目の時計職人』、『遺伝子の川』、『虹の解体』、『悪魔に仕える牧師』などがある。
英国学士院会員。
ドーキンスは以下の数々の賞を受賞。1987年英国学士院文学賞とロサンゼルスタイムズ文学賞、1990年マイケル・ファラデー賞、1994年中山賞、1997年国際コスモス科学賞、2001年キスラー賞、2005年シェイクスピア賞。
1941年生まれ。エソロジーの研究でノーベル賞を受賞したニコ・ティンバーゲンの弟子。現在、オックスフォード大学科学啓蒙のためのチャールズ・シソニー講座教授。1976年に刊行された処女作『利己的な遺伝子』が世界的なベストセラーになり、ドーキンスの名声を世界に轟かせた。この本は、それ以前の30年間に進行していた、いわば「集団遺伝学とエソロジーの結婚」による学問成果を、数式を使わずにその意味するところをドーキンス流に提示したもので、それまでの生命観を180度転換した。続く著作に『延長された表現型』、『盲目の時計職人』、『遺伝子の川』、『虹の解体』、『悪魔に仕える牧師』などがある。
英国学士院会員。
ドーキンスは以下の数々の賞を受賞。1987年英国学士院文学賞とロサンゼルスタイムズ文学賞、1990年マイケル・ファラデー賞、1994年中山賞、1997年国際コスモス科学賞、2001年キスラー賞、2005年シェイクスピア賞。
本書の要点
- 要点1生物は利他的に見える行動をとることがあるが、それは自らの遺伝子の生存に有利に働くからである。
- 要点2生物とは、遺伝子が自らを外敵から守るために築き上げた「生存機械」に他ならない。
- 要点3生存機械は、多数の遺伝子を含んだ「乗り物」のようなものだ。遺伝子は生存機械を乗り捨てていきながら、自らのコピーを次々と広めていく。
- 要点4「ミーム」は文化的伝達の単位であり、遺伝子のように、自己複製を繰り返していく性質を持つ。
- 要点5将来を予測する能力を持つ人間だけが、利己的な自己複製子に立ち向かうことができる。
要約
【必読ポイント!】 不滅の遺伝子と生存機械
遺伝子はあくまでも利己的にふるまう
これまで、生物は種や集団の利益になる行動をとるように進化してきたと広く信じられてきた。というのも、個体の生存という観点から生物の行動を観察すると、利他的としかいいようがない行動や習慣がいくつも確認されてきたためである。
だが、実際に利益を受け取っているのは、種でも集団でもなく、厳密には個体でもない――遺伝子こそが利益を受け取っている張本人なのだ。こう考えると、見える風景はガラリと変わってくる。生物は利他的に見える行動をとることもあるが、それは遺伝子の生存という意味で有利だからだ。今日まで生き延びていることに成功した遺伝子は、例外なく利己主義であり、ゆえに自然淘汰を生き延びてきたのだといえる。
生物は遺伝子のための「生存機械」である
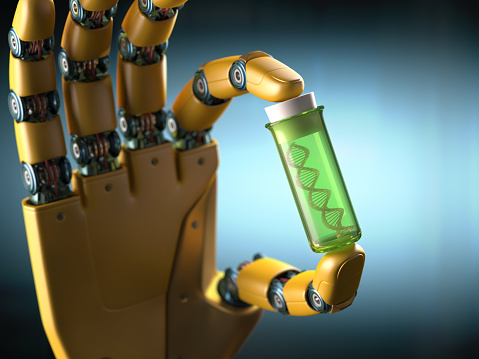
ktsimage/iStock/Thinkstock
遺伝子の始まりは、生命の誕生以前の地球に遡る。あるとき偶然、自らのコピーを作れるという驚くべき特性を備えた分子が登場した。これを「自己複製子」と呼ぼう。自己複製子はあっという間に広がっていったが、コピーをする段階で誤りが起きることがあった。しかし、そのエラーこそが、のちの生命の進化につながった。誤ったコピーは広まっていき、地球はいくつかのタイプの自己複製子で満たされることになった。
数を増やしていった自己複製子の特徴は大きく3つに分けられる。1つ目の特徴は分解のされにくさ、つまり長生きをすることである。長期間にわたって分解されなければ、その分だけ自らのコピーを作ることができるからだ。2つ目の特徴はそれよりも重要で、素早くコピーする能力である。コピーが速ければ速いほど、当然それだけ数を増やすことができる。3つ目の特徴は、コピーの正確性である、数を増やすためには、エラーが少なければ少ないほど望ましい。このように、寿命の長さ、多産性、複製の正確さを備えた分子が、日増しに増えていったと考えられる。
とはいえ、自己複製子が無限に増えていくことは不可能であった。地球の大きさは限られており、自己複製子を構成する分子も、かなりの速度で使い果たされていったからである。
これにより、自己複製子の間で「生存競争」といえるものが生まれた。そして、その過程で生き残った自己複製子は、ライバルから身を守るための容れ物である「生存機械」を築きあげたものたちであった。最初の生存機械は、保護用の外皮の域を出なかったと想像されるが、新しいライバルが次々と現れるなか、生存機械はいっそう大きく、手のこんだものとなっていった。
かつての自己複製子は、いまや遺伝子という名前で呼ばれている。そして、私たちこそがその生存機械なのである。
遺伝子は私たちを「乗り捨て」、生き続ける

Jupiterimages/liquidlibrary/Thinkstock
生存機械はもともと、原始のスープの中で自由に利用できる有機分子を食物にしていたが、それがすっかり使い果たされてしまったことで、別のやり方を採用することが余儀なくされた。
現在、植物と呼ばれている生存機械の多くは、自らが直接日光をつかって単純な分子から複雑な分子をつくりはじめ、原子スープの合成過程をスピーディに再現するという戦略をとった。一方、動物と呼ばれる生存機械は、植物を食べるか他の動物を食べることで、植物の成果を横取りする方法を「発見」した。

この続きを見るには...
残り2846/4197文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.09.01
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約
0%