超予測力
不確実な時代の先を読む10カ条
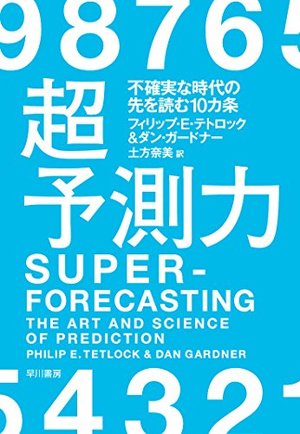
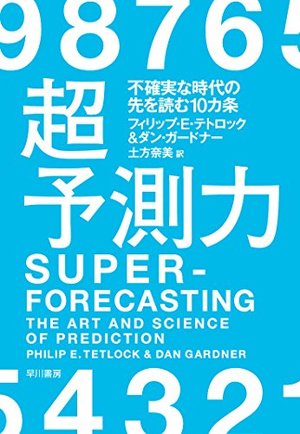
著者
フィリップ・E・テトロック (Philip E. Tetlock)
ペンシルバニア大学経営学・心理学教授。専門は社会・文化心理および意思決定過程。情報先端研究開発局(IARPA)が講演する《優れた判断力プロジェクト》の主催者。著書に Expert political judgment: How good is it? How can we know? 他多数。
ダン・ガードナー (Dan Gardner)
カナダ、オタワ在住のジャーナリスト。《オタワ・シチズン》紙の記者を経て論説委員を2014年までつとめた。カナダ新聞賞など受賞歴多数。著書に世界的ベストセラーになった『リスクにあなたは騙される』(ハヤカワ文庫)、『専門家の予測はサルにも劣る』がある。
ペンシルバニア大学経営学・心理学教授。専門は社会・文化心理および意思決定過程。情報先端研究開発局(IARPA)が講演する《優れた判断力プロジェクト》の主催者。著書に Expert political judgment: How good is it? How can we know? 他多数。
ダン・ガードナー (Dan Gardner)
カナダ、オタワ在住のジャーナリスト。《オタワ・シチズン》紙の記者を経て論説委員を2014年までつとめた。カナダ新聞賞など受賞歴多数。著書に世界的ベストセラーになった『リスクにあなたは騙される』(ハヤカワ文庫)、『専門家の予測はサルにも劣る』がある。
本書の要点
- 要点1直観はときに誤ることもある。意識的に考えるよう徹底することが、最終的な判断の質を高めるためには必要である。
- 要点2超予測者たちは、まず客観的なデータから物事を捉え、その後に個別のストーリーについて検討する。
- 要点3確率論的に物事を考えると、予測の正確性は高くなる。
- 要点4予測の精度を上げるためには、頻繁に最新情報を反映し、最初の考えにこだわりすぎないようにする必要がある。
要約
超予測者の発見
予測の「素人」が専門家を上回った

SIphotography/iStock/Thinkstock
予測力というのは才能ではなく、育てることのできる能力だ。たしかに、人間の力で先を読むことには、どうしても越えられない壁がある。だが、ある程度であれば将来を読むことは可能だし、それは測定可能な本物の「能力」だと言える。
著者は2011年、パートナーであるバーバラ・メラーズとともに「優れた判断力プロジェクト (Good Judgment Project, 以下GJP)」を立ち上げ、未来を予測するためのボランティアを募った。その結果、1年目から1000名以上が名乗りを上げ、最終的には2万人以上の知的好奇心あふれる一般人が、複雑で重大な世界的問題について予測を試みた。そして、そのなかでも優れた予測力を持つ人々は「超予測者」と呼ばれた。
このGJPを支援していたのが、2006年に発足した「情報先端研究計画局(IARPA)」というアメリカ国家情報長官直属の組織だ。彼らにとって、世界的な政治・経済のトレンド予測は重要な活動である。だが、予測の質を確保するための取り組みはそれまで充分にされていなかった。
IARPAはそうした状況を変えるため、予測トーナメントを実施することにした。すると驚くべきことに、GJPの成績は、ミシガン大学やMITといった大学を母体とするライバルチームにも30%~70%の大差をつけて勝利するだけでなく、機密情報にアクセスできるプロの情報分析官の成績までも上回った。アルゴリズムの力を一切借りずとも、プロの情報分析官に勝利できる一般人の存在が確認された瞬間であった。
私たちが予測を間違えてしまう理由

francescoch/iStock/Thinkstock
確固たる結論を引き出すためには直観だけでは足りない。これはどう考えても正しい真実である。だが実際のところ、拙速な判断をしないことの重要性を説いている人物ですら、時としてそれに抗う行動に出てしまう。これは現代の心理学者が好んで用いる「二重過程理論」で説明できる。この理論によると、私たちの意思決定は無自覚的な判断である「システム1」と、自覚的な判断である「システム2」を通しておこなわれている。システム1は迅速であり、わずかな証拠から結論を導き出すようにできている一方、システム2はシステム1で出された答えを突き詰めていく役割を担う。
ただしシステム2は、システム1の下した結論に自動的に介入するわけではない。システム1で出された結論は基本的に筋が通っている。なぜなら、人間の脳は首尾一貫した明快なストーリーを求めるからだ。だからこそ、システム2をうまく働かせるには積極的に疑念を働かせる必要があるのだが、そういった慎重さは、生存するため素早い判断を要求してくる人間の本能と大きく矛盾する。私たちは、最初に思いついた説明を否定する証拠を積極的に見逃すようになっているし、他者から自説を否定するような証拠を突きつけられると、むきになって懐疑的な姿勢をとってしまう。
もちろん、直観が正確であることも少なくない。私たちは訓練や経験を積むことで、大量の、それもきわめて詳細なパターンを記憶に刻み込むことができる。だが、このパターン認識能力は、ありもしないものをあると見なしてしまう、偽陽性のリスクと表裏一体でもある。ときには直観が誤ることもあると認識し、意識的に考えることが、最終的な判断の質を高めるためには必要なのだ。
【必読ポイント!】 超予測者たちの思考法
外側から内側へ
ずば抜けた予測力を持つ人達は、とびきり優秀な頭脳を持っていると考えられがちだ。実際、彼らは博識で知能が高い傾向にあり、知能と知識のテストにおいても、一般人の80%より良い成績を収めている。とはいえ、超予測者たちのスコアは、いわゆる天才の領域にははるかに及ばないことがほとんどだ。予測するうえで知能と知識がプラスに働くのは間違いないが、最終的に重要なのは地頭の良さではなく、それをどう使うかなのである。
例えば「レンゼッティ家がペットを飼っている可能性はどれくらいか」という問題があったとしよう。

この続きを見るには...
残り1857/3515文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.12.12
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











