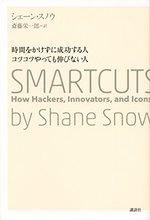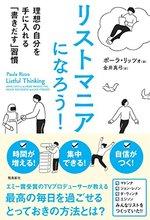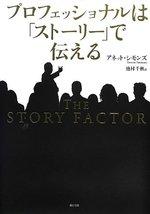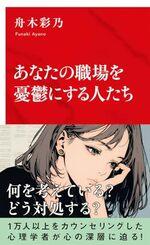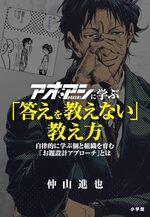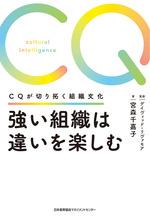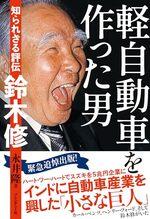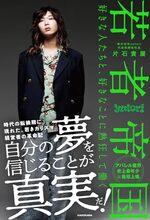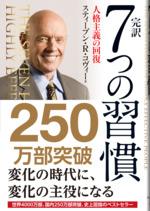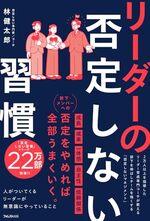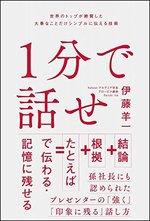人はなぜチームを組むのか
成功のカギは「超チーム力」

テクノロジーが発展した今日において、急激な変化は別段珍しいものではない。しかしこの変化の実態について、我々がその仕組みを十分に理解できているとはかぎらない。猛烈な勢いで移り変わる現実でうまくやりつづけるのは、私たちの想像をはるかに超えるほどに難しい。
そのような中で成功しつづけていくためには、どんな事態にも臨機応変に対処する能力が必要不可欠だ。そしてそれを可能にするのは、高度に最適化されたチーム、すなわち「超チーム力」である。どんな変化にも素早く対応し、事業を成功に導けるかどうか。そのカギを握るのは規模でもテクノロジーでもなく、そこに携わる人々そのものだ。
実際、人類の歴史は、マルコ・ポーロの東洋への冒険やコルテスのアステカ王国征服など、危機的な状況から脱し大勝利を収めた「機動的なチーム」の物語にあふれている。こうした物語から導き出されるのは、ある特定のチーム構造こそが、根本的な強度と安定性を集団に与える、ということだ。チームが安定しているからこそ、人々はある共通の目的のもとに行動できるし、当初の設定とは違う方向に動くよう求められても、うまく対応できるのである。
人間の繁栄にチームあり
ある考古学の研究によると、最も初期のヒト属動物は、集団で狩猟し生活していたという。また、今から6000年ほど前の世界最古の古代都市バビロンでも、分業化はすでにおこなわれていた。
ここで注目したいのは、それだけの月日を経てもなお、この分業制度が廃れていないことである。このことから、人間はひとりでは成功を収めることは難しく、何らかの組織的な枠組のなかで活動することが繁栄に結びついたのだといえる。
21世紀における最先端の脳科学研究も、人間には生まれながらにして協力する習性があることを明らかにしている。人間の脳は、共同作業に従事すべく、他者の考え方や感情にうまく対応できるよう進化してきた。その証拠に、良好な人間関係は私たちの健康維持に有利に働くようになっているし、逆もまた然りだ。
「違い」がチームにもたらすもの

人は皆、異なる考えを持っている。だが、そんなこと当たり前のことだと誰もが認識しているにもかかわらず、チームを組む際にこの事実を考慮する人は極めて少ない。
2001年に心理学者のリチャード・ニスベットと増田貴彦は、アメリカ人と日本人の学生を被験者とし、水中の様子を描いた20秒のアニメーションを見せた。鑑賞後、映像について説明を求めると、アメリカ人は全面を泳ぐ魚などの生物について回答する傾向が高かったのに対し、日本人は石や水槽といった背景の要素にも注目する傾向にあるということがわかった。このように、文化的な視点が異なるメンバーからなるチームの場合、それぞれの認知能力の違いに注意を払う必要がある。逆に言うと、このことを踏まえて集団を管理できれば、こうした多様性が、チームにとって唯一無二の強さの素となる。
多様性のあるチームには、イノベーションを起こすために不可欠な、幅広く柔軟な問題解決能力と批判的思考が備わっている。日産デザインインターナショナルの社長ジェリー・ハーシュベルグが、自由な発想の持ち主と分析的なデザイナーをペアにしているのはその好例である。あえて異なるタイプの人間を組み合わせることで、多様性や緊張感が育まれ、それが最終的には革新的なものを作り出す原動力となるのだ。
ペアをマネジメントする
チームの基礎となるのはペア
ペアは人間のチームにおける最も基礎的なかたちだ。人間はチームを作ろうとするとき、普通まずはペアが形成され、それが合体してより大きな集団に成長する。
ただ、一言でペアといっても、その実態は多種多様だ。並外れた2人が組むことで素晴らしい業績につながったペアの代表例としては、アップル設立時のスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックが挙げられるだろう。