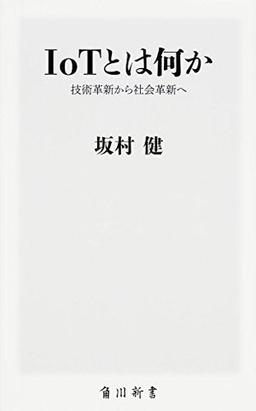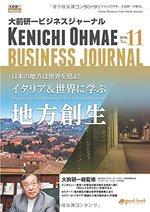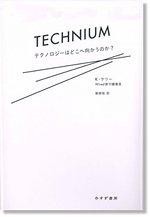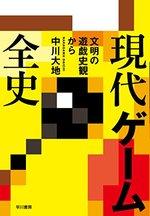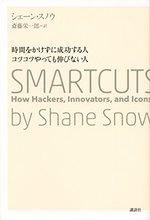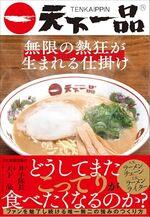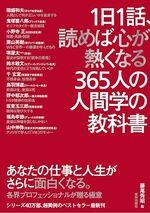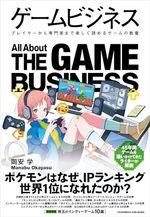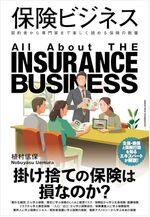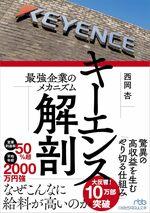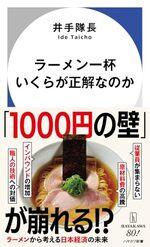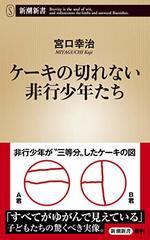IoTのしくみ
IoTとは何か
IoTは、「ユビキタス」と呼ばれていた時代から数えると約30年間研究が続いている分野である。その期間の長さはインターネットが研究開発されて普及するまでの期間と同等であり、まさにインターネットと同じようにオープンなインフラとして社会を支えるものとして取り組まれているテーマだ。現在はすでに実用化へ向けたフェーズに入っていると言える。
一般的に「モノのインターネット」と訳されることが多いが、「モノをインターネットで繋ぐ」というよりも「あらゆる垣根を超えてモノがインターネットのように繋がっている」と捉えるべきだろう。前者は所有者が機器を制御するクローズな利用だが、IoTで目指しているのはもっとオープンな利用のイメージである。
IoTに欠かせない、組込み用OS
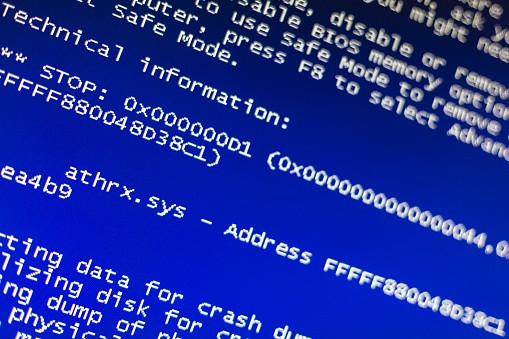
IoTを実現させるためには、さまざまなモノにコンピューターが組み込まれる必要がある。かつてはハード上に直接、まるで職人のように組み上げるシステム開発が主流となっていたが、この方法では開発効率が上がらないのが課題であった。
そこで著者は「組込みシステム開発用の標準OS」(TRONプロジェクト)を作り、広く普及させるために技術仕様やライセンスを無償で公開する「オープンアーキテクチャ」とした。この組み込み用OSの普及で組込みシステムの開発は安定し、技術者の教育は容易になり、ノウハウやユーティリティを共有し蓄積することが可能となった。
コンピューターがどうはたらくか
モノに組み込まれるコンピューターの構成要素は、基本的に「センサー」「コンピューター」「エフェクター」の3つとなる。たとえば電気炊飯器であれば、重量センサーや熱センサーで米の重さや温度をはかり、コンピューターがどう動かすかを判断し、エフェクターがはたらくことで実際に温度を下げたり加熱時間を変えたりするという流れだ。人間の入力や調整は必要なく、状況を読みとって判断し最適なアウトプットを出すということであり、多くのものにセンサーやエフェクターがついていればいるほど、状況を多面的に認識し、人間にとって有用なアウトプットが細かく出せるということになる。
「ギャランティ」か「ベストエフォート」か

日本はTRONプロジェクトの成果もあり、技術的には世界に先んじてIoTの構想をもち、各企業において実現もされている。しかしそれはあくまで一企業の中での仕組みであり「クローズな」環境である点が、世界の企業がめざすオープンな社会の枠組みづくりとは異なるのだ。
確かに企業の枠を超えてシステムが連携するとなるとその責任の所在は曖昧になり、ギャランティ(保証)ができなくなる側面はある。しかしよく考えてみればインターネットのように特定の管理者はいないがそれを利用する人たちそれぞれのベストエフォート(最大の努力)によって成り立つというインフラも存在する。むしろ広く普及するのは後者の仕組みであり、その恩恵も大きなものになると言えるだろう。日本が、クローズなシステムからオープンなシステムへと移行していくのかどうか、今はまさにその分岐点にあると言える。
IoTの実用化
モノのトレーサビリティ
IoTの研究ですでに実現されているものに、「トレーサビリティ」がある。製品自体に電子タグを取り付け、どこでどうやって作られ、どのような過程で運ばれ、どう使われたかなどの情報をすべてコンピューターに記録し追跡できるというものだ。ひとつひとつの製品の管理はもちろん、何か問題があった場合の回収や対応も迅速かつ効率的に行うことができる。
例えば食品や飲料ひとつひとつに電子タグがつけば追跡が可能になるのはもちろんのこと、