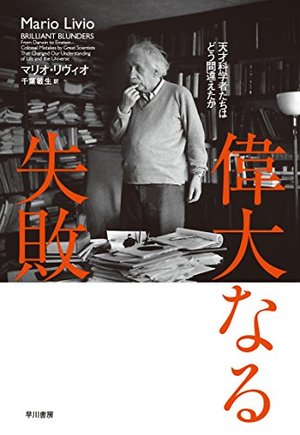偉大なる失敗
天才科学者たちはどう間違えたか
著者
マリオ・リヴィオ (Mario Livio)
宇宙物理学者。アメリカにある宇宙望遠鏡科学研究所の科学部門長をつとめた。宇宙の膨張からブラックホール近傍の物理現象、知的生命の創出など、関心は広い。著書に国際ピタゴラス賞とペアノ賞を受賞した『黄金比はすべてを美しくするか?』、および『なぜこの方程式は解けないか?』『神は数学者か?』(すべて早川書房刊)など多数。
宇宙物理学者。アメリカにある宇宙望遠鏡科学研究所の科学部門長をつとめた。宇宙の膨張からブラックホール近傍の物理現象、知的生命の創出など、関心は広い。著書に国際ピタゴラス賞とペアノ賞を受賞した『黄金比はすべてを美しくするか?』、および『なぜこの方程式は解けないか?』『神は数学者か?』(すべて早川書房刊)など多数。
本書の要点
- 要点1進化論を唱えたダーウィンの誤りは、自説の大きな矛盾を見落としてしまっていたことにあった。
- 要点2地球の年齢を画期的な方法で計測したケルヴィン卿だが、自説への反駁を受け入れられず、結果的に地球の年齢を大幅に見誤ってしまった。
- 要点3タンパク質の構造を解き明かしたボーリングがDNA研究で失敗したのは、DNAの構造決定について不十分な取り組みしかいなかったためだ。
- 要点4恒星内元素構成理論を確立したホイルだが、自説に固執したことで、ビッグバン仮説を受け入れることができなかった。
- 要点5相対性理論で有名なアインシュタインのミスは、シンプルな数式の美しさに固執しすぎたことに起因している。
要約
【必読ポイント!】 チャールズ・ダーウィン
進化論の提唱
13世紀のトマス・アクィナスから18世紀のウィリアム・ペイリーにいたるまで、多くの自然神学者たちは当時、地球上の生物は偉大なる造物主の手によって作られたに違いないと確信していた。だが、チャールズ・ダーウィンは種が永久不変であるという従来の考え方を一蹴し、適応と多様性という概念にもとづいた、いわゆる「進化論」を提唱した。
ダーウィンの理論は、「進化」「漸進説」「共通祖先」「種分化」の4本の柱から成り立っている。そして、そのすべての原動力であり、それぞれの要素を結びつけているのが「自然選択」というメカニズムだ。自然選択とは、個体群の中の「弱い」個体がふるいにかけられて消滅するプロセスであり、環境がそのふるいを振る役目を果たしているとダーウィンは考えていた。
ダーウィンの失敗

00Mate00/iStock/Thinkstock
何世紀も信じられていた考えをひっくり返したダーウィンだが、そんな彼も実は過ちを犯していた。
当時の科学界では、両親の特徴はペンキを混ぜ合わせるように融合して子に伝えられるという「融合遺伝」という考えが一般的だったのだが、この考えに立脚してしまうと、自然選択は期待通りに作用しえない。ダーウィンは従来の融合遺伝説には満足しておらず、メンデル遺伝の先駆けとなる着想をもっていたものの、最終的には「パンゲン説」というまったく的はずれな理論を提唱してしまっていた。
スコットランドの電気技術者フリーミング・ジェンキンによる指摘を受けて、ダーウィンは融合遺伝の代わりとなる「パンゲン説」を提唱してみたものの、これはまったくの的外れ。結局のところ、彼の自然選択による進化論がうまく機能するためには、メンデルによる遺伝学を待たなければならなかった。
ケルヴィン卿
地球の年齢を推定する
人間は有史以来、ずっと地球の年齢に興味を抱いてきた。著名な物理学者、ウィリアム・トムソン、のちのケルヴィン卿もその1人だ。
彼の主張は、「地球は冷却しているため、熱力学の法則を使えば、地球の有限の地質学年齢、つまり固体の地殻が形成されてから現在の状態に至るまでの時間を計算できる」というものだった。
この考え自体は目新しいものではなく、19世紀初頭にはフランスの物理学者ジョセフ・フーリエが、熱伝導や地球の冷却プロセスに関する数学理論を構築していた。だが、ケルヴィン卿の偉大なところは、フーリエの理論が有望だと信じ、地球の年齢を精密に計算するため、様々な情報を集めたところにある。その結果、地球の年齢は2000万歳から4億歳までに収まることは確実だという答えを導き出した。ケルヴィン卿は解決困難な問題に挑み、一定の成果を上げたのである。
ケルヴィン卿の失敗

Tanya Constantine/Blend Images/Thinkstock
ケルヴィン卿は地球の年齢は2000万歳から4億歳までに収まると推定したが、現在では地球の年齢はその50倍にもあたる45億4000万歳だとわかっている。彼の計算はなぜこれほど誤ってしまったのだろうか。
ケルヴィン卿の考えた仮説の穴を見つけた最初の人物は、ケルヴィン卿の元教え子で助手であった工学者のジョン・ペリーだった。彼は、「地球の熱伝導率はどの深さでも一定」というケルヴィン卿の仮説に疑問を投げかけ、「地球のマントルが対流すると仮定すれば、地球の奥深くでは熱がもっと速く伝わる可能性がある」と主張した。だが、ケルヴィン卿はこうしたペリーの主張を認めることができなかった。
だが1896年、フランスの物理学者アンリ・ベクレルが「放射性崩壊」という現象を発見したことで、多くの学者が放射性崩壊を研究するようになり、「あらゆる放射性元素の原子には、熱として放出される膨大な量の潜在的エネルギーが秘められている」という結論が導きだされた。これにより、ケルヴィン卿の仮説はさらに厳しい立場に立たされることとなった。

この続きを見るには...
残り2687/4259文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.01.20
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約