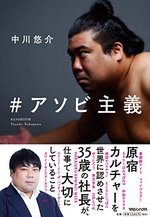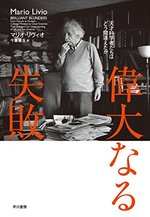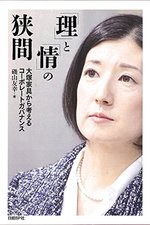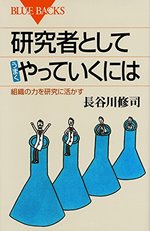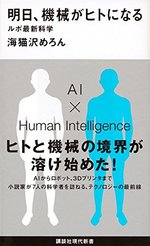究極にうまいクラフトビールをつくる
キリンビール「異端児」たちの挑戦


著者
永井 隆(ながい たかし)
1958年生まれ。群馬集桐生市出身。明治大学卒業。東京タイムズ記者をしていた1992年、同紙が突如休刊し、そのままフリージャーナリストとして独立。雑誌や新聞、ウェブなどで取材執筆活動を行う一方、テレビ、ラジオのコメンテーターも務める。『サントリー対キリン』(日本経済新聞出版社)、『人事と出世の方程式』(同)、『ビール15年戦争』(同)、『ビール最終戦争』(同)、『ドキュメント 敗れざるサラリーマンたち』(講談社)、『現場力』(PHP研究所)など著書多数。
1958年生まれ。群馬集桐生市出身。明治大学卒業。東京タイムズ記者をしていた1992年、同紙が突如休刊し、そのままフリージャーナリストとして独立。雑誌や新聞、ウェブなどで取材執筆活動を行う一方、テレビ、ラジオのコメンテーターも務める。『サントリー対キリン』(日本経済新聞出版社)、『人事と出世の方程式』(同)、『ビール15年戦争』(同)、『ビール最終戦争』(同)、『ドキュメント 敗れざるサラリーマンたち』(講談社)、『現場力』(PHP研究所)など著書多数。
本書の要点
- 要点1キリンビールの和田徹は、ビールの未来がクラフトビールにかかっているという思いのもと、非公式なプロジェクトを発足させた。そして、究極にうまい新次元のクラフトビールを醸造しその場で飲める「大聖堂」が必要だと訴えた。
- 要点2このプロジェクトは、大量生産で利益を上げるという業界の常識に逆行するものであったが、和田たちは社長やキーパーソンを味方につけ、「大聖堂」の建設に漕ぎつけた。
- 要点3東京の代官山に「大聖堂」こと「スプリングバレーブルワリー東京」が開業し、日本のビール文化を変える革命が始まった。
要約
【必読ポイント!】 ビールの未来
非公式なプロジェクトの始動
キリンビールに勤める和田徹は、日本のビールの未来を憂えていた。ビール市場は毎年縮小し、若者のビール離れが進んでいる。和田は日本のビール業界の大手が同じような商品ばかりをつくっていて、ビールの魅力を伝えられていないことに原因があると考えた。
2011年10月、出向先から本社マーケティング部に戻った和田は、「ビールの未来をつくろう」と社内で有志を募った。そこで、同じくキリンビールの社員であり醸造家でもある田山智広と意気投合し、「ビールの未来」がクラフトビールであることを見いだした。そして和田の考えに共鳴したマーケティング部の入社6年目の吉野桜子を招き入れ、3人の非公式なプロジェクトがスタートした。
クラフトビールとは
和田が「ビールの未来」として見いだしたクラフトビールとはどういうものなのか。日本のビール業界の大手は、大規模な工場でビールを生産する。そのほとんどが、澄んだ淡色でホップの苦みを利かせた「ピルスナー」である。発酵を終えた酵母が下層に沈む「下面発酵」により醸造され、このタイプのビールは海外では「ラガー」と呼ばれる。10℃以下の低温で、1カ月半ほどの期間で発酵する。
一方、クラフトビールは小規模な醸造所でつくられ、「上面発酵」で醸造される「エール」が多い。20℃程度の常温で発酵し、期間はラガーより短い。醸造所により味わいが異なり、果実やさつまいもを原料とするものもある。このように、ビールはワインや日本酒に負けないほど多様な醸造酒なのだ。
日本では地ビールがクラフトビールに呼称を変え、2010年ごろから需要を増やしていった。しかし、小規模な醸造所の出荷量は大手ビールメーカーに遠く及ばない。一方アメリカでは、クラフトビールの支持が高まっている。特に西海岸で著しく、オレゴン州では2015年の販売量シェアが30%を超えたという。バドワイザーなどのメガブランドが伸び悩む中、個性的なクラフトビール醸造所が増え、生産量を伸ばしている。
ビール文化に革命を起こす「大聖堂」
和田はビールの本当の魅力を伝えるために「大聖堂」が必要だと訴えた。和田の語る「大聖堂」とは、ビールを醸造し、その場で飲めるビアホールであり、建設後も常に進化し続けるような「概念」でもある。「大聖堂」から情報を発信して人々のライフスタイルを変え、日本のビール文化に革命をもたらすという構想を描いているのだ。実現すれば、大手ビールメーカーが初めて本格的に取り組むクラフトビール事業となる。
しかし、ビール産業はいわゆる「装置産業」である。大がかりな設備で同じ商品を大量に生産すればするほど利益を得られる。そのため「大聖堂」は、キリンも含む大手ビールメーカーの進めてきた効率化に逆行するものであった。
2009年当時、キリンはシェア争いでアサヒビールに引き離され、サントリーとの統合計画は破談となった。また、酒税法の改正により、ビール、発泡酒、第三のビールの税率を将来的に一本化しようとする動きも生まれていた。改正となれば、第三のビールに強みを持つキリンにとって大きな痛手となる。苦境の最中、和田たちのプロジェクトに対して社内で疑問の声が上がった。
もちろん和田は大量生産のビールがなくなることがないのは分かっていた。しかし、市場の縮小に歯止めがかからない中、まったく新しい流れをつくる必要性を痛感していた。和田はそれをクラフトビールで主導したいと考えたのである。
和田はキリンの子会社でキャリアをスタートさせ、1997年に発泡酒の開発プロジェクトに参加するために親会社に出向・転籍したという、異例の経歴の持ち主である。そこで手がけた「淡麗」と「氷結」は、大ヒット商品となった。
和田は無から有を生む、つまり「0」を「1」にする商品開発を得意とし、「大聖堂」はまさに無から有を生むプロジェクトである。若者たちが「ビールってカッコイイ」と考えるような未来をつくっていくという和田の信念が揺らぐことはなかった。
転機
プレゼンで新社長を味方につける
2012年1月、磯崎功典がキリンビールの社長に就任した。磯崎はホテル事業に長く携わり、アメリカに社内留学した経験がある。よって、クラフトビールへの理解が深いはずだという情報が和田にもたらされた。プロジェクトを軌道に乗せるためには、社長の了承が不可欠だと考えた和田は、新社長に「大聖堂」のプロジェクトをプレゼンすると決め、資料の作成を桜子に指示した。
5月に行われたプレゼンは見事成功した。

この続きを見るには...
残り2525/4398文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.01.21
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約