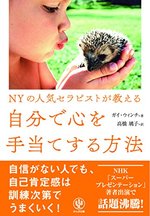仕掛学
人を動かすアイデアのつくり方

著者
松村 真宏(まつむら なおひろ)
1975年大阪生まれ。大阪大学基礎工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。2004年より大阪大学大学院経済学研究科講師、2007年より同大学准教授、現在に至る。2004年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校客員研究員、2012〜2013年スタンフォード大学客員研究員。趣味は娘たちと遊ぶこと(遊んでもらうこと)。
1975年大阪生まれ。大阪大学基礎工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。2004年より大阪大学大学院経済学研究科講師、2007年より同大学准教授、現在に至る。2004年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校客員研究員、2012〜2013年スタンフォード大学客員研究員。趣味は娘たちと遊ぶこと(遊んでもらうこと)。
本書の要点
- 要点1多くの問題は自分の行動を変えることで問題の解決につながるが、実際に行動を変えるのは難しい。無理やり行動を変えさせるのではなく、つい行動を変えたくなるように仕向ける「仕掛け」が有効である。
- 要点2仕掛けには3つの定義がある。誰も不利益を被らない「公平性」、行動を強要せず、仕掛けが行動の選択肢を増やす「誘因性」、仕掛ける目的と、行動する目的が異なる「目的の二重性」である。
- 要点3「仕掛け」は大きく物理的トリガと心理的トリガに分類される。物理的トリガは物理的な特徴、心理的トリガは人の内面に生じる心理的な働きを表す。
要約
「仕掛け」とは
仕掛学の誕生

Lisa5201/iStock/Thinkstock
著者はもともと人工知能の研究者であり、コンピュータを使用してデータから意思決定に役立つ知識を発見することに取り組んでいた。
しかしある日、世界で起こるほとんどの事象は、データにはなっていないことに気づく。
生活空間で聞こえる鳥のさえずりや木々の葉がこすれる音など、データになっていないものは無尽蔵に存在する。そしてどんなに高性能のコンピュータでもデータがなければただの箱にすぎない。
この問題を解決する一つの方法はデータやコンピュータに頼ることを止めることである。
人はデータに頼らなくても、道端の花や鳥のさえずりに気がつく。そこには日常の生活空間の魅力を人に気づかせる、「仕掛け」が存在するのである。
著者が見つけた最初の仕掛けは、大阪の動物園で見つけた筒である。真ん中が穴になっており、地上から約1メートルの高さのところに設置されていて、子どもは覗きたくなるようにできている。実際に覗くと、筒の先にある象のフン(精巧な模型)が見える仕組みである。
子供にかぎらず、動物園ではどうしても動物に注目が集まり、それ以外のことには目が届きにくい。しかしこの動物園では「生態的展示」という生息地の環境を再現した展示があり、動物以外のところにも見所があることを筒は気づかせてくれる。
仕掛けとは普段、見えているのに、聞こえているのに気づかない事象を気づかせるための仕組みのことである。著者は仕掛けの事例を集めていくうちに、問題解決のための手段として汎用的に仕掛けが利用できることに気づいた。「仕掛学」の誕生である。
仕掛けで問題を解決する
私たちが直面する多くの問題は私たち自身の行動が作り出している。環境問題や交通安全から自分のダイエットに関するものまで、多くの問題は自分の行動を変えることで解決につながる。しかし多くの人は望ましい行動を自覚し理解していても、行動に移すのは難しいのが現実である。
このとき「このように行動するのが良い」という直接的なアプローチではなく「つい行動したくなる」ように間接的なアプローチで結果的に問題解決に繋げるのが仕掛けである。イソップ寓話の「北風と太陽」のように無理やり行動を変えさせるのではなく、つい行動を変えたくなるように仕向けることが重要である。
仕掛けの定義

ismagilov/iStock/Thinkstock
本書では、以下の3つの要件を満たすものを「仕掛け」と定義する。それは「公平性」、「誘因性」、「目的の二重性」である。3つを英訳した際の頭文字を取って「FAD要件」と呼んでいる。一つ目の「公平性」は誰も不利益を被らないもので、他人を欺くものは仕掛けとは呼ばない。二つ目の「誘因性」は行動を強要するのではなく、仕掛けが行動の選択肢を増やす、かつ個人が行動するかを選べることが前提である。最後の「目的の二重性」は、問題を解決しようとする仕掛ける側の目的と、行動したくなる仕掛けられる側の目的が異なることで、目的に二重性のないものは「仕掛け」とは見なさない。
仕掛けの基本
行動の選択肢を増やす
仕掛けは、人の行動の選択肢を増やすものである。また仕掛けは行動の選択肢を増やすだけで、行動を強要しない。どの行動を選んでも自ら選んだ行動なので不快に思うことはない。また、もともと何もなかったところに選択肢を追加するだけなので、最初の期待から下がることもない。つまり仕掛けとは、選択肢を魅力的に見せることで、自ずとそちらの行動がえらばれるように仕向けることである。
また仕掛学は仕掛けに興味を持った人のみアプローチしていくため、全員の行動を変えることは想定していない。どれほど効果があるかに加え、製作のコストや難易度も考慮して、その場に合う仕掛けを作ることが望ましい。例え100人のうち一人しか反応しなくても、簡単に実現できるものなら、良い仕掛けと言える。
仕掛けの強弱
仕掛けには、多くの人が反応するものと、一部の人しか気づかないものがある。

この続きを見るには...
残り2518/4126文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.02.17
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約