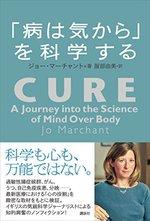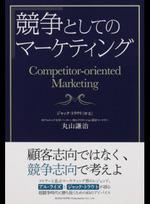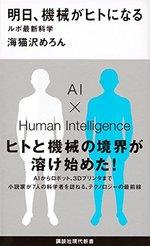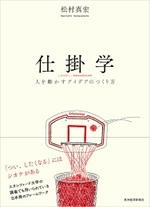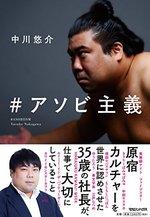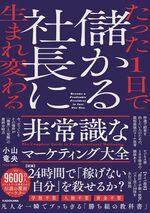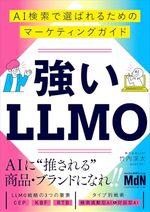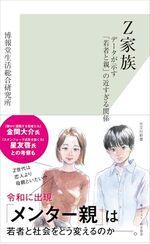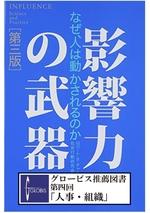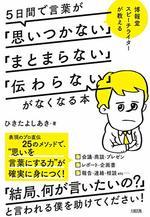ビジネスには「センス」が必要
差のない時代に「センス」を磨く重要性
ビジネスの究極の目的とは、「違いをつくること」だ。あらゆるデータを分析、数値化して合理的に論理を組み立て、みんなと同じことを求めていてはいけない。個人が、「センス」を発揮して、違いをつくることが求められている。センスとは「微妙な違いに気づき、感じ、嗅ぎ分けられる感覚の総体」である。全体の流れや細部の変化まで感じ取ることができれば、次の予測に違いが出る。とくに現在のような答えが見えづらい時代にこそ、予想外の発想で人に幸せや楽しみ、驚きを与えることが重視される。
著者は以前、データや調査資料をもとに合理的なコンセプトをつくりあげたところ、上司から「ロジックのエモーショナル化がない」と指摘されたという。たとえロジックを上手く組み立てたとしても、センスがなければ、人の心を動かせないことを示している。
そもそも、ビジネスとは全てケース・バイ・ケースであり、人間が生み出したものである。人間は「好き嫌い」の感情を伴うため、数値によるデータではなく、感覚的な「センス」で共感を得る必要がある。つまり、「この商品サービスを、どのように好きにさせるのか?」を考えることが、差別化を図る上で欠かせない。
創造性を発揮したいなら、センスを磨け

未来の予測の精度を上げるには、センスを磨き、感度を高める必要がある。微妙な違いを感じ取れるようになるには、モノゴトを知らなくてはならない。
知識と体験を増やすことで、センスが磨かれる。すると、全体を見渡しやすくなり、個々の違いも発見しやすくなる。とくに発想がモノを言う仕事では、全体を俯瞰して仮説につなげ、「考えること」と「表現すること」を一体化させる姿勢が求められる。
ビジネスにおいては、いくら見事な戦略を組み立てたとしても、最後のディテールに気をくばれるかどうかが勝敗を決めることがある。日本人は、合理性や効率性が重視される欧米と比べたとき、気くばりのセンスがあると言われる。日本人の気くばりの細やかさは、想像力を働かせて相手の立場でモノゴトを考え、微妙な違いを感じ取った結果によるものである。今後、日本人が持つ想像力は、世界にも通じる大きな競争力となる。
著者によれば、センスとはクリエイティブの触覚部分となり、すべてはセンスからはじまる。創造性を発揮するには、日頃からモノゴトを知ろうとし、センスを磨くことが求められるのだ。
【必読ポイント!】 センスは誰でも磨ける
センスの有無は体験と知識次第

個々人のセンスは、天性のものではなく、その人が過去に得た知識や体験がベースとなっている。センスは誰もが持っているものであり、アートにとどまらず生き方やビジネスなど、ところどころで発揮されるセンスの総体が「あなたらしさ」となる。あえて「センスがない」と言うとすれば、それはモノゴトを知らないにすぎない。
一流と評価される人は、センスを磨く努力を怠らない人だといえる。センスとは誰かから教わるものではなく、自分でモノゴトを知っていく中で育つものにほかならない。「ビジネスのセンスを磨こう」と思うのなら、ひとつの課題に対してひたすら時間をかけて、量をこなし、深掘りしていくことが効果的だ。
センスのいい人は目のつけどころが違ううえに、あらゆる体験を通して、たくさんのモノサシを持っている。