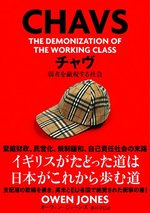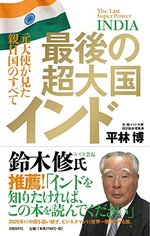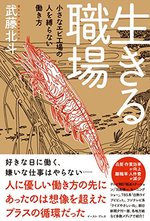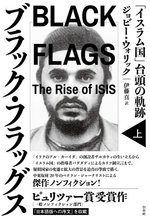若い読者のための第三のチンパンジー
人間という動物の進化と未来
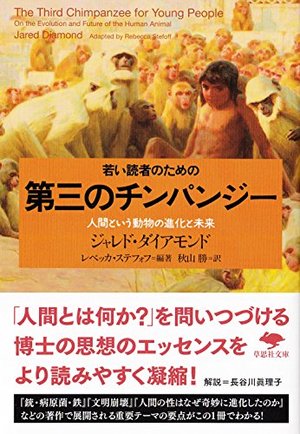
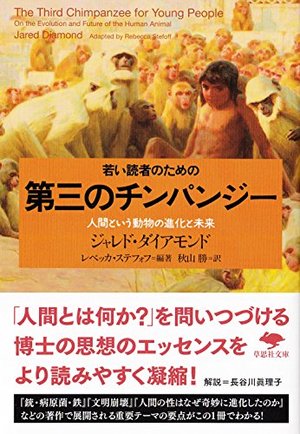
著者
ジャレド・ダイアモンド (Jared Diamond)
1937年ボストン生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。進化生物学者、生理学者、生物地理学者。アメリカ国家科学賞受賞。著書『銃・病原菌・鉄』(草思社)でピュリッツァー賞、コスモス国際賞受賞。同書は朝日新聞「ゼロ年代の50冊」第1位に選ばれた。他に『人間はどこまでチンパンジーか』(新曜社)、『セックスはなぜ楽しいか』(草思社)などの著書がある。
1937年ボストン生まれ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授。進化生物学者、生理学者、生物地理学者。アメリカ国家科学賞受賞。著書『銃・病原菌・鉄』(草思社)でピュリッツァー賞、コスモス国際賞受賞。同書は朝日新聞「ゼロ年代の50冊」第1位に選ばれた。他に『人間はどこまでチンパンジーか』(新曜社)、『セックスはなぜ楽しいか』(草思社)などの著書がある。
本書の要点
- 要点1人間を人間たらしめているのは「言語」である。複雑な発声を可能にする咽頭周辺の発達があったために、人間は言語を手に入れ、発展を遂げることができた。
- 要点2人間の場合、子孫を最大数残すことが最大の目的とはかぎらない。繁殖とは無関係な性行動や、繁殖ができない年齢になっても生き延びる老人の存在は、人間に特有のものだ。
- 要点3農業によって、人口は大きく増えた。しかしその代わりに飢饉や疫病が生じ、不平等な階級社会も誕生した。
- 要点4ジェノサイド(大量虐殺)は人間だけに見られる特徴ではないが、他の動物をここまで急速に全滅させてきたのは人間だけである。
要約
【必読ポイント!】 哺乳類としてのヒト
ヒトになる

Goce Risteski/Hemera/Thinkstock
人間とチンパンジーの違いは、遺伝子で見ればごくわずかだ。しかし、このわずかな違いが、私たち人間とチンパンジーを決定的に分けている。では私たちとチンパンジーは一体何が違うのだろうか。
地球上に生命が誕生したのが数十億年前であることを踏まえると、人類の祖先がチンパンジーの祖先から分かれたのは、ほんの1000万年から600万年前と、ごく最近のことだ。人類の祖先は、400万年前に二足歩行を始めたと言われている。
250万年前ごろになると、より人間らしい特徴である道具の使用が見られるようになる。この時期にはいくつかの先行人類が存在していたが、生き残ったのは1種だけだ。それが現生人類の祖先であるホモ・エレクトゥスである。彼らは道具を使うことで、他の先行人類との生存競争を勝ち抜いたと考えられている。
その後、ホモ・エレクトゥスはホモ・サピエンスへと進化を遂げ、3種の原始人に分かれていく。(1)ヨーロッパと西アジアに住んでいたネアンデルタール人、(2)アフリカに住み、現代人と似た身体的特徴を持っていた集団、(3)東アジアに住んでいたと見られる集団である。
このうち、東アジアに住んでいたと見られる集団については、よくわかっていない部分が多い。一方、ネアンデルタール人とアフリカに住んでいた集団については、原始的な石器を用いていたことがわかっている。ただ、彼らには人間にとって最も重要な資質である「革新性」、すなわち、新しいものを生み出していく能力が備わっていなかった。では、人類の革新性は、どのように得られたのだろうか。
人類の大躍進
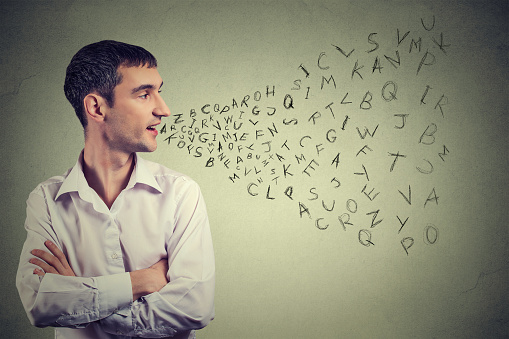
SIphotography/iStock/Thinkstock
人類の大躍進は、およそ6万年前に始まった。私たちの祖先(クロマニヨン人と呼ばれることが多い)が大きくその居住区を広げ、先住のネアンデルタール人にとって代わっていったのだ。
その大躍進を起こした要因は、DNAのわずか0.1%に起きた変化、すなわち「言語」の登場にあった。私たちの祖先は、ある時点から複雑な話し言葉を操れるようになった。そして、発明する力を急速に発達させていった。
類人猿も、口から出す音によってコミュニケーションを取っている。しかしヒトと違い、彼らに複雑な言語活動は見られない。では、なぜチンパンジーは複雑な自然言語を発達させてこなかったのか。それは、のど周辺の構造の違いに原因がある。
ヒトが言葉を話せるのは、声帯がある喉頭や舌など、たくさんの構成要素と筋肉が正しく機能しているためである。一方、類人猿は限られた母音と子音しか発音できない。そのため、複雑な言葉を話すことができない。ヒトをヒトたらしめたのは、声道に生じた、きめ細かく音声をコントロールし、幅広い発声を可能にするという変化だったのである。
言語が生まれたことで、狩りの段取りや道具の作り方など、複雑な情報のやり取りが簡単にできるようになり、自分とは異なる集団や、次の世代に知識を伝えることも可能になった。人類の革新性は、言語の獲得によって生まれたのだ。
ヒトの特殊なライフサイクル
ヒトの性行動
ライフサイクルという観点でも、人間と他の動物はずいぶん異なっている。
ライフサイクルは、1回の放卵や出産でどれぐらい子どもを生むか、母親や父親が子どもの世話をどれくらいおこなうか、大人はどのような社会的関係を結ぶのか、雄と雌はどうやって相手を選ぶのか、平均的な寿命はどれぐらいなのか等によって形づくられる。
特にヒトの性行動は、他の哺乳類とはまったく違う。

この続きを見るには...
残り2793/4236文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.12.02
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約