チャヴ
弱者を敵視する社会
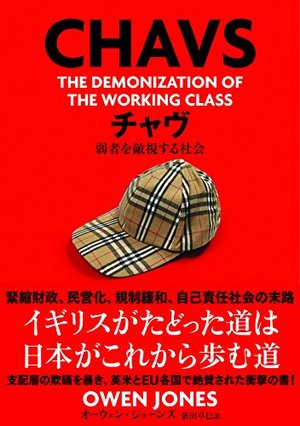
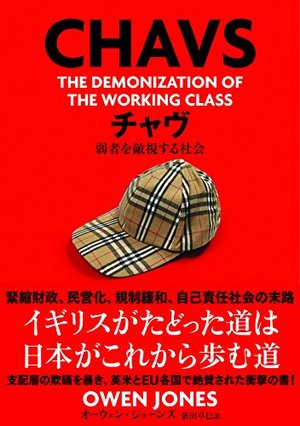
著者
オーウェン・ジョーンズ (Owen Jones)
イギリスのシェフィールド生まれ。オックスフォード大学卒(歴史学専攻)。20代で初の著書である本書を上梓。たちまち世界的ベストセラーとなり、各国の政治運動のあり方に一石を投じた。本書はまた、ニューヨーク・タイムズ紙の「2011年の本トップ10」に選ばれ、2013年には「ポリティカル・ブック・アワード」の「ヤング・ライター・オブ・ザ・イヤー」も獲得した。現在は、ガーディアン紙などでコラムを執筆。テレビやラジオでも活躍中。いま世界が注目する若き論客でもある。その他の著書に『The Establishment』(2018年海と月社刊)がある。
イギリスのシェフィールド生まれ。オックスフォード大学卒(歴史学専攻)。20代で初の著書である本書を上梓。たちまち世界的ベストセラーとなり、各国の政治運動のあり方に一石を投じた。本書はまた、ニューヨーク・タイムズ紙の「2011年の本トップ10」に選ばれ、2013年には「ポリティカル・ブック・アワード」の「ヤング・ライター・オブ・ザ・イヤー」も獲得した。現在は、ガーディアン紙などでコラムを執筆。テレビやラジオでも活躍中。いま世界が注目する若き論客でもある。その他の著書に『The Establishment』(2018年海と月社刊)がある。
本書の要点
- 要点1チャヴへの嫌悪感はイギリス中に広まっている。こうしたバッシングは、昔から続く階級差別のあらわれだ。階級闘争はまだ終わっていないどころか、むしろ強まってきている。
- 要点2サッチャリズムにより、「貧困はすべて自己責任である」という風潮が広く見られるようになった。しかし根本的な問題は、安定した仕事の欠如にある。
- 要点3これからの労働組合は、労働者が誇りや社会的価値の感覚を取り戻すことを主眼に、彼らが感じている疎外感の問題にも取り組んでいく必要がある。
要約
階級のない社会という迷信
見えない被差別民

Digital Vision./Photodisc/Thinkstock
イギリスには「チャヴ」という差別用語がある。主に労働者階級の人間を指した言葉で、「偽物のバーバリーなどを身に着けた無職の若者を中心とする下流階級」というのが、多くの人が持っているチャヴのステレオタイプだ。
現在、チャヴへの嫌悪感はイギリス中に広まっている。人種や性別への差別に敏感な人ですら、チャヴへの偏見を根強く持っている。マスメディアは、「チャヴの生活」のぞっとするエピソードをしきりに取材し、それが労働者階級の典型的な暮らしであるかのように演出する。また、インターネットでも、チャヴを笑いものにするようなサイトがあちこちで見つけられる。まるで、労働者階級はどれほどけなしても許されるかのようである。
チャヴという言葉には、労働者階級に関連した暴力、怠惰、10代での妊娠、人種差別、アルコール依存など、ありとあらゆるネガティブなイメージが含まれている。とくに、「白人労働者階級」という意味で使われることが目立つ。「白人労働者階級は人種差別主義者の集まりなのだから、彼らに何を言っても許される」という風潮がイギリスにはある。
中流階級が支配する世界
興味深いことに、イギリスの人の半数以上は自分のことを労働者階級だと考えている。実際、この自己認識は概ね正しい。今日のイギリスで、ブルーカラーの労働とホワイトカラーの単純事務作業に従事している人を合わせると、労働者全体の半分を超えるからだ。
にもかかわらず、ジャーナリストや政治家たちは、すでに階級社会はなくなりつつあると見なしている。彼らの論理はこうだ。かつての優秀な労働者階級の多くは、すでに全員中流階級にステップアップしている。残っているのは野心も向上心も持たない、「野生化した下流階級」――すなわちチャヴ――だけである、と。
ジャーナリストや政治家がチャヴのことを無視しているのは、彼らが恵まれた中流階級の家庭で育ち、労働者階級とまったく触れることなく社会に出ているからだ。中流階級の人々にとって、チャヴはそもそも同じカテゴリの人間とは見なされていない。しかも、チャヴを代弁するジャーナリストや政治家は、ますます少なくなっている。
階級闘争は「上から」仕掛けられた

LewisTsePuiLung/iStock/Thinkstock
チャヴへのバッシングは、昔から続く階級差別の流れの延長にある。イギリスにおける保守党の歴史はまさに、労働者階級の脅威から「特権階級の仲間たち」を守る歴史であるといえるだろう。
なかでも特筆すべきは、1980年代のマーガレット・サッチャーの政策だ。サッチャーは、国民に階級で物事を考えるのをやめさせたかった。ある集団が富と権力を持っているのに、ほかの集団は持っていないことを認めてしまうと、それを修正しなければならないという結論が導かれてしまうからである。
だからこそサッチャーは、集団的な行動で自分たちの生活をよくするという考えを否定し、それぞれが自ら向上すること、つまり「自助努力」を尊んだ。結束を認めないことで、自分がどの階級に属しているのかを人々に認識させないようにしたのである。そして、労働組合を叩きのめし、税の負担を労働者階級と貧困者に移し、ビジネスから国の規制を取り払った。
サッチャーは、たしかに階級闘争を終わらせようとしたのかもしれない。しかし、そこには「上流階級に有利な条件で」という但し書きがつけ加えられていた。

この続きを見るには...
残り3406/4793文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.11.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











