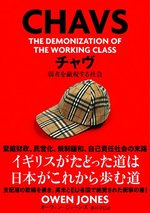航空産業入門
[第2版]

著者
㈱ANA総合研究所
航空事業に関連する戦略を研究し提案する組織として2004年に全日本空輸株式会社内に設置された「ANA総合研究所」を母体に、2006年4月に「株式会社ANA総合研究所」として法人化された。以来ANAグループで蓄積してきた知識・ネットワークを生かして、長期的な航空需要開拓を目指した地域活性化や観光振興、海外との人の交流拡大策の研究、ANAグループ内のノウハウを活かすための人材活用やアイデア発掘、新たな発想での空港活用ビジネスモデルの研究等、大胆な発想で元気に未来を切り開くようなテーマに取り組んでいる。
航空事業に関連する戦略を研究し提案する組織として2004年に全日本空輸株式会社内に設置された「ANA総合研究所」を母体に、2006年4月に「株式会社ANA総合研究所」として法人化された。以来ANAグループで蓄積してきた知識・ネットワークを生かして、長期的な航空需要開拓を目指した地域活性化や観光振興、海外との人の交流拡大策の研究、ANAグループ内のノウハウを活かすための人材活用やアイデア発掘、新たな発想での空港活用ビジネスモデルの研究等、大胆な発想で元気に未来を切り開くようなテーマに取り組んでいる。
本書の要点
- 要点1かつて規制色が強かった航空産業は、「オープンスカイ」と呼ばれる規制緩和により、激しい競争がおこなわれる産業に変貌した。
- 要点2航空会社の提供する「運送」という商品は、在庫がきかず、他社との差別化も難しい。一方で、固定費はきわめて大きく、空港などのインフラ整備や規制などにも左右されてしまう。
- 要点3航空会社の経営において重要なのは、どこからどこへ路線を張るかという「ネットワーク戦略」、いつ・いくらで・どのように座席を売るかという「プライシング」、顧客囲い込みのための「マイレージプログラム」をどう設計するかである。
要約
航空の歴史と政策
航空輸送の歴史

kieferpix/iStock/Thinkstock
ライト兄弟が史上初の動力飛行を実現したのは、1903年のことだった。だが、そのわずか16年後には、パリ―ロンドン間で世界初の国際定期便が就航した。
このような急速な技術発展の影に、戦争の影響があったことはまちがいない。現在は平和産業である航空輸送業だが、もとはといえば戦乱で寸断された陸上輸送の代替手段として花開いていったのである。
欧米における航空産業の急速な発展に触発され、日本でも1923年までには定期民間航空会社が誕生した。しかし戦争の影が濃くなるにつれ、国内の民間航空は軍が主導する国策会社にすべて吸収されていった。
その後、1945年の敗戦にともなう「航空禁止令」により、日本からは一時、あらゆる航空産業が姿を消した。しかし1952年、日本が独立を取り戻すと同時に、民間航空の復活に向けた制度整備がおこなわれ、1954年には日本航空が戦後初の国際線である羽田発ホノルル経由サンフランシスコ便を就航。空の主権を完全に取り戻した。
国際航空を規定する「シカゴ体制」
成田や関空などの国際空港には、各国の航空会社が運行する色とりどりの航空機が並んでいる。一見すると当たりの光景に思えるが、これは日本が各国と航空協定をひとつひとつ締結した成果である。
このような航空協定の枠組みとなっているのが「シカゴ体制」だ。1944年、米国の呼びかけで52カ国がシカゴに参集し、戦後の国際民間航空のあり方が議論された。シカゴ体制とは、この会議で採択された「シカゴ条約(国際民間航空条約)」の基本的な考え方を指している。その根底にあるのは各国の領空主権の尊重である。
日本の航空機が他国に着陸する場合はもちろん、領空を通過する場合にも、その国の承認が必要になる。このように相手国の許可を必要とする運行形態は9つに分類され、「運輸権」と呼ばれている。民間国際航空における2国間協定では、運輸権の相互承認をベースに、路線や運賃など、より事業に即した内容を取り決めている。
航空自由化の流れ
シカゴ体制は、国家主権を前面に出した、規制色の強いものであった。しかし米国は、「民間国際航空にも市場原理を働かせるべき」という考えを持っており、1990年代に「オープンスカイ」と呼ばれる考え方を打ち出した。これは、運輸権の相互承認をはじめ、参入企業や運賃、便数などの規制を原則として撤廃するとともに、コードシェアやアライアンス(提携)など、複数の航空会社が協力して利便性を向上させる取り組みを認めるというものであった。
この考え方を2国間の航空協定に適用した「オープンスカイ協定」を米国と締結した国は、2016年9月時点で120カ国に上っている。この取り組みこそ、LCC(格安航空会社)の台頭や、航空会社同士のグローバルなアライアンスのきっかけをつくったのである。
機材の変遷

aapsky/iStock/Thinkstock
かつて旅客機の主役といえば、ジャンボジェットの愛称で知られるボーイング747のように、4発のエンジンを搭載した大型機であった。しかし2000年前後から燃料コストの高まりに加え、米国同時多発テロ事件などによる需要低迷を受け、現在の主役は2発エンジン(双発)の中型機に替わっている。この主役交代の理由には、双発機の長距離運行性能が向上したこともある。実際、双発機でも、いまでは地球上のほぼすべての場所を飛行することが可能だ。
また、パイロットの訓練コスト低減に配慮してつくられているのも、最近の機材の特徴である。たとえばエアバス社は、主力となる各機種の共通性を高めることで、パイロットが他機種に乗務を変更する際の移行訓練期間を、従来の半分以下にすることに成功している。
航空会社の戦略と経営
航空運送業の特徴・使命・環境
航空運送業の本質は、「A地点からB地点に人や貨物を運送すること」だ。
一方で、需要変動が大きな商品を扱っているにもかかわらず、供給力の調整が難しい。

この続きを見るには...
残り2320/3929文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.11.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約