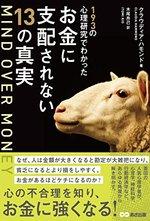「意味」と「価値」のギャップ
アジアの人々と消費を共有する時代

昨今、日本企業によるアジア市場進出が続いている。しかし、華々しく進出したにもかかわらず、思うような成果を挙げられていないという話もよく聞く。一方日本では、アジアの人を中心とした「訪日観光」が盛り上がり、多数のアジア人観光客が日本を訪れている。「爆買い」と称される日本での「大量買い」を目的にして来る人も少なくない。今や、日本人とアジアの人々が国境を越えて消費を共有する時代がやってきたのだ。
では、企業の海外市場での成否は何が決めるのだろうか。そして、アジアの人々は日本で何を「爆買い」しているのか。著者は、たとえ同じ商品や店舗であっても、それぞれの市場によって全然違う「意味」と「価値」がつけられているという。そして、その市場による「意味づけ」と「価値づけ」こそが、人の消費行動の原動となるカギだとしている。
たとえば、100ヶ国以上に店舗を持つマクドナルドは、その運営やメニューはかなり統一されているものの、国によって店の持たれるイメージが異なる。アメリカでは「安くて安心感があり、ひとりでも子連れでも気兼ねなく入れる店」である。これに対し、インドでは「週末に家族で出かける少し高級な店」、中国では「子供の誕生日パーティーを開く店(開いてみたい憧れの店)」ととらえられている。つまりマクドナルドは、市場によって異なる意味づけをされ、異なる価値を提供しているのだ。
インドネシアでポカリスエットはなぜ売れたか
ポカリスエットは東南アジア・中東の20ヶ所の国と地域で販売されている「グローバル商品」である。大塚製薬がポカリスエットを初めてインドネシア市場に持ち込んだのは、1989年、インドネシアであった。1997年には現地に工場を建設して本格的に参入を果たしたが、売れ行きはさっぱりだった。熱帯気候のインドネシアではわざわざスポーツで汗を流すこともないし、湯船に浸かる習慣もない。また、国民の大半がイスラム教徒のため二日酔いになる人もいない。つまり、日本では効果をあげてきた「体の渇きを癒すイオン飲料」というコンセプトが通用しなかったのだ。
そこで大塚製薬は「発汗」「渇き」といったシーンの根本的な見直しを図り、「デング熱」に注目した。デング熱は40度以上の熱と激しい下痢が続き、脱水症状を起こす、熱帯特有の感染症だ。ポカリスエットを「デング熱患者向け水分補給剤」として医療機関や医師に売り込みを始めた結果、インドネシア人の間で広く認知されるようになった。そして、次第に「脱水症状全般に効果のある飲料」として意味づけをされていった。さらには、「イスラム教のラマダン(断食)時の脱水症状に効く」という、新たな価値シーンが出現し、ポカリスエットは爆発的に売れるようになった。
大塚製薬はこの発見により、一気に巨大市場(日本の2倍の2億4000万人市場)を手に入れた。ここで重要なのは、デザインや機能(中身)の変更をせずとも、商品の持つ意味と価値を変えただけで商品が売れるようになったことである。つまり、見た目では確認できない「現地適応化(ローカル化)」がされたということだ。
吉野家の海外戦略

2017年6月時点、中国を中心としたアジアで約650の店舗を持つ牛丼チェーンの吉野家。アメリカ進出は1975年にさかのぼる。当時は「ビーフボウルのアメリカ進出」と話題となったが、結果は惨敗であった。米を主食せず、また赤身ばかりを食べてきたアメリカ人に、牛丼の価値が伝わらなかったというのが大きな理由だ。