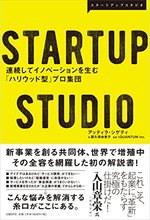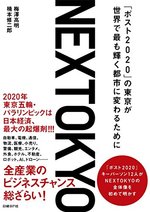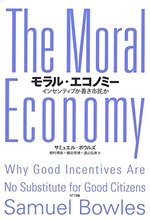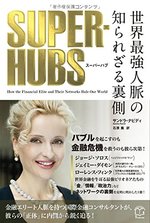大前研一ビジネスジャーナル No.14
企業の「稼ぐ力」をいかに高めるか
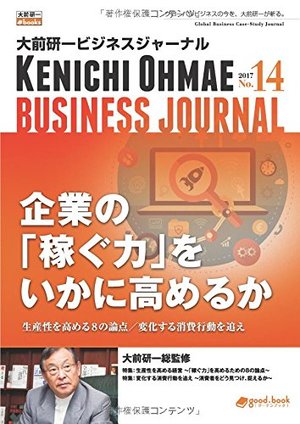
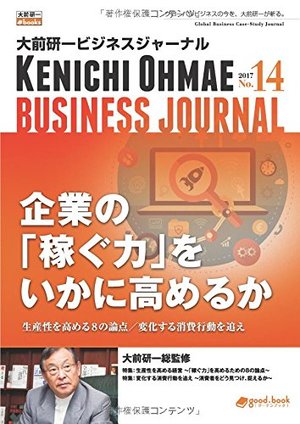
著者
大前 研一(おおまえ けんいち)
株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長/ビジネス・ブレークスルー大学学長
1943年福岡県生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院原子核工学科で修士号、マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、常務会メンバー、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。以後も世界の大企業、国家レベルのアドバイザーとして活躍するかたわら、グローバルな視点と大胆な発想による活発な提言を続けている。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長及びビジネス・ブレークスルー大学大学院学長(2005年4月に本邦初の遠隔教育法によるMBAプログラムとして開講)。2010年4月にはビジネス・ブレークスルー大学が開校、学長に就任。日本の将来を担う人材の育成に力を注いでいる。
株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長/ビジネス・ブレークスルー大学学長
1943年福岡県生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院原子核工学科で修士号、マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、常務会メンバー、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。以後も世界の大企業、国家レベルのアドバイザーとして活躍するかたわら、グローバルな視点と大胆な発想による活発な提言を続けている。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長及びビジネス・ブレークスルー大学大学院学長(2005年4月に本邦初の遠隔教育法によるMBAプログラムとして開講)。2010年4月にはビジネス・ブレークスルー大学が開校、学長に就任。日本の将来を担う人材の育成に力を注いでいる。
本書の要点
- 要点1日本企業が「稼ぐ力」をつけるには、1時間あたりの付加価値額を上げ、高付加価値化した商品を高値で売り出すことに取り組むべきだ。定型業務や非定型業務の混在する間接業務を徹底的に仕分けして、コア業務以外はIT化や外部委託をする業務改善などが効果的な方法だ。
- 要点2新時代の消費者のキーワードとなるのは、「越境EC」「インバウンド消費」「ラグジュアリー消費」だ。企業は、対象を広くとらえて新時代の消費者を見つけ、その消費者を「待つ」のではなく「呼び起こす」よう働きかけることが重要になる。
要約
生産性を高める経営
低下する日本企業の「稼ぐ力」
世界的に見て、日本のホワイトカラー層は労働時間が長く労働生産性が低い傾向にあり、日本企業の「稼ぐ力」は大幅に低下しているといえる。際立って生産性が低いのが、管理業務などの売り上げに直結しない業務を担当する、「間接人員」である。これは、様々な雑用的な仕事まで修行と称してやらせる、日本的な新規採用・人材育成の方法の弊害である。このために、間接人員の業務は定型業務と非定型業務の霜降り肉状態になってしまうのだ。
非効率な間接人員の問題を改善せず、日本企業は原価全体に利益を上乗せする「コストプラス」の方法で、商品やサービスの価格設定をしてきた。が、それでは行き詰まってしまう。
企業は自ら生まれ変わるべき

cbies/iStock/Thinkstock
日本は人口オーナス期に入っており、人手不足の上に生産性が低いとなれば、1人当たりの労働時間は当然増える。そのために働き方改革が大きな注目を集めている。が、長時間労働是正に国が介入し、規制だらけにしては、企業はおかしくなってしまう。現に、電通などの広告会社やテレビ局が、クリエイティブな業務を外部の下請け会社に委託するという例が多発している。
つまるところ、労働生産性は従業員1人当たりの付加価値額である。それを書き換えれば、(付加価値額/売上高)×(売上高/労働時間)×(労働時間/従業員数)とも表すことができる。すなわち、付加価値率×1時間当たりの売上高×1人あたりの労働時間、ということである。1人当たりの労働時間を高めることには既に限界がきているが、最初の2つはまだ高めることができる。その2つの積は、(付加価値額/売上高)×(売上高/労働時間)=付加価値額/労働時間であるので、つまり1時間当たりの付加価値額となる。
企業は、長時間労働で付加価値を生み出すビジネスモデルから自ら脱却し、イノベーションや業務の改善で高付加価値化を達成し、労働生産性を高めるべきだ。そうやって、高付加価値の商品に高い値段をつけて売りに出していく力こそ、「稼ぐ力」なのだ。
スタイリッシュなスイスの時計、スウォッチには、250万円もの高額がつけられているものもある。これは、実際の製作コストを反映している値段ではなく、ブランドが提示している付加価値の値段なのである。これこそ、企業の「稼ぐ力」が表れた実例だといえるだろう。
【必読ポイント!】いかにして企業の「稼ぐ力」を高めるか
間接業務の生産性を向上させる
企業の「稼ぐ力」を高めるためにはどうしたらよいか、大前氏は8つの論点を挙げているが、ここではそのいくつかを紹介したい。
「稼ぐ力」を高める上で一番効果的なのは、先にも述べた間接業務の徹底した仕分けだ。まずは自社のコアとなる事業を明確にする。その上で、定型業務と非定型業務を分け、コア業務と非コア業務を分ける。その上で、業務プロセスを標準化し(Standard Operating Procedure、すなわちSOPの作成)、廃止すべき業務、社外に出す業務、社内に残す業務というふうに、業務を選別する。加えて、IT化する業務、人がこなす業務も区分けする。
ひとつひとつの間接業務には、経理の月次のリポート、商品別の売上実績など、全部名前がつけられるはずである。名前をつけて、それぞれのコストを見直し、コスト低減案を作成する。SOPはこのときにも役に立つ。たとえば、誰も使わないレポートを作成しているなど、受益者がいない間接業務は、廃止するか質や頻度を下げるなど、コストを低くしていく。そうすると、だいたい4割くらいの間接業務が不要になる。
そして、トップマネージメントの仕事として、クリエイティブな仕事を任せられる人材を、SOPに合わせて見つける。
中間管理職は必要か

SunnyGraph/iStock/Thinkstock
このICT時代においてミドルマネージメントはいらない。例えば、鴻海精密工業(ホンハイ)に買収されてからのシャープでは、社長に就任したホンハイグループの副総裁、戴正呉(タイセイゴ)氏が社員全員に直接メールするという。中間管理職がいると、あいだで余計な忖度が起きて、上の言葉が下にそのまま届かなかったり、途中で止まったりする。
クリエイティブなミドルマネージメントは必要だが、このような、非効率極まりない間接業務を担当しているミドルマネージメントは不要だ。社員どうしの連絡は、メール一通送ればいいのである。
どのような「人材/機械のポートフォリオ」を構成するべきか
業務を仕分けしていくと、効率はおそらく10倍くらいになり、社内に残るのは10分の1くらいになる。残るのは、クリエイティブな仕事をする人間だ。人材について、クラウドソーシングやビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)、AIやロボットまで含めてどのような構成にしていくのか、という「人材/機械のポートフォリオ」を考える必要がある。
今や日本でも、間接業務をアウトソーシングするサービスを提供する会社は増えている。たとえば、

この続きを見るには...
残り2586/4616文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.04.10
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約