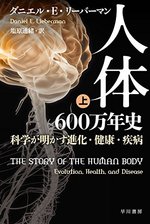カズオ・イシグロ入門
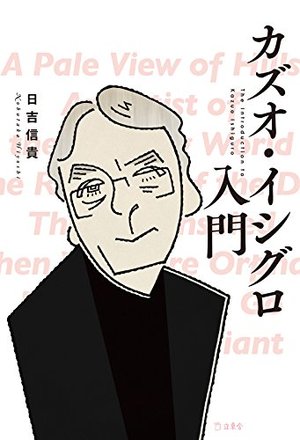
カズオ・イシグロ入門
著者
著者
日吉信貴(ひよし のぶたか)
1984年愛知県生まれ。神田外語大学、千葉商科大学非常勤講師。東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻修士課程修了。共著に『ノーベル文学賞にもっとも近い作家たち』(イシグロを担当)がある。
1984年愛知県生まれ。神田外語大学、千葉商科大学非常勤講師。東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻修士課程修了。共著に『ノーベル文学賞にもっとも近い作家たち』(イシグロを担当)がある。
本書の要点
- 要点1カズオ・イシグロは日本の長崎で生まれたが、父親の仕事の都合で幼少期に渡英し、イギリス国籍を取得した。1982年に長編小説『遠い山なみの光』でデビュー。『日の名残り』はブッカー賞を受賞し、人気作家としての地位を築く。2017年にはノーベル文学賞を受賞した。
- 要点2イシグロ作品の特徴として、主人公の記憶がしばしば自身の都合によって歪んでいること、その主人公の一人称の語りによる物語が多くの場合、読者を欺くことなどがあげられる。
- 要点3イシグロの初期作品は日本を舞台としているが、彼は、デビュー前から、日本という出自が高い商品価値をもつことを予想していたと考えられる。
要約
【必読ポイント!】イシグロとは誰か
石黒一雄からカズオ・イシグロへ

MattiaATH/iStock/Thinkstock
現代イギリスを代表する作家カズオ・イシグロは、もともとは日本の長崎で生まれた、石黒一雄であった。海洋学者であった父親がイギリス政府から招聘されたため、1960年、イシグロは両親と姉とともに長崎を発った。滞在期間は当初の予定よりもだいぶ伸びて、イシグロは1989年まで日本の土を踏むことはなく、また、その後も日本で暮らすことはなかった。そして、実用上の理由でイギリス国籍を取得することになる。
幼い日のイシグロにとっては、自分の面倒をよく見てくれた祖父が大切な存在であったが、渡英によってその死に目にあうこともかなわなかった。『浮世の画家』と『充たされざる者』に描かれている、少年と祖父の間の親密な関係には、作家自身の祖父への憧憬があらわれているといえるのではないだろうか。
イシグロ一家の渡英当時、まだ現地では日本人はめずらしい存在であった。カズオ少年は初等教育から高等教育に至るまで一貫してイギリスの学校で教育を受けた。両親とは日本語で話し続けていたものの、それはイシグロ自身の言葉によれば「五歳の子供の日本語」であり、彼は漢字を習得し損ねた。そのため、イシグロの使用言語は英語であり、その作品も全て英語で書かれている。
作家としての出発
1973年にグラマー・スクールを卒業したあと、イシグロはロック・ミュージシャンを目指しつつ職を転々とする。しかし、1974年から78年までケント大学で英文学と哲学を学んだあと、ミュージシャンへの道を断念し、作家の道へと転向した。イシグロは1979年から80年まで、イースト・アングリア大学大学院の創作科に在籍している。この期間に執筆したであろう3作の習作的短編小説は、1981年にイギリスのフェイバー社の新人アンソロジー集に収録された。
そして、3作の主題を掛け合わせ、イシグロは『遠い山なみの光』を執筆した。同作にて、1982年に作家デビューを果たす。『遠い山なみの光』は、ウィニフレッド・ホルトビー賞に輝き、13の言語に翻訳された。
1986年には、敗戦直後の日本を舞台にした『浮世の画家』でウィットブレッド賞(現コスタ賞)を受賞、そして1989年には、イギリスの老執事の無様な生を描き出した『日の名残り』によってイギリス最大の文学賞であるブッカー賞を受賞するに至る。30代半ばという若さでの受賞は当時としては異例のことであった。本作によって作家としての地位を確立したイシグロは、前衛的な実験小説である『充たされざる者』や『わたしたちが孤児だった頃』で新境地に挑戦し、2005年に発表された長編小説『わたしを離さないで』は映画化や舞台化のみならず、日本ではテレビドラマ化もされた人気作となった。
その後、初の短編集、『夜想曲集――音楽と夕暮れをめぐる五つの物語』、7作目の長編『忘れられた巨人たち』を発表し、2017年にはイシグロはノーベル賞を手にすることになる。
イシグロ作品あらすじ
『遠い山なみの光』

bbargueiras/iStock/Thinkstock
日本人女性悦子は、夫と祖国を捨て、長女景子をつれて渡英し、イギリス人の新たな夫シェリンガムとの間に次女ニキをもうけた。イギリス社会と新たな父、さらには妹までにも馴染めなかった景子は、長じてからマンチェスターの貸家で首つり自殺を遂げる。
物語では、今や親元を離れてロンドンで暮らしているニキが、イギリスの片田舎に住む悦子のもとに帰省する五日間と、悦子の長崎時代の回想とが描かれる。ニキの再訪を機に、悦子はかつて景子を身ごもっていたころ、長崎で過ごした数週間の日々を振り返ることになるのだ。
長崎時代の回想は、夫の父親である緒方と、戦争未亡人の佐知子を軸として進んでいく。ニキ訪問時の逸話と、長崎時代の回想の関係が少しずつ明かされる構成になっており、なぜ悦子が当時のことを語る必要があったのか、最後に読者は気づくことになる。
『浮世の画家』
かつてはその名をよく知られていた老画家・小野益次は、現在は豪邸で次女紀子とともに隠遁生活を送っている。その語りは、過去と現在をたびたび往復し、様々な蛇行と迂回を繰り返すが、彼の当面の関心は紀子の縁談にある。父親のもとを訪れた長女節子は、妹の見合いの破談は、小野の過去によるのではないかとほのめかす。
小野は、戦争下の日本で、戦意高揚のためのプロパガンダ絵画を制作し、名声をほしいままにしていたのだ。多くの弟子を抱え、政界での権威も得たが、敗戦を機にその地位を失った。

この続きを見るには...
残り2592/4439文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.04.16
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約