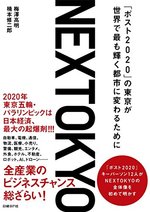江副浩正

著者
馬場 マコト (ばば まこと)
1947年石川県金沢市生まれ。1970年早稲田大学教育学部卒業。
日本リクルートセンター、マッキャン・エリクソン、東急エージェンシー制作局長を経て、1999年より広告企画会社を主宰。JAAA第4回クリエイティブ・オブ・ザ・イヤー特別賞のほか、日本経済協会賞、ACC話題賞、ロンドン国際広告賞ほか、国内外広告賞を多数受賞。第6回潮ノンフィクション賞優秀作、第50回小説現代新人賞、受賞。著書に『戦争と広告』(白水社)、『花森安治の青春』(潮文庫)、『朱の記憶 亀倉雄策伝』(日経BP社)ほか多数。
土屋 洋 (つちや ひろし)
1946年大阪府豊中市生まれ。大阪大学文学部卒。1970年日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)入社後、採用広告事業、デジタル通信事業、教育研修事業に従事後リクルートスタッフィング監査役、2007年リクルート定年退職。株式会社メンバーズ入社後監査役(2007~2017)。
著書:「採用の実務」(日経新聞社)、「新卒採用の実際」(日経新聞社)、「人材採用成功実例集」(アーバンプロデュース)、「eラーニング導入ガイド」(共著、東京電機大学出版局)。
1947年石川県金沢市生まれ。1970年早稲田大学教育学部卒業。
日本リクルートセンター、マッキャン・エリクソン、東急エージェンシー制作局長を経て、1999年より広告企画会社を主宰。JAAA第4回クリエイティブ・オブ・ザ・イヤー特別賞のほか、日本経済協会賞、ACC話題賞、ロンドン国際広告賞ほか、国内外広告賞を多数受賞。第6回潮ノンフィクション賞優秀作、第50回小説現代新人賞、受賞。著書に『戦争と広告』(白水社)、『花森安治の青春』(潮文庫)、『朱の記憶 亀倉雄策伝』(日経BP社)ほか多数。
土屋 洋 (つちや ひろし)
1946年大阪府豊中市生まれ。大阪大学文学部卒。1970年日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)入社後、採用広告事業、デジタル通信事業、教育研修事業に従事後リクルートスタッフィング監査役、2007年リクルート定年退職。株式会社メンバーズ入社後監査役(2007~2017)。
著書:「採用の実務」(日経新聞社)、「新卒採用の実際」(日経新聞社)、「人材採用成功実例集」(アーバンプロデュース)、「eラーニング導入ガイド」(共著、東京電機大学出版局)。
本書の要点
- 要点1すべてのはじまりは大学新聞向けの広告とりだった。この経験から江副は、「広告だけの本」を思いつく。経費はすべて広告費でまかなうという事業モデルは、日本のあらゆる情報誌の原点となった。
- 要点2「日本株式会社の人事部」として人事・教育事業での地位を確立したリクルートは、その後「情報産業」へと拡大。一時代を築いた。
- 要点3江副の贈り物好きが災いし、「リクルート事件」は起きた。これにより江副は会長職を辞することになっただけでなく、最終的にはリクルートの経営にまったく関われなくなってしまった。
要約
「日本リクルートセンター」ができるまで
すべては東京大学新聞からはじまった

jaimax/iStock/Thinkstock
1955年に晴れて東京大学へ進学した江副浩正(以下、江副)だったが、当時はとにかくお金がなかった。だから駒場の本校舎1階にある「アルバイト委員会」へ行き、アルバイト募集のビラを確認するのが日課だった。
転機となったのは大学2年の頃だ。いつものように「アルバイト委員会」へ赴くと、そこには「月収1万円。東京大学学生新聞会、新規体制に向けて営業急募」と書かれている。当時としては破格のアルバイト料だ。実際に話を聞いてみると、1万円というのは昔そういう学生がいただけで、実際はそこまで稼げないという。だがたとえ歩合制でも、がんばれば月1万円になるかもしれない。
江副は間もなくやってくる東大入試に目をつけた。合格者の名前が出る東大受験号は、受験者であれば誰もが買うはずである。ならば合格者名簿の記事と予備校広告を一体化させ、実際の試験問題に対する有名予備校講師の模範解答も載せてみたらどうか。結果は大成功だった。
とはいえ受験時以外にも、広告を集める必要がある。そこで次に江副が目をつけたのが求人広告だ。東大生を募集するうえで、東大新聞ほど効率のよいものはないと江副は考えた。当時勢いをもちはじめた証券会社に目をつけ、積極的に営業した。
就活シーズンが終わるころになると、江副の月収は20万近くになっていた。サラリーマンの給与が、よくて月1万円の時代である。江副は就職ではなく起業を志すようになり、創業パートナーと「大学新聞広告社」を設立するにいたった。
「企業への招待」とリクルートの誕生
当時は好景気で、どの企業も大卒新規採用を積極的におこなっていた。東大新聞だけではなく、その他の大学新聞への広告出稿も取り扱いはじめると、江副の会社の規模はさらに拡大。個人ではなく法人としての運営に切り替え、会社名も「株式会社大学広告」に変更した。
この頃から大学新聞広告事業に次いで、入社案内や学生名簿の作成も事業に加わった。クライアント企業の特徴や将来性をうまくまとめながら、各大学の就職課から学生の氏名と住所を書き写し、入社案内を学生に発送する。徹夜作業が続いたものの、充実した日々を過ごした。しかし同時に「僕らの仕事は本当に学生のためになっているのだろうか」という思いが、江副のなかでくすぶっていた。
企業の就職広告を提供するだけなら、広告とりにすぎない。こうした危惧を抱いた江副は、新しい事業として「広告だけの本」を思いついた。得意先からの広告費ですべてをまかない、無料で配る。しかも企業の立場からではなく、あくまで学生の立場から求められているものをつくるのだ。
こうして「企業への招待」(後の「リクルートブック」)が生まれた。学生からの反響は大きく、初年度こそ純利益はゼロだったものの、日本のあらゆる情報誌の原点となった。1963年8月からは配布対象を私大にも拡げ、募集大学別に細分化。社名も「大学広告」から「日本リクルートセンター」(以下、リクルート)に変更した。
素手でのし上った男
「日本株式会社の人事部」

Bet_Noire/iStock/Thinkstock
創刊されてからわずか1年にもかかわらず、「企業への招待」は就職希望の学生にとってなくてはならないものになった。それまで企業の人事部は、指定校の学生課とゼミ教授の推薦制度に採用を頼っていた。だが応募者が増えつづけていたことから、企業は正確な適性検査の導入を必要としていた。

この続きを見るには...
残り2251/3666文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.04.27
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約