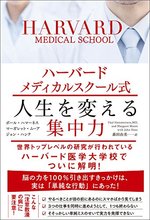結婚と家族のこれから
共働き社会の限界

著者
筒井 淳也(つつい じゅんや)
1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部卒業。同大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。現在、立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学・計量社会学。著書に『制度と再帰性の社会学』(ハーベスト社)、『親密性の社会学』(世界思想社)、『仕事と家族』(中公新書)などがある。
1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部卒業。同大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。現在、立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学・計量社会学。著書に『制度と再帰性の社会学』(ハーベスト社)、『親密性の社会学』(世界思想社)、『仕事と家族』(中公新書)などがある。
本書の要点
- 要点1古代社会では男女関係は、現代に近い自由なものであった。古代末期から中世にかけて、「家父長制度」が登場した。近代化にともなって男女は「家」から独立したが、女性の家族生活は政治的理由と経済的理由によって、男性支配をともなうものだった。
- 要点2女性が雇用労働の世界に進出して、共働き社会になった。しかし、共働き社会の本格化は経済格差の問題を引き起こし、不自由な親密性の世界を生み出している。
- 要点3家族を気軽に作れる社会のほうが、人々は積極的に家族を形成できるようになる。
要約
これまでの家族
自由な古代社会

jacoblund/iStock/Thinkstock
まずは、男女関係における古代社会と現代の類似性についてみていこう。出発点となるのは「食べていくこと」だ。食べていけるだけの経済的な生活基盤がなければ、生きていけない。逆にいえば、生活基盤が確保されていれば、結婚や家族のことは、比較的自由に決められる。
日本の古代社会の庶民にとっては、村落共同体が生活基盤であった。集落を離れると、生きていくことはほぼ不可能だった。
集落にとって重要なのは、みんなが協力しあって農作物を収穫することだ。そこでは、子どもは重要な労働力である。誰の子どもなのかについては、それほど重視されなかった。子どもが共同体のなかで健やかに育ち、将来の労働力になってくれればよい。よって、血統を守ることに重大な関心が注がれることはなかった。
すると、恋愛や結婚における男女関係は多少緩くなる。実際のところ、古代社会では、好きになったら体の関係を持ち、そのまま結婚し、子どもを持った。そして、気づいたら別れていることも多くあった。男性も女性も、同時に複数の相手と親しい仲になることがあり、「誰かと付き合っているときは他の人と付き合ってはならない」という強い規範もなかった。これを「対偶婚」という。
このような人間関係のあり方は、女性の生活基盤の確保が前提となる。日本の古代社会では、庶民なら村落共同体のなかに、支配層なら親族からなる絆のなかに、女性がしっかりと埋め込まれていた。そのため、配偶者である男性、つまり「家族」に依存する必要はさほどなかった。
家父長制度の登場
古代社会の自由な人間関係のかたちは、古代末期から中世にかけて、大きく変わっていった。私たちが「伝統的家族」として理解している「家父長制度」が登場する。
家父長制度は、男性優位の社会体制と家族体制からなる。具体的には、家長が「家」の社長となり、妻や子どもの処遇を決めるというものだ。息子の結婚相手として誰を家に迎えるのか。娘の結婚相手としてどの家を選ぶのか。こうしたことは家長に決定権があった。また、家の財産である「家督」も、家長から次の家長に譲り渡された。女性は多くの場合、財産の所有権を持っていなかった。
家父長制的な家族のあり方が典型的に見られたのは、武士階層においてだ。武士は、戦争で手柄を得ることによって「家」を確立させ、主君から土地をもらう。そこで農民を使って食料生産を管理して食べていく。土地は武士個人ではなく、「家」が引き受ける。そのため、家族は、労働力となる子どもではなく、家長の血を引いた子どもを必要とする。
そうすると、子どもは間違いなく「父の子」であることが重要になるため、男性は単婚や一夫多妻制を選択した。一方、女性は、生まれてくる子どもが誰の子かがはっきりわかるよう、他の男性との肉体関係を厳しく禁じられた。
「家」からの離脱

Halfpoint/iStock/Thinkstock
明治時代、家父長制度はいっそう厳格化した。明治民法が規定した家父長制には、多くの権限が家長(基本的に「父」)に与えられていた。例えば、家長は、「戸主権」と呼ばれる、家族の行動についての決定権も広く持っていた。子どもの結婚は、家長の同意なくしてはできない。家族がどこに住むのかも、家長の命令の範囲内で決定された。
家父長制度から自由になるためには、家長が握っている経済力から自立しなければならなかった。「家」から離れる一般的な手段は、自分で商売を始めるか、あるいは会社に雇ってもらうことだった。
明治政府はこの時期、経済の近代化といえる工業化を進めていた。やがて工業が重工業化し、商業や金融業にもその動きが拡大していった。人々は会社に雇われて自分の稼ぎを得ることで、親からの経済的自立を獲得していった。雇用されるという働き方が都市部に浸透するにつれて、家父長制度はその根底を掘り崩されていったのである。
【必読ポイント!】 家族のいま
性別分業が進んだワケ
雇用労働の一般化によって、家長はもはや「家」の社長ではなくなった。どこに住んで、誰と結婚するかは自分で決めたいという男性が都市部で増えた。
しかし、女性については事情が異なっていた。職業女性は基本的に未婚女性であり、結婚と同時に退職するケースが大半だった。一部の例外を除くと、女性が結婚後も家業以外で職業人として働き続けるケースはほとんどなかった。経済の近代化にともなう「家からの個人の離脱」。これは、離脱した先の家族生活において、性別分業や男性支配をともなうものだった。そして「女性の非労働力化」が進んだ。
一見、女性を差別する根拠はないように思われるが、なぜこのような状況になったのか。著者は2つの理由をあげている。1つ目は政治的な理由だ。経済拠点が家から工場や会社に移っても、家での男性優位の体制が継続した。
2つ目は経済的な理由だ。「家」が経済活動である自営業は、私生活を送る場と、稼ぎのために働く場が重なっていた。しかし、勤め人は通勤のため、日中は家を不在にする。小さな子どもがいる家庭では、誰かが家でその面倒を見なくてはならない。よほど稼ぎの良い女性であれば、子育てを他の人に任せて働きに出ることは可能だ。しかし、女性の労働賃金は通常はそれほど高くない。そのため、多くの女性にとっては外で働き続けることの経済合理性がなかった。
理想の親密性
女性は、欧米主要国では1960年代、日本でも1980年代ころから徐々に雇用労働の世界に進出していった。結婚後も継続して働き続けるようになった。
では、男性も女性も自立し、自由に結婚したり別れたりするような社会が到来したのだろうか。この状態を、著者は「リベラル派の理想の親密性」が実現した社会と呼ぶ。関係を取り結ぶのも、人間関係から撤退することも自由ならば、必ずしも家族という形態を選ぶとは限らない。よって、「理想の家族」ではなく「理想の親密性」と表現している。「親密性」は、家族、友人関係、恋愛関係、同棲などを含む広い概念を指す。しかし、このような「リベラル派の理想の親密性」は、実現していない。
私たちが向かっているのは、一組の男性と女性がともに稼いで協力して家族を支える「共働き」社会だ。男女が雇用を通じて経済的に自立し、自由に人間関係を築くためには、次の3つの条件が必要となる。それは、安定した雇用が男女に行き渡っていること、家事や育児のサービスが何らかの形で提供されていること、そして高齢者が少なく、それを支えるコストが小さいことである。ただし、現実には、これらの条件がそろうことはまず難しい。
共働き社会の「落とし穴」

evgenyatamanenko/iStock/Thinkstock
性別分業の社会から共働き社会への移行には、いくつかの背景がある。まずは、オフィスワーク中心の働き方が普及し、女性が高学歴化するにつれて、女性が雇用労働の世界に入ったことだ。
もう1つの背景は、男性の雇用の不安定化である。欧米では、男性の10%以上が失業しており、この傾向は特に若い男性に顕著だ。そこで、欧米の若者は、異性と同居し、ともに稼ぐことで困難を乗り切ろうとしている。女性も男性と同じくフルタイムで働くことが多いため、長時間働くケースは少ない。女性が働きやすいように、様々なサポート制度や労働規制が発達した。いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現だ。
「共働きの異性愛カップル」の増加は、日本政府がワーク・ライフ・バランスの実現や女性活躍推進に力を入れていることからわかるように、理想の状態だと考えられている。
しかし、共働き社会には、「落とし穴」と呼ぶべき問題がある。その1つは経済格差に関わる問題だ。かつての性別分業の時代には、夫が働いて給与を得るので、多くの妻は専業主婦になり、労働所得を得ることはなかった。夫の所得では子どもの教育費を賄えない場合、妻がパートで働いて家計を補助していた。つまり、夫の稼ぎのある家庭のほうが、妻の稼ぎは少なくて済む。経済学では、これを「ダグラス=有沢の法則」と呼ぶ。
ところが、フルタイムの共働きカップルが増えていくと、たとえ全体的な賃金格差が縮まっていても、世帯所得の格差は広がっていく。というのは、所得の高い男性がやはり所得の高い女性と結婚し、他方で所得の低い男女が一緒になることが多いからだ。つまり、所得という面での同類婚が格差をもたらすといえる。
このほか、家族のケア・サービスを外部化することの悪影響といった問題については、本書に譲りたい。
家族のみらい
家族がリスクになる社会

BrianAJackson/iStock/Thinkstock
共働き社会を促進することで、家族が「リスク」になりうると著者はいう。アメリカでは「家庭の職場化」という現象が起きている。共働きカップルが、家庭と仕事の両立をマネジメントするなかで、家族生活がもはや単純に安らぎをもたらすものではなくなりつつある、ということだ。
現在の日本も、特に女性にとっては、仕事と家族の両方をマネジメントするような社会になりつつある。男性にとっては、仕事上の挫折は他でもない仕事の領域で生じるのかもしれない。だが、女性にとっては、家庭生活が仕事の挫折の原因になりえる。
家族マネジメントがうまくいかなければ、女性は結婚・出産、あるいは介護を機にキャリアの転換を余儀なくされる可能性がある。このまま共働き社会化が本格的に進めば、今度は夫と妻は「共同経営者」として、仕事と家庭を調整しながら運営しなければならない。しかし、どれもうまくいかず、いずれかが犠牲になることも多いことだろう。
仕事が家庭のリスクになり、家庭が仕事のリスクになり、両方が人生のリスクになる。これは、まさに「不自由な親密性の世界」だ。
家族主義からの離脱
著者は、気軽に結婚し、気軽に子どもを作ることができる社会、家族が上手くいかなくなってしまったとしても、それほど困らない社会をめざすべきだという。「家族で失敗できないぞ」というプレッシャーがある社会では、人々は家族から逃避してしまう。
逆説的だが、家族を気軽に作れる社会のほうが、結果的には家族がうまくいくのではないか。なぜなら、家族以外の支援が得られ、人々が家族の本来の良さを楽しめるようになり、家族が壊れてしまうリスクを軽減できるからだ。
よって、家族主義から離脱し、「家族がなくても生活できる」社会の実現を著者は提言する。そうすれば、人々は家族を積極的に形成するのではないだろうか。

この続きを見るには...
残り0/4198文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.05.04
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約